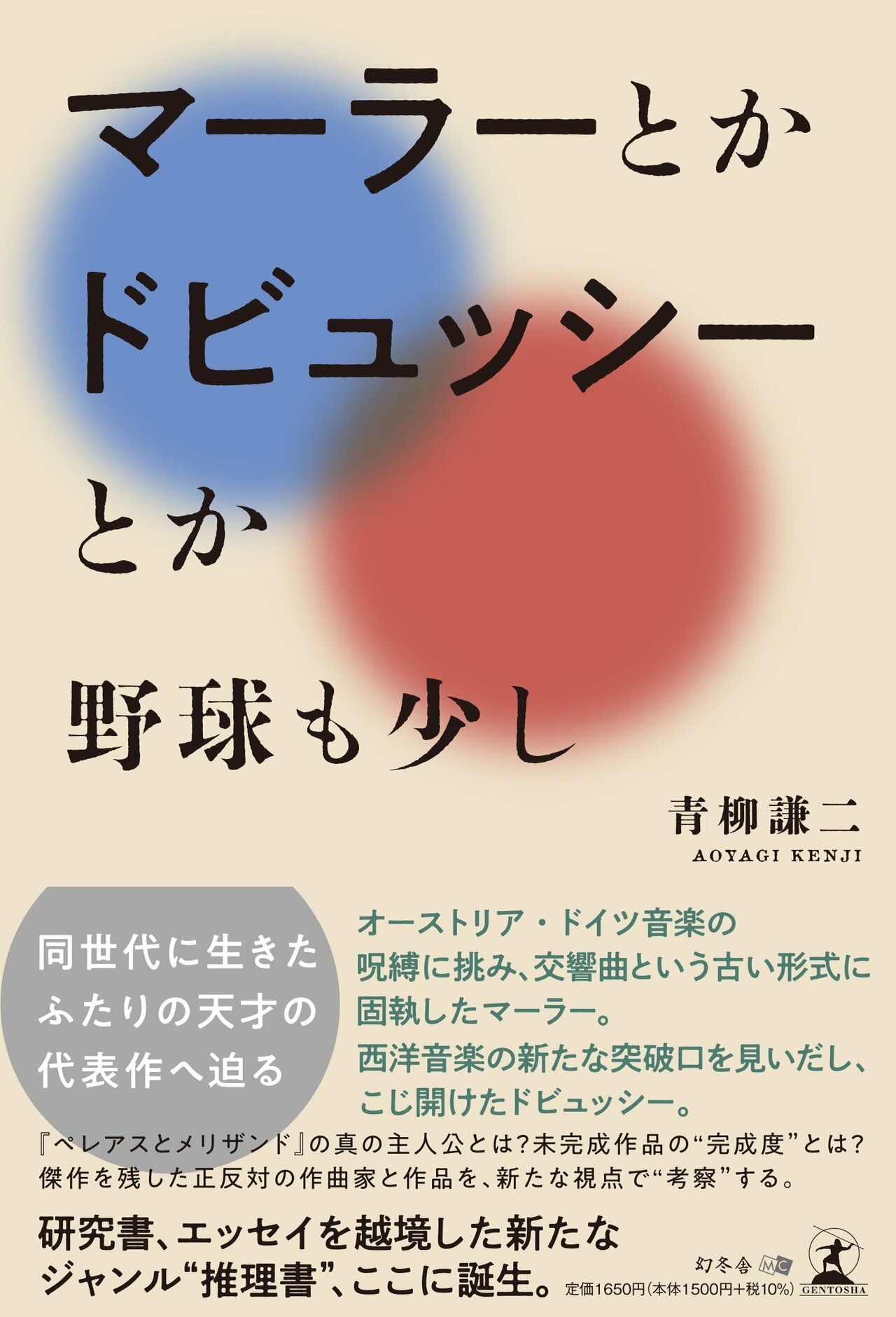だからこそある作品に対するアプローチも種々様々だが、それを異なる言葉で表現すれば多数の切り口が存在するということになるだろう。その複数の切り口こそが、構造主義的用語で言えば異なる分節の網で対象を掬い取ると言い換え可能だろう。だから対象全体を隈無く掬い取ることは至難の業で、むしろ複数の分節の網の妥当性と非妥当性を考慮することが重要だ。
言い方を変えれば、また平たく言えば、構造主義の一つの貢献は、物事は分かることは分かる、分からないことは分からないことを明らかにしたことではなかろうか。いずれにせよこのことは本文中、直近では次の序章でも触れることになる。
序章 目に付く鱗
映画『ニジンスキー』
『ニジンスキー』と題されたアメリカパラマウント映画がある。二〇世紀前半の音楽シーンを席巻したディアギレフ率いるロシアバレエ団、その花形ダンサーを描いたものだ。このニジンスキーは、ストラヴィンスキーの『春の祭典』世界初演の舞台を振り付けたことでも有名だが、精神障害を患い後半生は不遇に終わった。
映画ではロシアバレエ団の主要な演目も再現されており、これも映画としては本格的で貴重な記録だ。特に『春の祭典』はリハーサル風景も収録され、舞台場面は短いものの、マリインスキー劇場の全曲DVDが出るまでは得難い映像だった。
ほかにもドビュッシー『遊戯』も部分ながら再現されている。映画は後に妻となるロモラの伝記に基づき記録映画風に構成され、ロシアバレエ団内部の人間関係も赤裸々に描かれている。とても興味深く貴重な映画だ。
この映画のある場面で、ロモラにバレエ教師が次のようなことを言うシーンがある。「高くてうまいランチをおごってくれ。いや、味は期待すまい。ここはロンドンだ」私はこの台詞に妙に納得した。ロンドンとは言わず、イギリスでは味は期待できないのだ。
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...