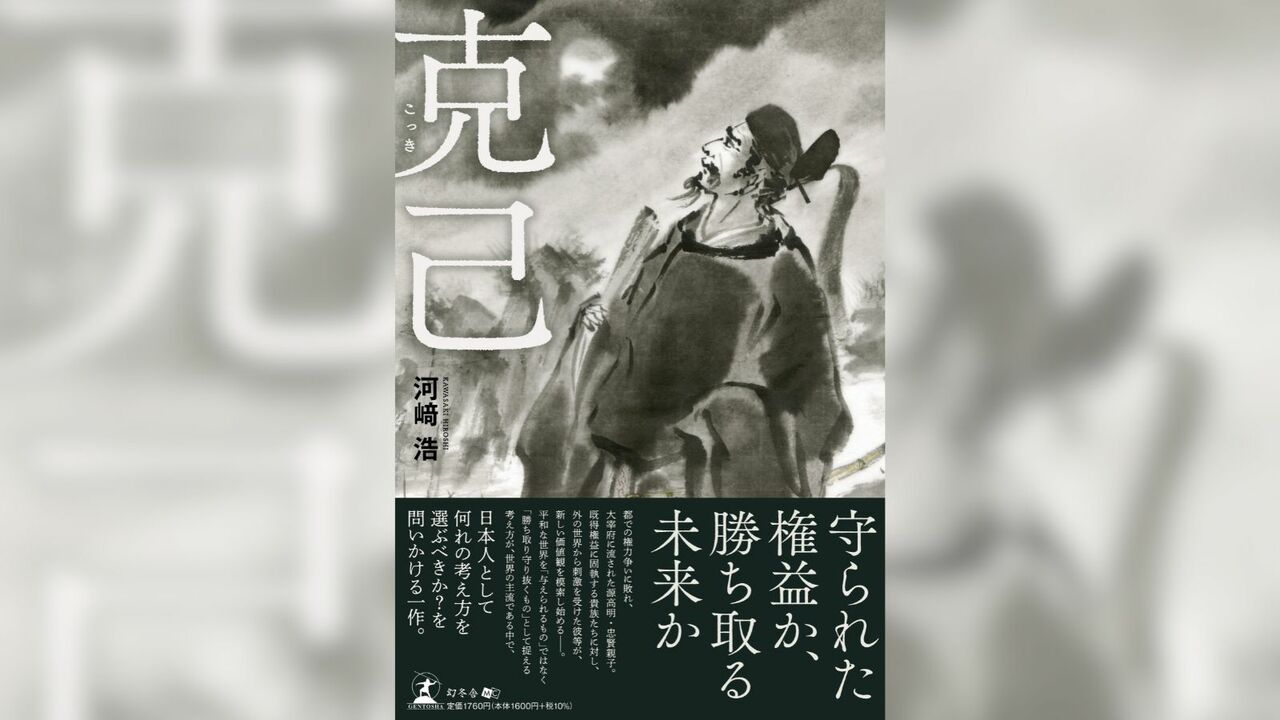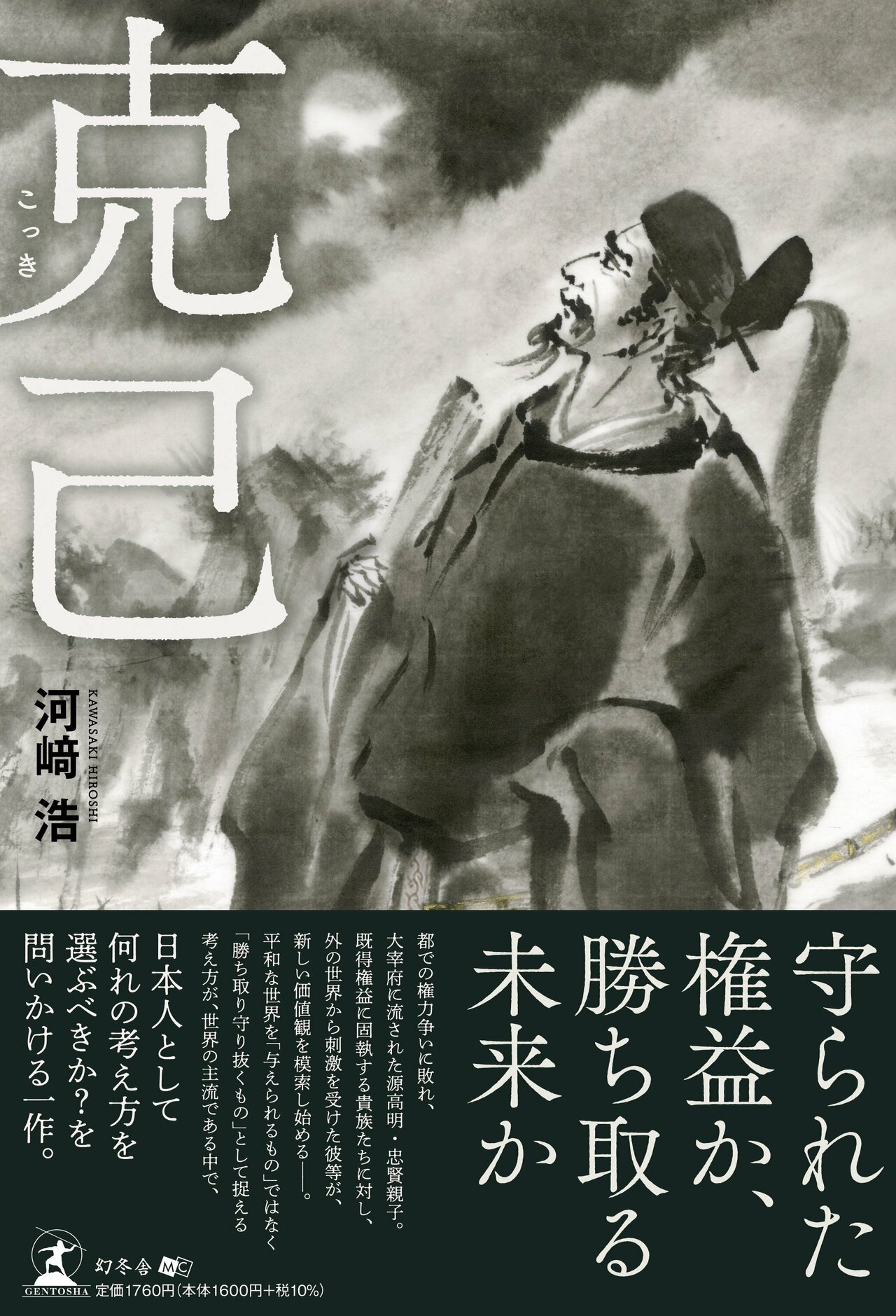【前回の記事を読む】隠岐へ流罪になった藤原千晴を監視せよ、との依頼。だが彼は、平将門の乱で名を馳せ、束になっても返り討ちに遭うこと確定の腕前で…
プロローグ
「其の方に、これ為(な)る先の左大臣、この度、大宰府の権帥に任官される源高明様が、お連れになった、藤原千晴卿を隠岐の島まで護送する任を依頼したいのじゃ」
「はっ」
マムシは、首を垂れて上司の言葉を恭しく拝聴したが、心の中で
『冗談じゃない。この御仁は、何時も、使える人間を使い倒し、使えない人間を放置して居(お)る。儂等は、こんな使えない人間達を食わす為に、身を粉にして居る訳ではない』と常々思っていた。
「ではお殿様、実頼卿にご依頼されていた、お腰のモノ(太刀)や、今年の年貢の取り立てに関しての〝責〟に関し、儂は、任を離れても構わぬ。と考えて宜しいのですね?」
決定打であった。荘園を預かる藤原某は、二の句が出なかった。上座に控えていた忠賢は、此の者は〝馬鹿では無い〟と感じた。
「如何した?」父の言葉は、おっとりとしていたが、十男故、臣籍降下しているとは言え、先々代(醍醐帝)の息子、故に最上位、一時(いっとき)は、正二位・左大臣に迄、上り詰めていた貴族らしく振舞ってはいた。
しかし、答え様(よう)に依っては、〝只では済まさぬ〟と云う、帝(みかど)の息子。源家独特の迫力が、その言葉には在った。
高明は、以降、武家の棟梁として知られる、清和源氏とは異なる系統の、延喜御後と称される源氏の創始者ではあったが、彼自身、雅(みやび)の出なれど、武辺に長けた剛の者として、都で(当時)は、一目置かれていた。
「はっ」
荘園を預かる司である地頭は、高明の迫力のある問い掛けに、二の句が出ず、首を垂れるのみであった。
忠賢は、少し救いの手を差し伸べてやるか、とばかりに、若い好奇心を発揮した。
「其の方、其の腰のモノはなんじゃ」
マムシは、腰に吊るした三尺は無い小太刀を、腰帯から外し恭しく掲げて、忠賢の前に伺候(しこう)した。
彼は、造りは〝大した事は無い〟その小太刀を、鞘から抜いてみようとした。
その瞬間、右手に持つ、安っぽく見えた柄(つか)は、手に馴染み、真鍮製らしき、鎺(はばき)は単純な造りであったが、しっかりと刀身を鞘に固定し、実用本位の鍔もしっかりと咥えていた。
腕に覚えのない者から見れば、只の造りか〝粗末な〟刀にしか見えないが、触った瞬間、忠賢は、マムシと呼ばれていた男の顔を〝まじまじ〟と眺めた。
彼は『解(わか)ったか? 小僧』とでも言わぬばかりに、ニヤついていた。
この二人の様を高明も見逃さなかった。
「それを持って、近う」
そう言って、息子を呼び寄せた。