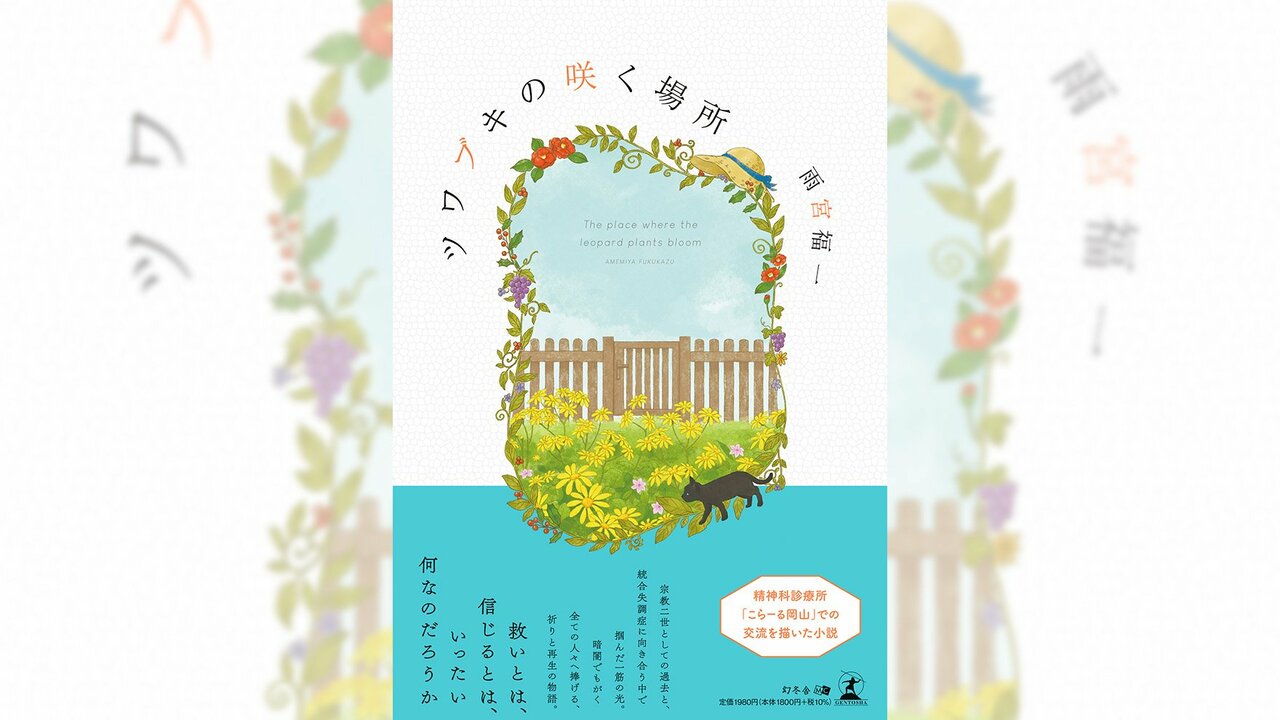【前回の記事を読む】「韓国へ行くの。聖地巡礼をしましょうね」激情が込み上げそれを拒否した。母に飛び掛かり、体を叩き続けた。
第一章 靴
【 二 】
その時である。背後に嗚咽が聞こえてきたのは。それは、空港内の喧騒を切り裂いて届くほどの、激しいむせび泣きの声であった。
あの声は、私を制止した若い男のものではないか。男はこちらに姿を見せないままで、私にはただ、彼の泣く声だけが聞こえる。声を嗄らすほど泣くことができるその人のことが、羨ましかった。
(僕だって本当は泣きたい。でも、何かを変えたい時に泣いてたって、何にもならないんだ)
草原で女の子を救い出せなかった日、私はこのことを、心に刻みつけていたのであるから。
タラップを進み、飛行機に乗り込む。母は私を、右奥の窓際の席に座らせる。
「お母さん、やっぱり行くの?」
そう聞きながら母の手を握ろうとしたが、母に素早く拒まれて、私の手は虚しく空をつかむ。
手狭な飛行機のエコノミー席で、離されてゆく母の手が瞳に焼き付いている。母は何にも答えてはくれず、私の方を見ようともしない。
耳元に冷房の風が抜けていく。そこかしこで、韓国語でなされる会話の声がしている。
帰国して家族に会うのを楽しみにしている人もいれば、帰ると仕事がまた始まるから億劫だとおどけてみせる人もいる。
母と私のように、布施のために韓国へ行く者など一人もいない。
「こんにちは。ドリンクサービスに参りました」
キャビンアテンダントがにこやかにやって来ても、母はむっつりと押し黙り、返事をしない。
機内にて、私たち二人だけが、透明なガラスの部屋に閉じ込められたかのように別の時間を過ごしていた。
私と母との関係は、その日から大きく変わることになる。
私たちは互いに気持ちが通じなくなり、分かり合うための努力さえできなくなっていった。韓国に到着した後、母は食事や買出しのときの以外は、七泊八日の旅程のほぼすべてを涼しいホテルで過ごすありさまであった。
聖地巡礼がふいになって喜ぶ私と対照的に、あの時の母の顔からはすべての感情が抜け落ちていたのを思い出し、無性に悲しくなることがある。
日本に帰国した後。
私は精神科へ連れて行かれた。母が医師に何かの相談をしている。思い返せば、母と私の関係について相談に乗ってくれる人物が医師の中にいたのかもしれない。
だが、少なくともこのことは確実に言える。私が幼少期にかかった精神医療は、ろくなものではなかった。
真っ暗な深淵に私を引き込み、私は今なおこの時分の記憶から自由になれない。
旅が終わるころには母と私の進み行く道は遠く分かたれ、千切れてばらばらになっていた。
雲がその同じ形状を二度と回復せぬように、夏の日の思い出は追憶の彼方に消えていくのである。