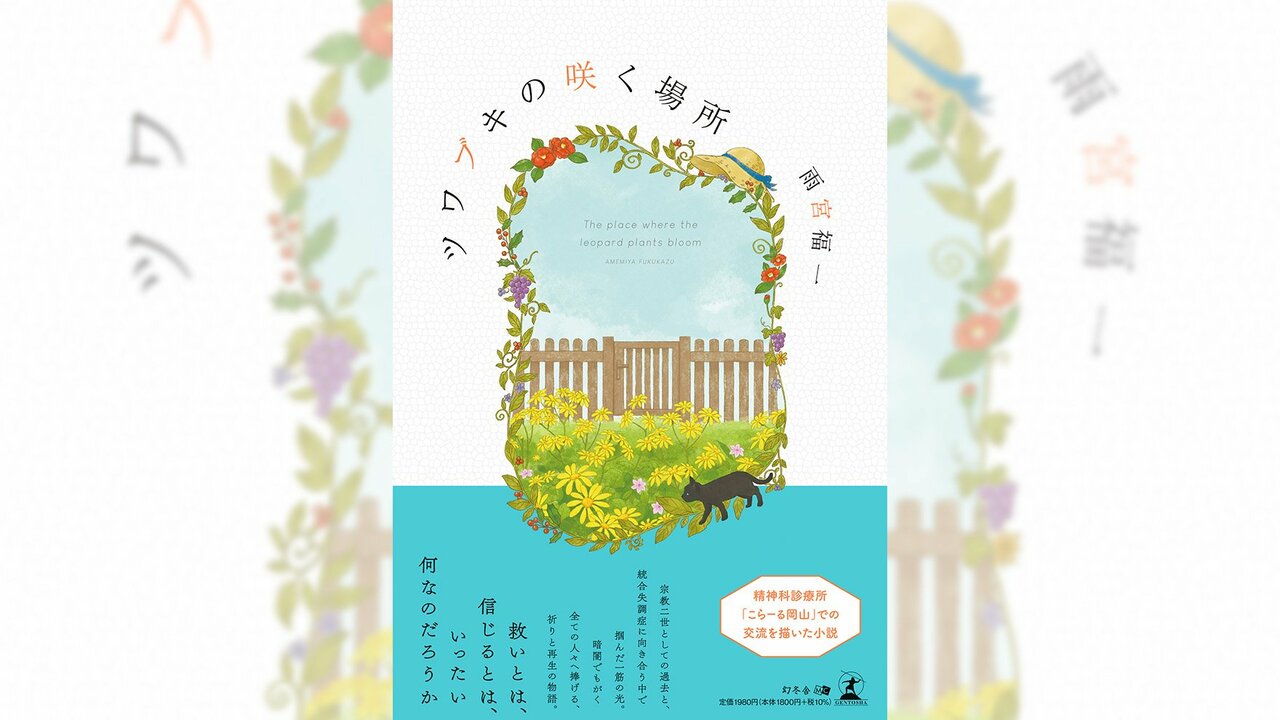【前回の記事を読む】久しぶりに書いた妹の名前。できない気持ちの塊が音や匂いを引き連れて、こちらへ近づいてくるような気配さえした。
第一章 靴
【 一 】
鉛筆が手を離れ、かたんと音を立てて床に落ちる。ハッと我に返り、目を見開いた。
「しまった!」
私のメモ帳は、繰り返しの言葉で真っ黒に埋め尽くされている。
何かできたんじゃないか。ごめんなさい。
何もできなかったじゃないか。ごめんなさい。
そんな言葉を延々と書き連ねた。しまいには鉛筆の芯が折れてしまって、無我夢中で、それでも何かを記そうとして紙をこそげた跡だけが虚しく残るのみである。
少女のことを追想するうち、こんなことを書いたのだと思えば合点がいく。妹へ送ることのできる文面では、到底ないように思われる。
「……茜」
そっと妹の名を呟いてみる。久しく呟くこともなかった妹の名を。
妹が生まれてからずっと、彼女のことを大切に思ってきたけれど、私は深い罪の意識に苛まれていた。救えなかったあの時の女の子の姿が、心の深層で妹と重なり合うためだろうか。私の意識はその心的事実を認めようとしない。怖かったのだ。
茜はあの日の少女でないというのに、同一人物であるかのように思ってしまう自己の錯覚が、私には空恐ろしいものと感じられた。茜を救うこと。茜を愛すること。
それらに類した尽力をもって、何もしてあげられなかったあの女の子に報いることなぞ、とてもじゃないができないことである。でも本当は、そんな風に穿って考えたりせず、茜は茜として、妹として大切にすればそれでよかった。
私の意識は茜を少女と同一視することに固執していた。草原のただ中で人形のように揺られる彼女の脚を思ううち、私はやがて一つの答えを考え付いた。