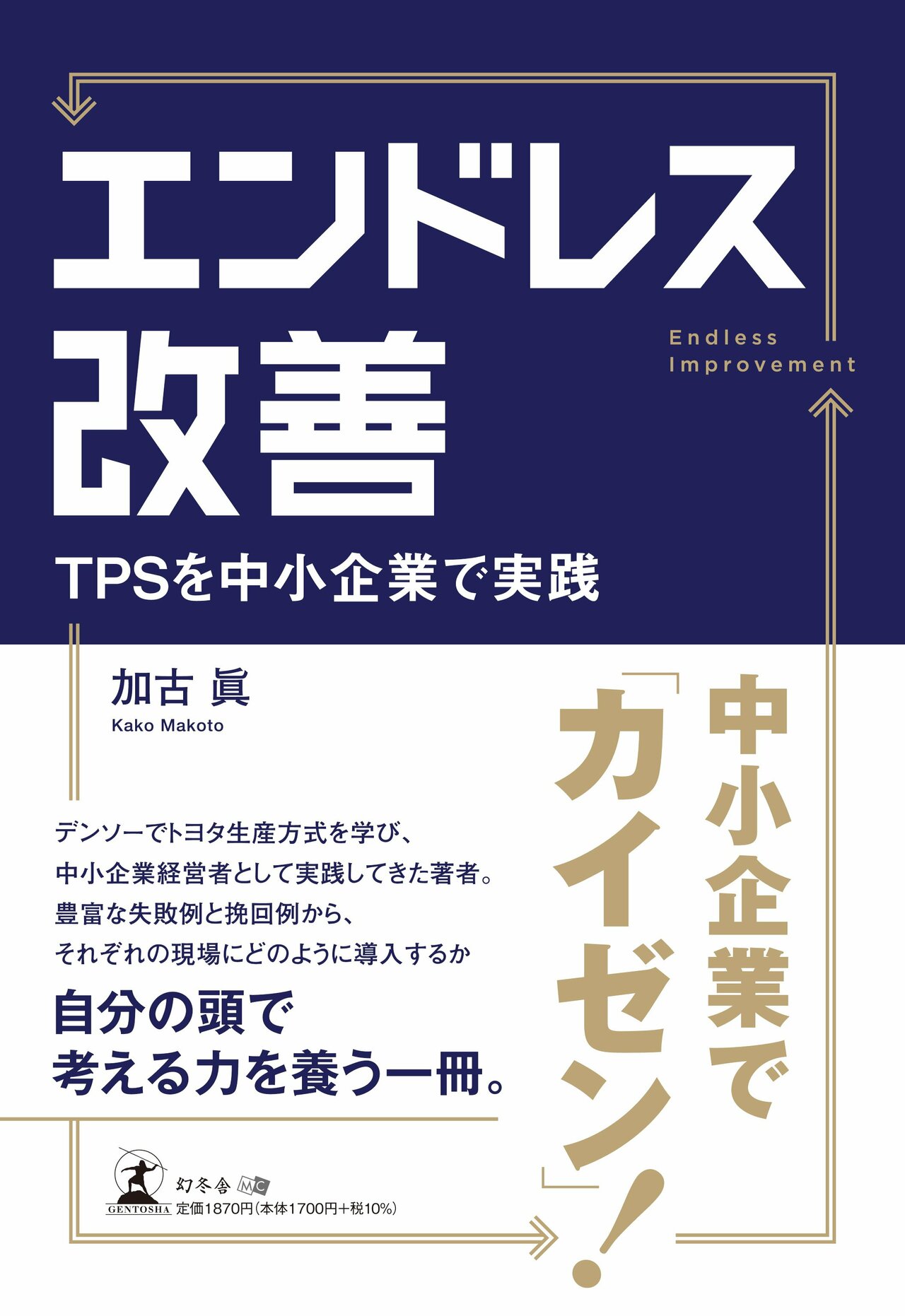事例(5)グラフは「手書き」で、体で感じる!(管理帳票の活用)
生産現場には程度内容の差はあるものの、どの工場でも管理帳票があり、掲示されているケースが多いと思う。
これは、事務部門や営業部門でも同じことがあると思う。
管理帳票は、何のために記入し、掲示されているんだろうか?とそれぞれの職場で考え直してもらうと、それなりの答えが見つかると思う。
従業員の中には「仕事」というよりは「作業」として決まっていることを実行しているケースが散見される。
こうした人達に対してもこの管理帳票は、過去・現在の現場状態を正確に表しているものが多いので、活用してもらいたいもの。また、目標との対比も容易にできる。
単なる実績記録、計画と実績、QC7つ道具といわれる各種の管理図などを思い起こしてもらい、記入中と記入後に眺めている人や見ている時間はどれ程だろうか? その時間の少なさにヒヤッと気づくことが多くある。
まずは、記入段階。私は、グラフは『手書きで!』をいつも主張している。
前回までの記入結果に加えて新たに「1つの点」を書き込む。普通の人ならば、そのポイントが前回と比べてどうなっているのかを考え、気にするはず。
その次に、前回の点と今回の点を線で結ぶ。コンピュータに頼れば、データをインプットするだけで、正確に新しいプロットが加えられ、同時に前回データと結んだ「線」もキレイに正確に書いてくれる。
もう1度、「2つの点を線で結ぶ」行為を振り返ってみよう。
普通は、この2つの点を小さな定規をあてがい、鉛筆で両点を結ぶ。この時に、あてがった定規の角度、傾きが目標線の位置、または月間積み上げ目標線の角度とどれ程違っているのを一瞬、1、2秒だけでも味わってもらい、何かを感じ、何かに気づいてもらいたいもの。
もう少し、大げさに言えば「グラフ線にあてがった定規の傾きを体で感じる、味わう」こと。
一瞬でも、悔しい思いをしたり、達成感を味わったりしその時に「何でだろう?」と考える時間を大切にしたいと思う。
本連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...