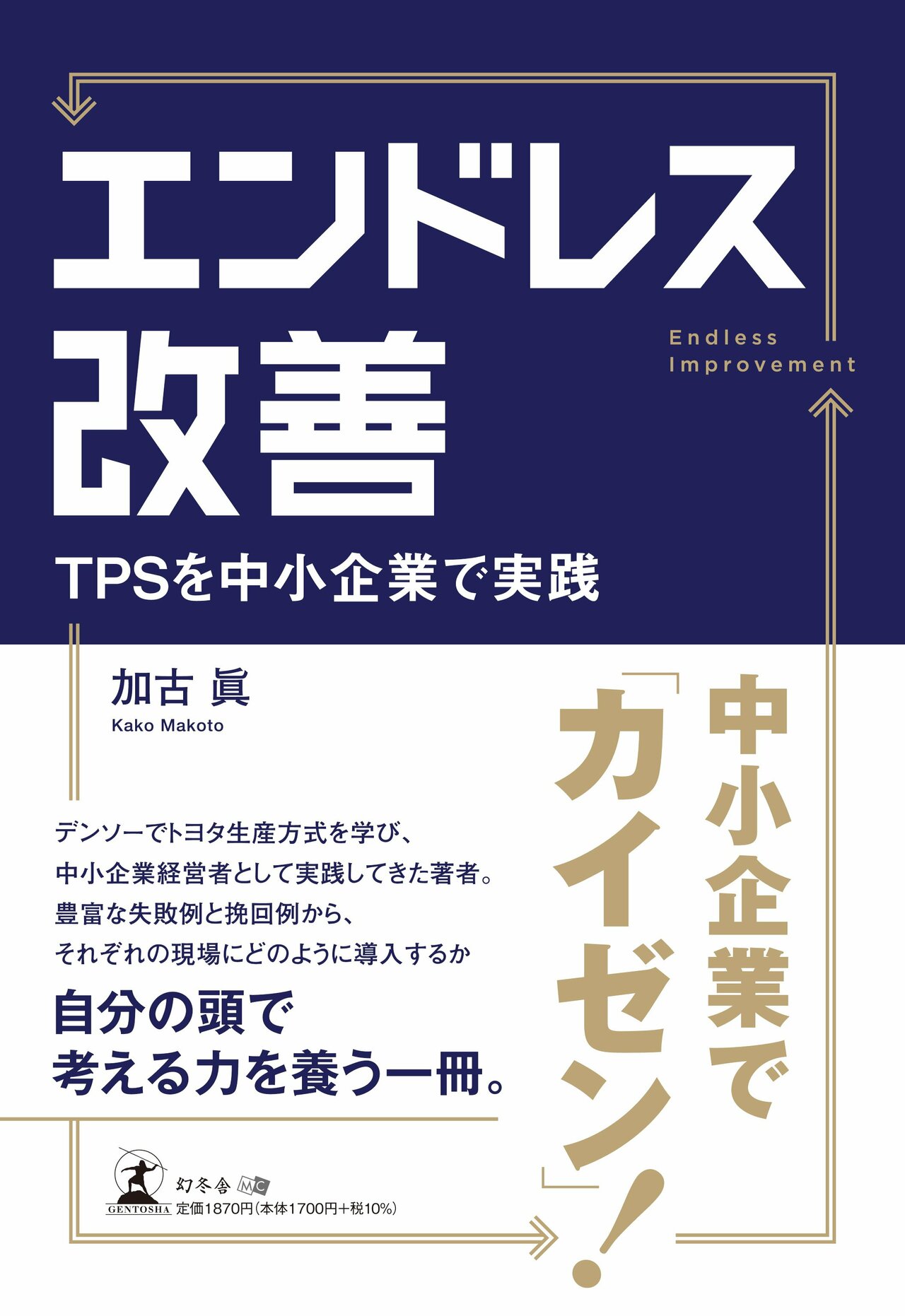ここで、私の身の回りであったうまくいかなかった事例から、変化点ボードの使い方そのものの改善を含めて、この変化点ボードを使って「問題点を見つけやすくする」ことに発展していきたいポイントをレベル別に示す。
①「目に見えた変化だけを書き出す」レベル
誤りではないのだが、如何にも工場管理者、現場監督者としては寂しい。
目に見えた変化の「要因、原因、わけ」を一瞬で良いので、考えていることのキーワードを書き込むことで、メンバー全員の「気づき」のレベルアップ、視野拡大、ひいては潜在リスクの発見、危険予知力の向上に繋がるもの。
②「前の日の記述を消さないで、前日と変わった部分だけ書き直す」レベル
一見、効率が良さそう。だんだんと「手抜き」=「考えなし、考えサボリ」が増大して、無意味なボードになってしまった。
ここが現場監督者(例えば班長)の頑張りどころ。朝礼の30分前に現場を眺め、出勤状態を確認し、前夜、前直までの稼働状況を中間在庫量、帳票、申し送り帳やメモから読み取れば、いっぱい思い付くはず。
③「1人で全部やり切ってしまう」人
班長など現場監督者の責任感の強さを認めてあげることは必要。
しかし、メンバー全体の「動き、特に心の中の動き」を気にして、少しずつでもメンバーの自らが書き加える余地を作ってあげることも大切。
ただしこの段階での指導は、個人別の適切な対応を選ぶことが肝になる。
やらされ感の排除、当事者意識の向上、参画感……ひいては、メンバー自身の「問題発見能力の強化、向上」に繋げていきたいものと今更思っている次第。
以上のように、変化点ボードを持って、使うだけでも「問題点を見つけやすくする」ことによって、次に向けた改善のキッカケやヒントがゴロゴロ出てくる。