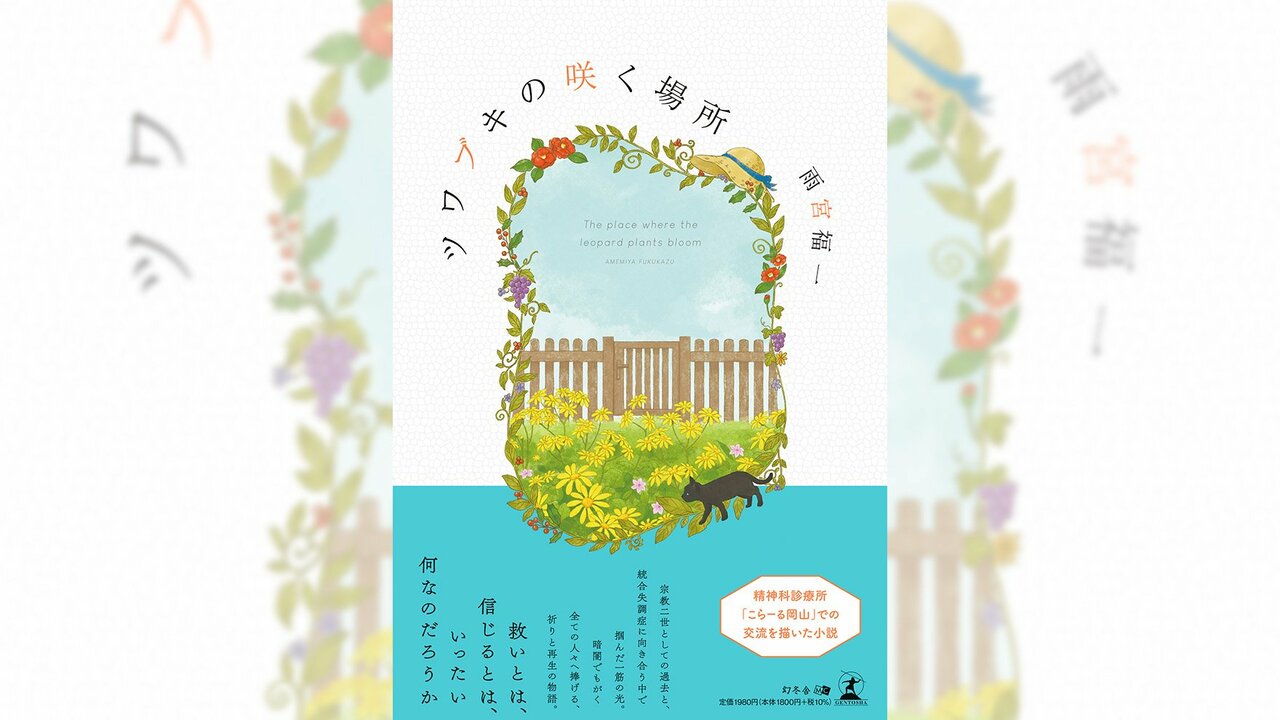【前回の記事を読む】父と母の出会いのきっかけを妹にどう伝えるか悩み…そんな私のところへやってきたのは親友の「永ちゃん」だった
第一章 靴
【 一 】
「そうか。ところでこれは、俺からの差入れだ」
永ちゃんはそう言ってから、背に背負ったリュックの中からプラスチックのタッパーを取り出した。タッパーには唐揚げが入っていて、ほかほかの状態である。彼の家の近所に唐揚げ屋があって、そこで買って持ってきてくれたようだ。
「……いつも、ありがとうな」
呟くようにぽつり、私が言えば、永ちゃんは顔をほころばせて、にかっと笑ってみせる。
「いいさ、いいさ。どうせ死んだら使えない金だ。今死ぬかもしれない、明日死ぬかもしれない。なら、使っちまって、美味しいものに消えた方がよっぽどいい」
キッチンの籠や野菜の棚へ持参した野菜を手際よく収納してゆく永ちゃんに、私は頷き返す。
「じゃあ、私が食事を作るよ」
「いいなあ。何にしてくれる?」
「そうだなあ。今日は農場から、蓮根、それにブロッコリーも届いた。よし、唐揚げと炒めて甘酢和えといこう。中華風に仕上げるよ」
美味しそうだと、楽しげに永ちゃんが言う。 少なくとも、彼といる間は手紙のことを忘れていられそうだ。そんなことを思いながら、ブロッコリーをビニール袋から取り出す。
キッチンのコンロのうえで油と蓮根が弾ける。
ジューッと音がする。永ちゃんは、手際よくブロッコリーを洗ってから一口大に刻んでゆく。そうするうち、思い出すかのような調子で永ちゃんは言った。
「そう言えば、あのヘビースモーカーもこの唐揚げ、好きだったよな」
「うん。そうだね。好きだった」
頷く私の耳元で、ヘビースモーカーこと、菅野直彦(すがのなおひこ)さんのガハハッという笑い声が響いた気がした。
彼は永ちゃんと同じく、ずっと私のそばにいてくれた親友であって、何より私に、たゆみなく生活を継続していく勇気をつけてくれた人物である。そしてまた、私がその生涯の最期を看取った人でもあった。
「今でも、ちょっとした時にあいつの詩を思い出すのさ。不思議だな、耳なじみのする昔の唱歌みたいだ」
ブロッコリーを塩茹でにしながら永ちゃんが言う。
「すずらんの花が庭に、咲いたんだ。ちっぽけな白い花。まるで君のように。しおらしく下をむいて咲いている」
私は彼が何の詩を言ってるのかにすぐ気付き、その詩を承けて続けた。
「すずらん。すずらん。耳を近づければ、君の優しい声が、鳴り響いてくるような、そんな気がした」
私が彼のことを「菅野さん」と呼べるようになったのは、いつのことだったろう。「実は詩を書くのさ」と彼が打ち明けてくれた。その時から、だったかもしれない。