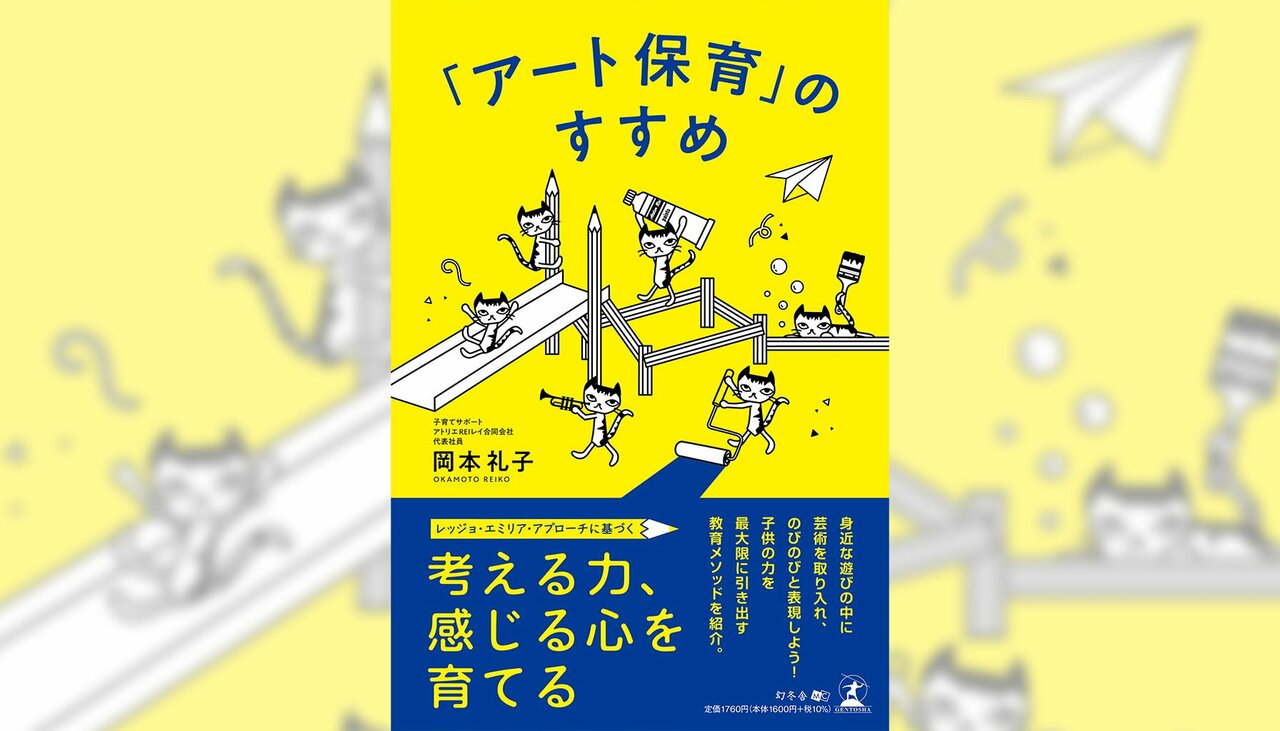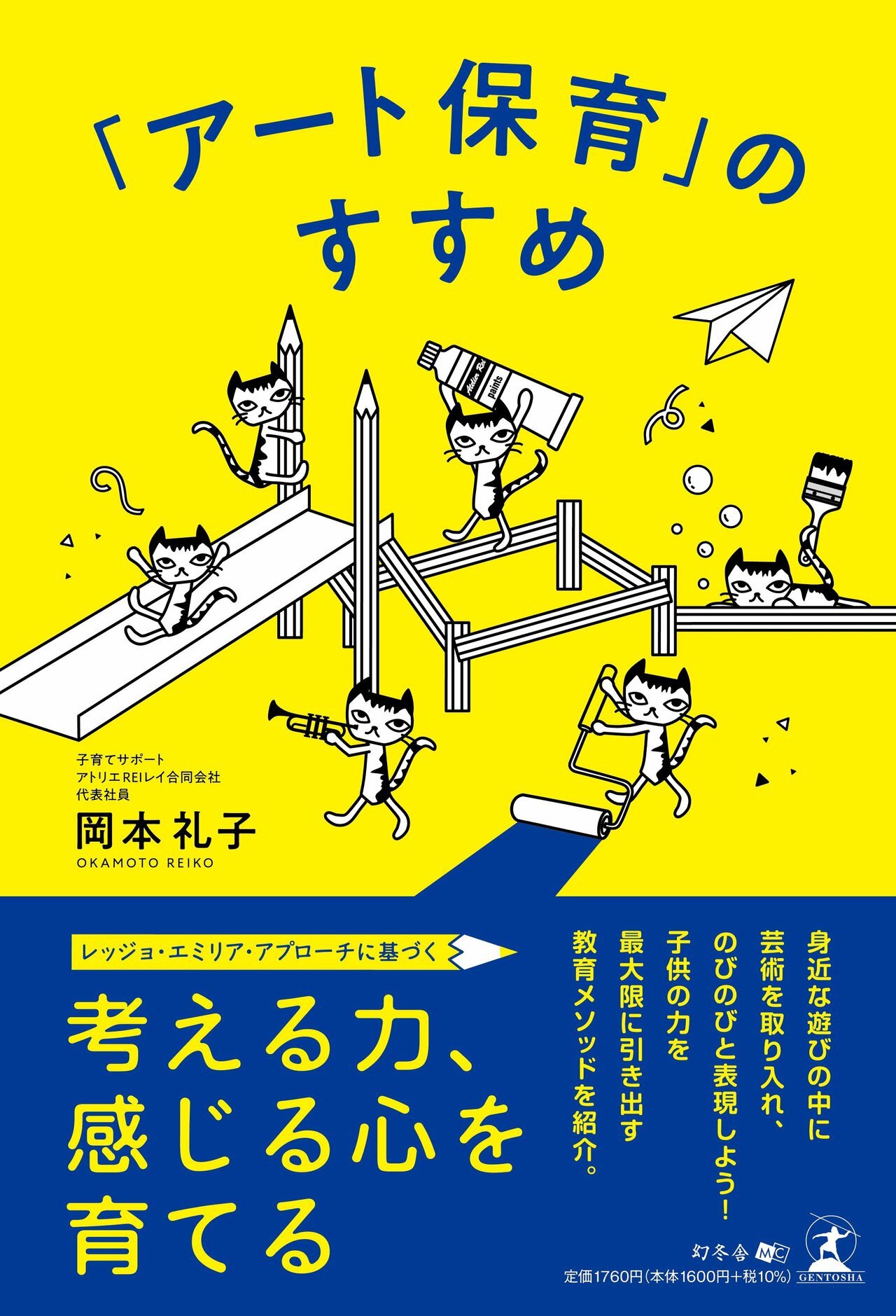【前回記事を読む】【アート保育】美意識の土台づくりをする保育。色やカタチ、素材を意識して展示をして環境を作り、「感性」を育てながら…
第1章 アートと保育を考える
「アート保育」〝ART KID KERE〟という考え方
そこで、気になったのが、イタリアのレッジョ・エミリア・アプローチ1)の考え方であり、ドイツからはじまりオランダで広がったイエナプラン教育2)の共同体の考え方です。
またフランスでは、子供たちがポンピドゥー・センターのベンチで、有名な絵の側で絵を見ながら、友達を待っているような様子で休憩している風景が自然に見られます。日本であれば、警備員に常に守られているような有名な作家の作品の前でした(ロープはあったかしら?)。
日常に名画が溶け込んでいる空間でお喋りしている風景がうらやましく、日本にもこんな風にアートが自然に溶け込んでほしいと思います。
芸術が生活の隅々に入り込んだフランスの日々を感じ、日本とのギャップを感じながら、「REIレイ式アート保育」を考えています。「アート」は、教え込んで表現するのでは楽しさは伝わりません。日々の感じることで培われていくのです。
「色やカタチをもっと楽しませて遊ばせようよ!」
必要なのは、物的アート環境と人的アート環境だと思います。そのような環境ができたら、子供たちは夢中になります。「アート」の世界が生活の中にあり、遊ぶことができます。まだまだ未熟な私の「アート保育」の考え方ですが、進化し続けていくと思います。
レイでは、アート活動を園全体で意識しながら、進めていきたいと考えてきました。できるだけ子供の感性をいじりすぎず、子供の感じたままを受け止める保育を話し合ってきたつもりです。様々なモノを並べたり、飾ったりしてアートを常に意識させています。
「レイコさんのいうアート保育は、わからない」と当時の保育士に直球を投げられました。開園から10年が過ぎようとして何となく伝わってきたのかなと思うところです。
運動会のテーマは、ある年は「紙」、ある年は「色」、ある年は「音」など、「アート」の素材を使ってみんなで遊びます。はじめた当時は、このテーマ設定は思いつきだったのです。その時の保育士はとまどい、かなりのブーイングがありました。
しかし年を重ねるごとに、子供たちと保育士とのアイデアの出し合いで、とても楽しい運動会になっています。「アート」がテーマの運動会、一風変わった取り組みだと思います。