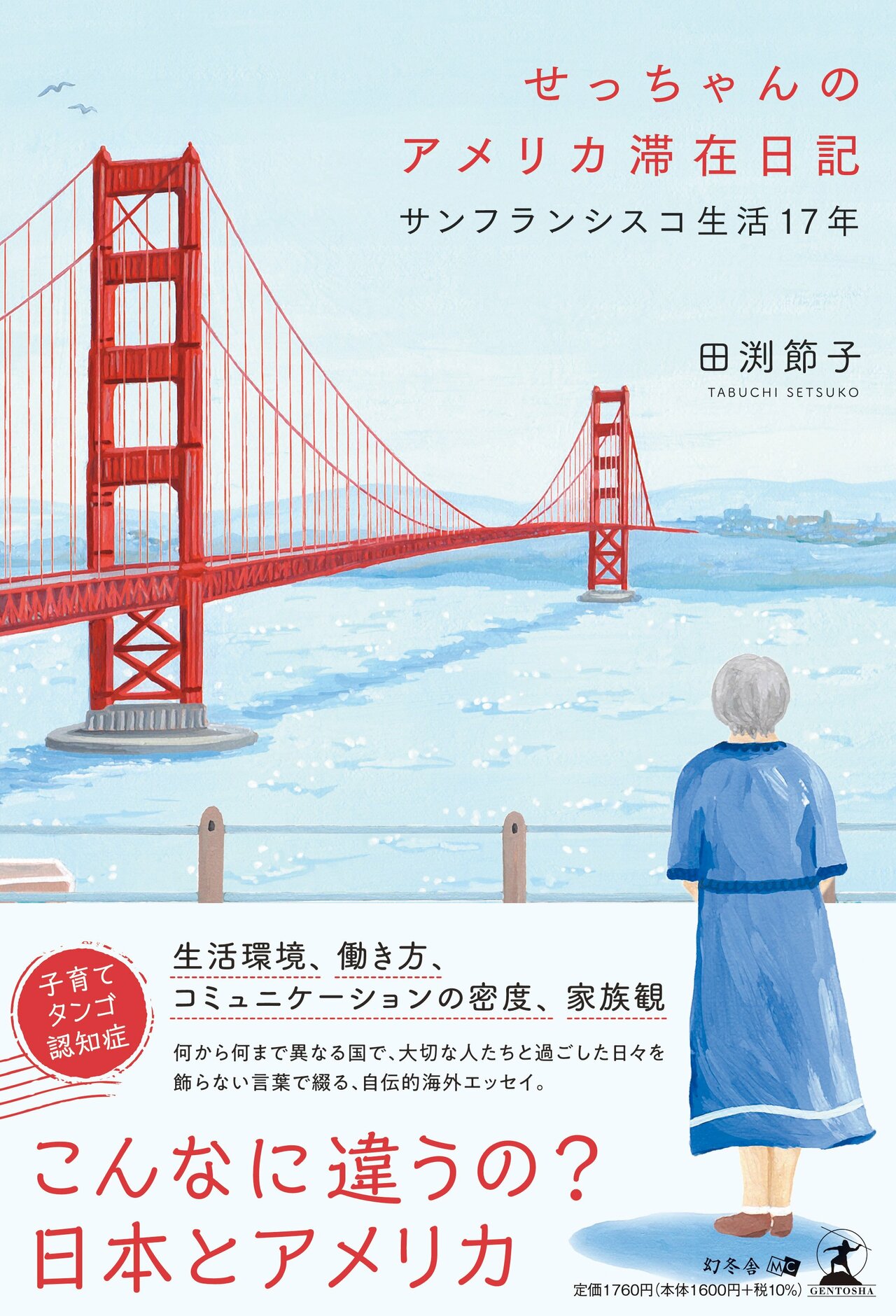長男は積極的に英語の勉強をしていたようです。それだけでは十分でないと、保夫さんの勤めているバンク・オブ・アメリカがベルリッツ(英語学校)から先生を派遣してくれました。
学校の教室の一部を借りて、二人とも別々に毎週1時間ほどレッスンを受けられるようになりました。このように必要に応じて、事情の許す限り温かい協力をしていただきました。
次男は1年生の初めからですし、また、一週間に一度はお手伝いを兼ねて私も教室に顔を出していたので、担任の先生とも連絡が取りやすく、あまり心配しなくてもいいと思っていましたが、私が教室に入るといつもまとわりつき離れようとしません。
普段も落ち着きがなく、うろうろ教室の中を動き回る様子です。英語の個人レッスンでも身が入らず、先生方も困っていたようでした。
そうこうしているうちに学校から連絡があり、学習障害児かどうか日本語のわかるカウンセラーをつけて調べてくれることになりました。入念な調査が全て公費でまかなわれ、カウンセリングが終わると、私達夫婦、担任、カウンセラー、校長先生まで交えて会合を開いてくれました。
調査の結果、問題はなく、異文化に接する時の不適応反応であり、知能は平均以上なので時間をかけて温かい目で見て接していくようにすればいいということになり、皆納得しました。
私達は初めから結果を予測していましたが、一人一人に丁寧に対応してくれるアメリカの教育に目を見張る思いでした。
先生方の大らかで、ゆとりのある態度には感心させられることが度々ありました。校長先生の名前はベン・ショー。日本式に姓名の順にするとショー・べン。
ショーベンじゃないかと息子達は親しみを込めてそう言っていました。そのショーベン校長先生は朝や午後の、父母による子ども達の送迎時間には、必ず校長室から出て廊下に立ち、父母と立ち話をしたり、子ども達に話しかけたりしています。
次男が体の具合が悪い時には校長先生自ら息子を家まで送り届けることを申し出てくれ、日本では考えられないと驚いたこともありました。
また、次男についてはこんなエピソードもあります。
次男は初めて学校に行った時しっかり私の手を握っており、私は教室に残るように約束させられました。担任の先生にその事情を話したら、私に帰るようにいいます。
家も近いですし、彼女に次男を託して帰ることにしました。その日帰宅すると次男が「お腹が痛い時は英語で何というの?」と尋ねてきます。おや?とは思いましたが、簡単に覚えやすく「ストマック・エイク」とだけ言ってごらんと教えたのです。次男にとって初めて必要に迫られ積極的に覚えた英語でした。
【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?