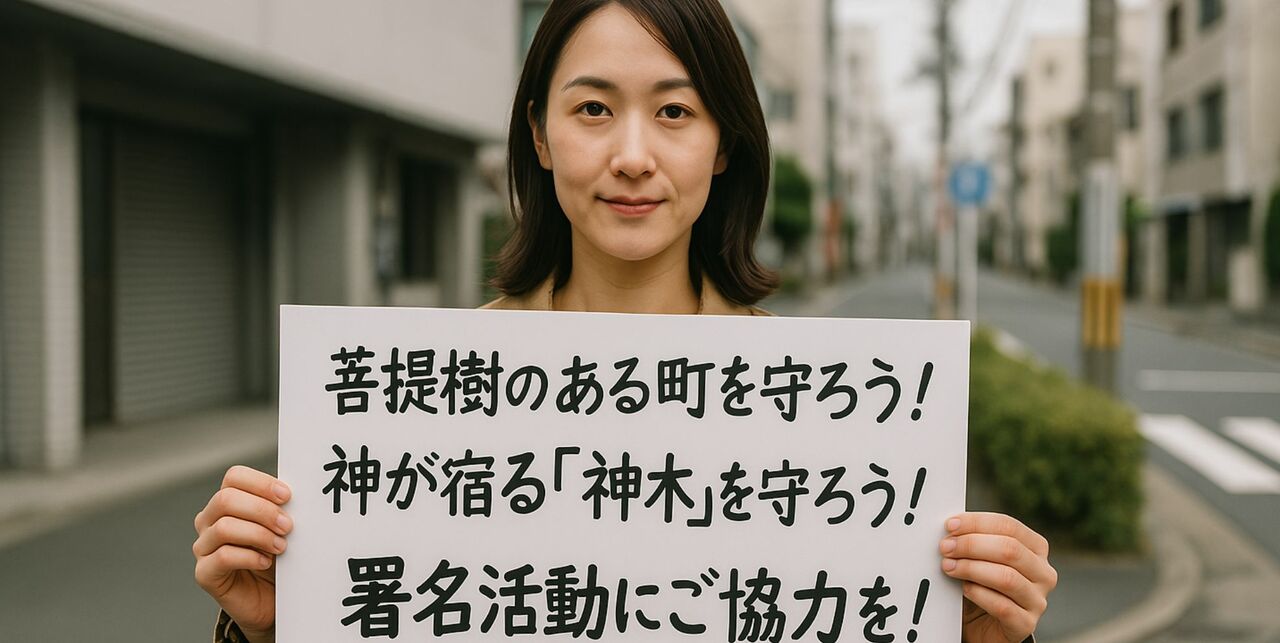【前回の記事を読む】中学二年の夏休みが終わり残暑も遠のいたある日――クラスで「陰の女番長」と呼ばれている女子生徒に神社の境内に連れて行かれ…
神様の樹陰
恩人の樹(き)
深夜、眠れないまま寝返りをうったとき、沙那美は窓の隙間から忍びいった菩提樹の香りをかいだ。
時は秋。菩提樹は落葉の季節を迎えていた。落葉の時期、菩提樹は葉の柄から芳香を発散する。沙那美はその香りに誘われ、寝間着姿のまま菩提樹の下に立った。
見上げると、黄葉(もみじ)の狭間に一本の枝が夜の闇とはまた違う濃さで黒く見え、ぐっと沙那美に迫ってきた。
沙那美はほとんど衝動的に玄関にいつも客用に置いてある丸椅子を持ち出していた。そしてその枝に無意識に寝間着の腰紐をかけ丸椅子を蹴った。
「馬鹿なことするんじゃないわ。生きるんよ」
今までに聞いたことのない未知の声だ。菩提樹の声だったのだろうか?
その瞬間、枝が折れた。沙那美は地面に叩きつけられた。しばらく起き上がれない。
やがて、菩提樹の芳香が気付け薬になったようだ。沙那美はその芳香に心地良く心がほぐされていくのを感じた。命を絶っても父母や祖母を悲しませるだけだ。沙那美は考え直し始めていた。
このままでは未来への展望もない。沙那美は唇を噛む。
雪絵たちにはこれから毅然とした対応をしよう。
まさにこの菩提樹は沙那美にとって忘れられない〝命の恩人〟となった。でも、沙那美はこのことを誰にも話すことができなかった。もし、人に話したなら、この菩提樹と沙那美の間の絆が断ち切られるようにおもえた。
心の奥に深く刻まれたいじめの傷とともに沙那美にとって決して消し去ることのできないできごとだった。だからなおさら、心の裡に秘めておきたかった。沙那美は密かにこの菩提樹のことを一生忘れないと心に誓った。この菩提樹がいつからここで生きていたかは定かではないが、母に聞くと、入居前からこの町のランドマークのようであったという。