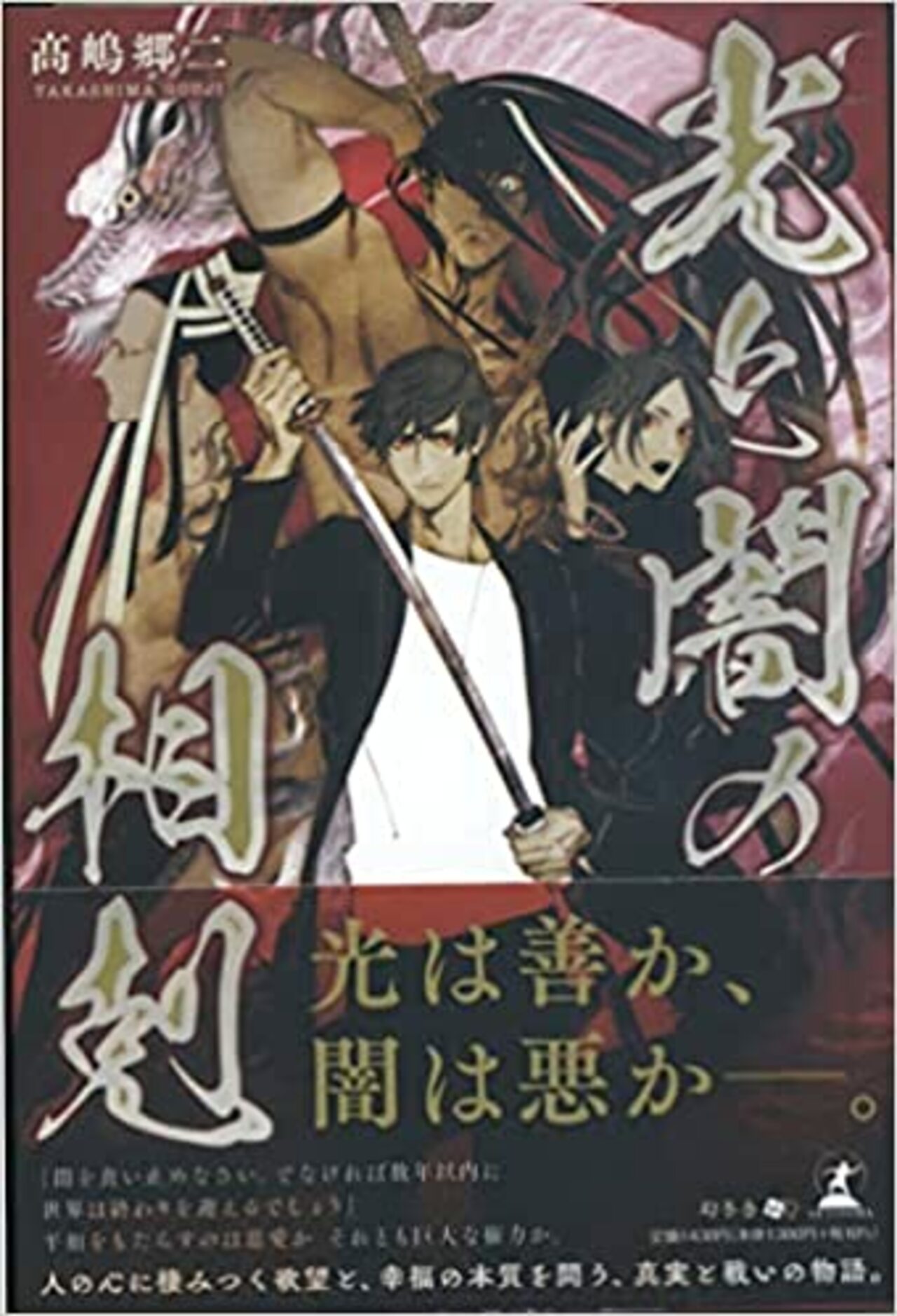【前回記事を読む】気になって見舞いに行くと、「松本さんはお亡くなりになりました」…えっ? 思わず絶句した。かけるは死んだ…。
序章 新たな預言
英良の章(一) 振出し
翌日、英良は非番の日だったので神社へ行った。何かヒントみたいなものを期待して鳥居の前に立っていた。時々、近くを車が通り抜けて行き運転手の視線を感じる。黙って時を過ごすことは苦痛ではないが、人の刺すような視線は苦手だった。
二、三十分経った時、真っ白い一匹の尻尾の長い猫が現れた。その猫は「にゃー」、と鳴いたようだ。鳴き声は聞こえなかったが、英良に口を開けて何か意志を伝えた。英良には付いてこい、と指示を出したように感じたので猫の後を付いて行った。
英良が見慣れた境内までの石畳を歩いて行くと猫は祠(ほこら)の左側に回り込み草藪の中へ入って行った。背の高い虎杖(いたどり)が密生しており、それをかき分けながら歩いて行く。長く白い尻尾が上に伸び、尾先が不規則に上下左右に僅かに揺れている。猫は一定の距離を保ち英良から離れない。時々、立ち止まり距離を詰めているようにも感じた。
周りの空気が違ってきたように感じる。遠くに煙が立ち上っている。松明のように見える。煙は一軒の小屋のようなところから出ていた。周りの景色は現代の風景には見えない。英良の足元にはあの白い猫がいた。「お入りください」と猫が言ったように聞こえた。
戸は古い戸襖のようで英良は左側に開いた。部屋は八畳ほどあった。戸を閉め靴を脱ぎ中へ入ると白い猫は何処にもいなかった。部屋の中央にはストーブが置いてあり煙突が巡らされていた。
お兄ちゃん、とふと誰かが声を掛けた。その声には聞き覚えがあった。かけるだ! 英良は部屋を見渡した。入り口から見ると両側に窓が見え、左側の窓から入って来る光に重なって一人の少年が立っていた。年の頃は八歳くらいでかけると同じくらいだ。
「かける君かい?」英良は聞いた。
「ちょっと違うよ、お兄ちゃん」とその少年が言うと暫く二人とも何も喋らず沈黙が続いた。
「どうしたんだい?」英良は聞いた。
「僕はね、もう死んじゃったの。それでね、何かに姿を変えないとお兄ちゃんとは話ができないの。それでね、猫になってお兄ちゃんをここまで連れて来たの」英良は黙って聞いていた。
「今はちょうど七日目だからまだここに居られるの。それも今日までだね。今日が最後の日だから。それで、何としてもお兄ちゃんに会って、お話ししなければいけないなって思ったの。だけど、もう死んでいるからこれしか方法がなかったの」英良は上手く言葉が出ず大きく咳払いした。