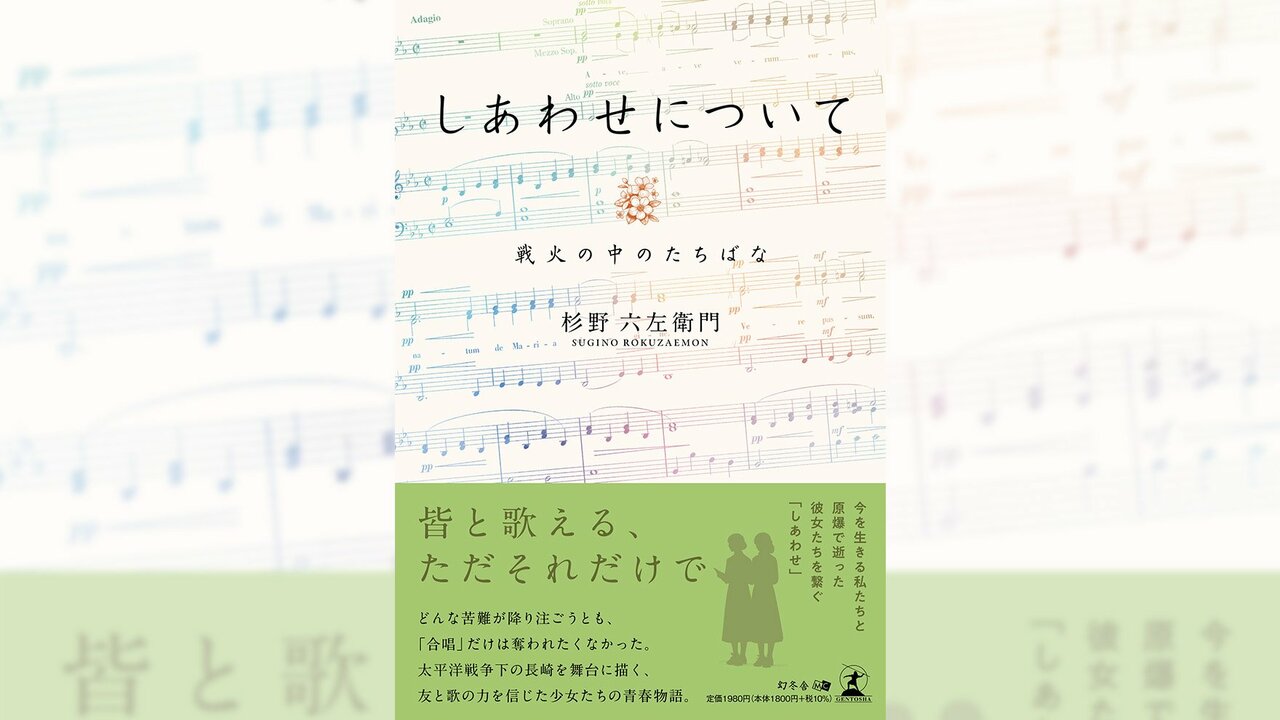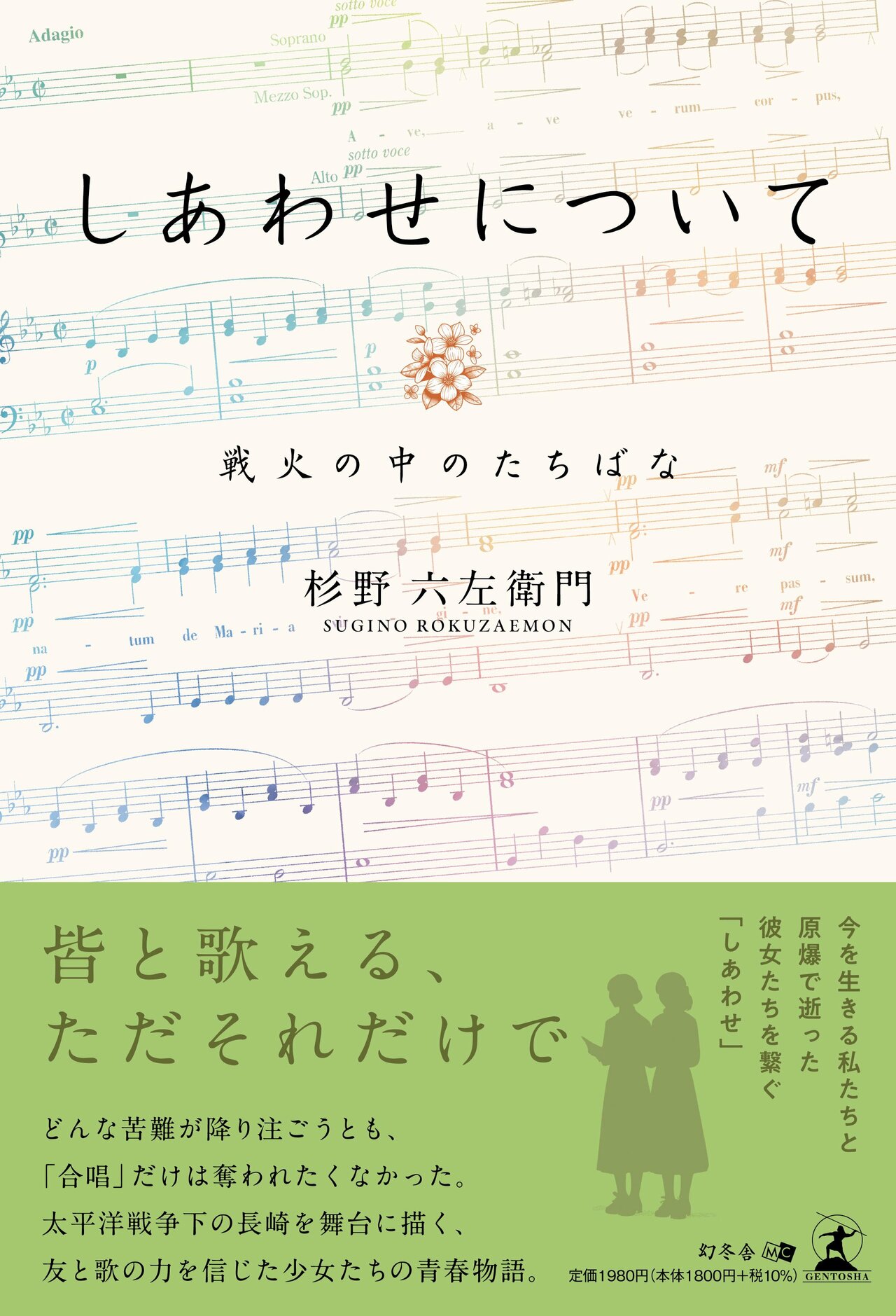【前回の記事を読む】軍需工場へ勤労動員に出ている二年生に代わって、特別に三年生が一年生を指導をするという。
一年生
歌唱の指導は佐々木(ささき)先生が行う。
「十二小節から入ってくるメッゾは、もう少し小さく、レガートで」
と先生が指示した。
「メッゾってなに?」
朋は隣に立っているミサちゃんに聞いてみた。
「メゾ(mezzo)・ソプラノのことよ。イタリア語の正しい発音だとメッゾなんだって先生が言ってた。メッゾなんて言ったって、ほかの人には通じないわよね。だいたい、先生は自分の世界に閉じこもって出てこない人だから。もっともこれは、部長のサエさんの寸評だけど」
佐々木先生の指導は「テヌート(音を保って)」「アニマート(生き生きと)」「レッジェーロ(軽く優美に)」と初めて聞く外国語の連続だった。
このころ街中で外国語を話していると「非国民」と非難されたから、堂々と外国語を使っていて大丈夫なのか心配で、また隣のミサちゃんに聞いてみると、先生が言うには音楽用語のほとんどはイタリア語で、イタリアは日本の同盟国だからその言葉を使うのは問題ない、という話だった。
佐々木先生は四十四、五歳くらいだろうか。ノッポで、気の毒なくらい痩せていて、キリギリスを思わせた。佐々木左馬助(さまのすけ)という強そうな名前とは裏腹に、これでは徴兵検査は丙種(へいしゅ)だったろう。目は柔和だが、自分の意見は変えない頑固そうな力があった。
副顧問の福村昭子(ふくむらあきこ)先生は「昭子先生」と呼ばれていた。県女の専攻科を出て七年目ということだから、二十五歳だろうか。少々背が低いが、美人といってよかった。それも、満開の牡丹が笑みくずれているような、温かみのある美人だった。
昭子先生は歌唱の指導はあまりやらず、もっぱら部の事務的な運営を指導しているらしかった。逆に言えば、佐々木先生は歌唱指導以外はズボラといったところだった。