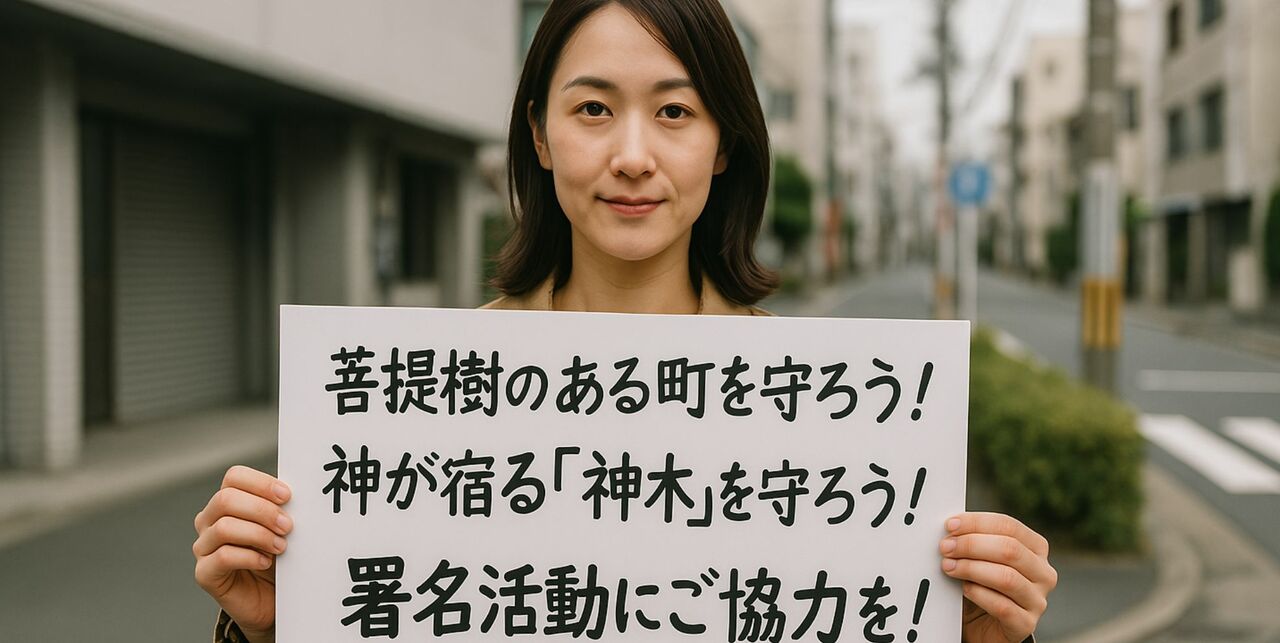「今、桜紅葉が見ごろやさかい我が家の桜の園へ来やしまへんか」と。
やがてふたりは心を通わせ愛し合うようになった。
夕子は今のところ、どこも悪いところはないし、独りでもやっていけるとおもう。しかし、娘の桜子は休日に時どきやってきて、いつもの決まり文句の応酬が始まる。
「ウチに来たらええねん」
「そないな迷惑かけられへんわ。絶対いやや」
でもいつ、健康寿命が尽きて桜子の世話になるかもしれない。現代人は何らかの形で誰かの世話にならなければ死ねない。猫などは死期を悟るといなくなるようだが、人はそうはいかない。夕子は猫の死に憧れていた。
明石海峡に飛び込んだら遺体が決して上がらない場所があるらしい、と誰からだったか忘れたが聞いたことがある。死期を悟ったら、どこだか知らないが、そこへでも行って人知れず消えようか、とおもったりもする。鳥葬風葬ならぬ魚葬というのだろうか。
しかし残された桜子や孫の麻美たちの気持ちを考えると、そうもいかないのかもしれない。家族にとっては行方不明でしかなく、時が過ぎるにつれてあきらめもつくとはおもうが、まだどこかで生きているかもしれないという一縷(いちる)の望みを捨てきれないのではないか。
悠輔の死は突然だったし、無口だったから死後のことはあまり聞いたことはなかった。それでも、おれは桜守やさかい、桜の樹の下に埋葬してほしいねん、とふと漏らしたこともあった。
しかし、墓地でないところに埋葬はできないから、悠輔は桜の園からさほど遠くない丘の上の先祖代々の墓で眠っている。そこから、桜の園の大紅しだれ桜が見える。