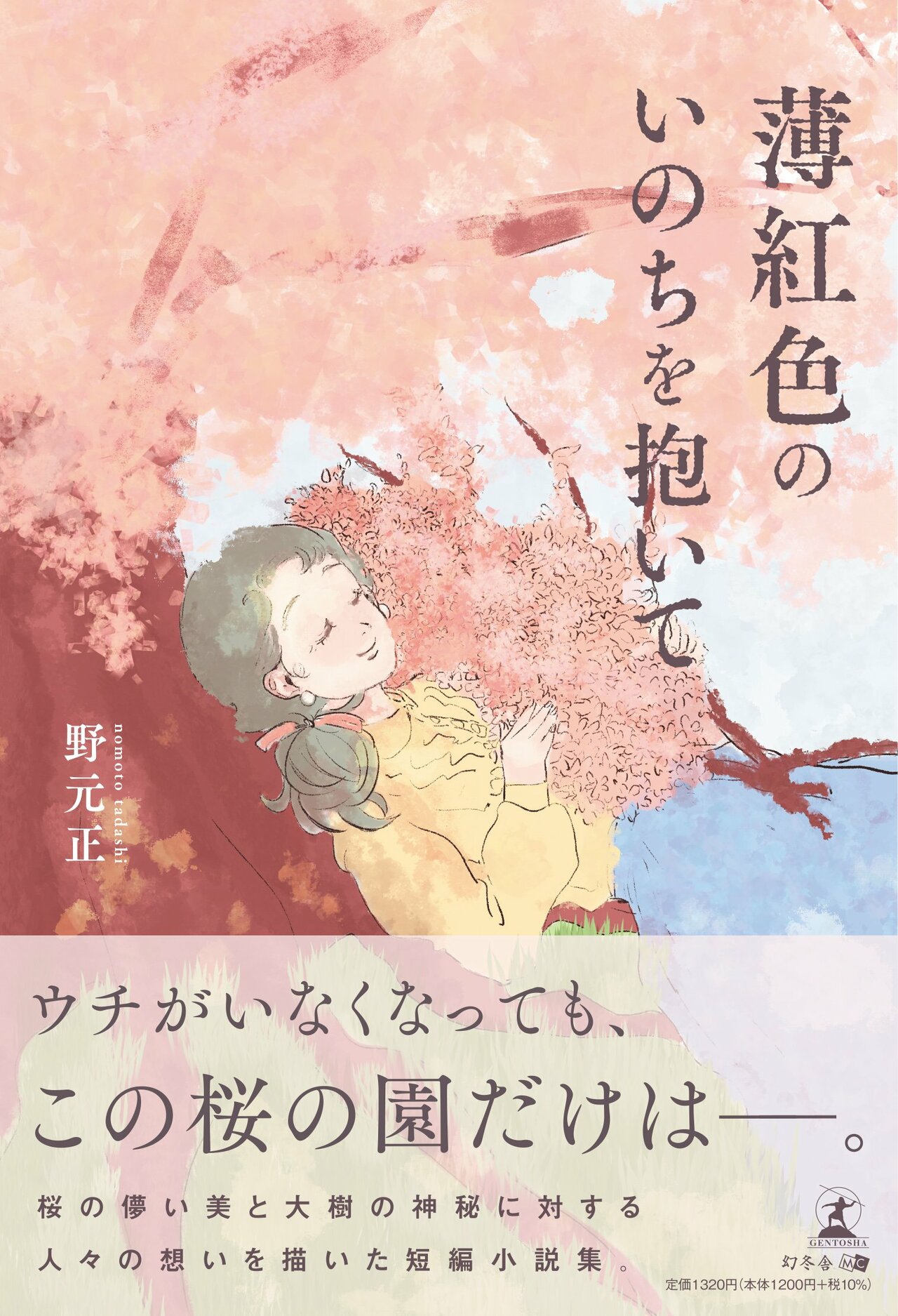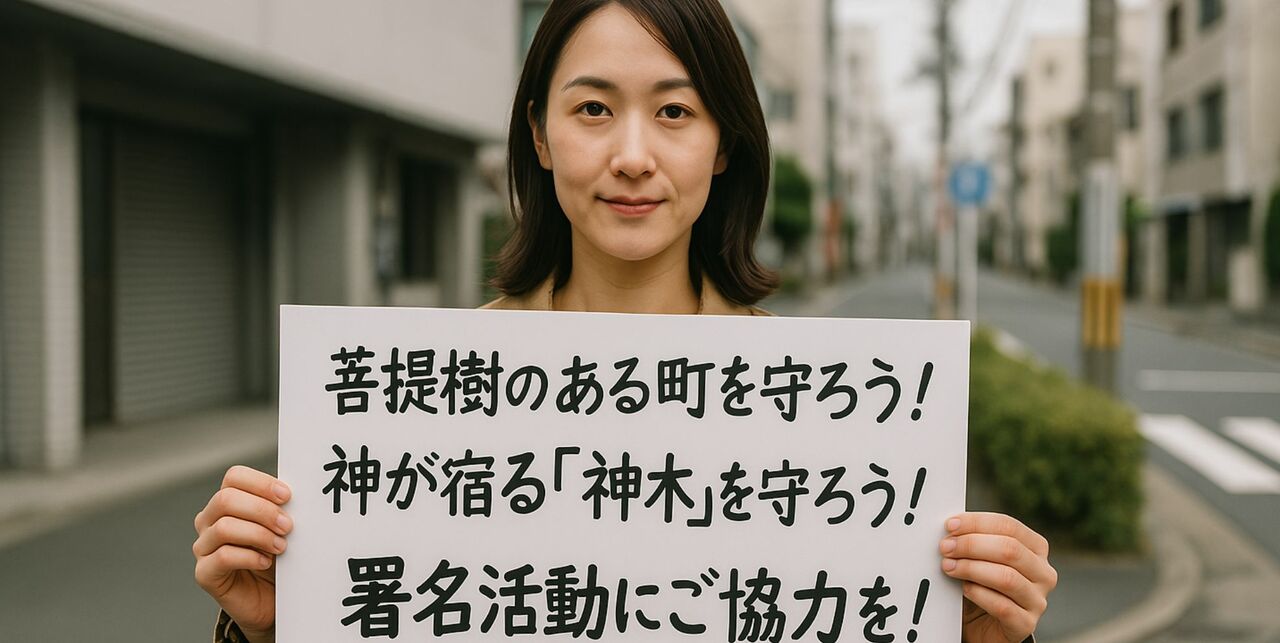夏の暑いときなどは、悠輔や桜子の目を盗んで諸肌を脱ぎ、汗をぬぐうこともあった。今は独り暮らしの気楽さも手伝って、もっとおおっぴらに未だ艶のある肌を露わに井戸水の涼を求める。
井戸へ行く御影石の石畳は幅一メートルくらいある。途中から分かれて野良の地下足袋のまま入れる下(しも)の蔵へ通じている。この蔵には大きな青大将が棲んでいて鼠を捕ってくれるが、夕子は苦手だ。
母屋はほぼ田の字で玄関を入って左手が六畳の客間で、桜材の座テーブルが置かれている。桜の取引の間でもある。悠輔はここの座卓で発送伝票の整理や請求書の作成など夜遅くまで精を出していた。夕子が出した茶も冷えてそのままのこともあった。
奥の年輪模様が浮き出た一枚物の杉戸を開けると、框(かまち)と中柱が桜材の床の間と透かし彫り欄間や、すべてが桜材でできた大きな仏壇がある。それが、それぞれ二間間口で並んでいる。仏壇には悠輔さえ知らない先祖からの位牌が闇の中にくすんで見える。
真新しい悠輔の本位牌だけは、黒地に金文字で旭祥院薫香桜道清浄居士(ぎょくしょういんくんこうおうどうせいじょうこじ)とはっきり読めた。
座敷は南向きだ。床の間の袋戸棚や違棚やほんのりした明かり取りの付書院 (つけしょいん)の花頭窓(かとうまど)など書院造りの意匠が取り入れられている。このしつらえは、江戸時代の農民階級には禁じられていたから明治時代の改装だろう、と悠輔から聞いた。
庇と広縁があるので陽射しは縁先までだ。夏になると、広縁の明障子と、客間と寝間との境の襖を夏用の簾戸(すど)に変えると、風が通って涼しく、クーラーなどいらない。
姑が健在なころは遠慮していたが、悠輔もいない今は、誰はばかることもない。ご先祖様に見られないように仏壇の扉を閉めて時どきここで昼寝をしている。短時間でもぐっすり眠れる静謐 (せいひつ)な空間だった。
注1) 三和土(たたき) 玄関など家の中で床を張らない土間のこと。三和土の由来は赤土に消石灰とにがりを加えて固めたセメントがない時代の土舗装。現在ではタイル舗装や煉瓦舗装やセメント舗装など表面を舗装することが多いが、土間の総称として使われている。
次回更新は3月24日(月)、22時の予定です。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...