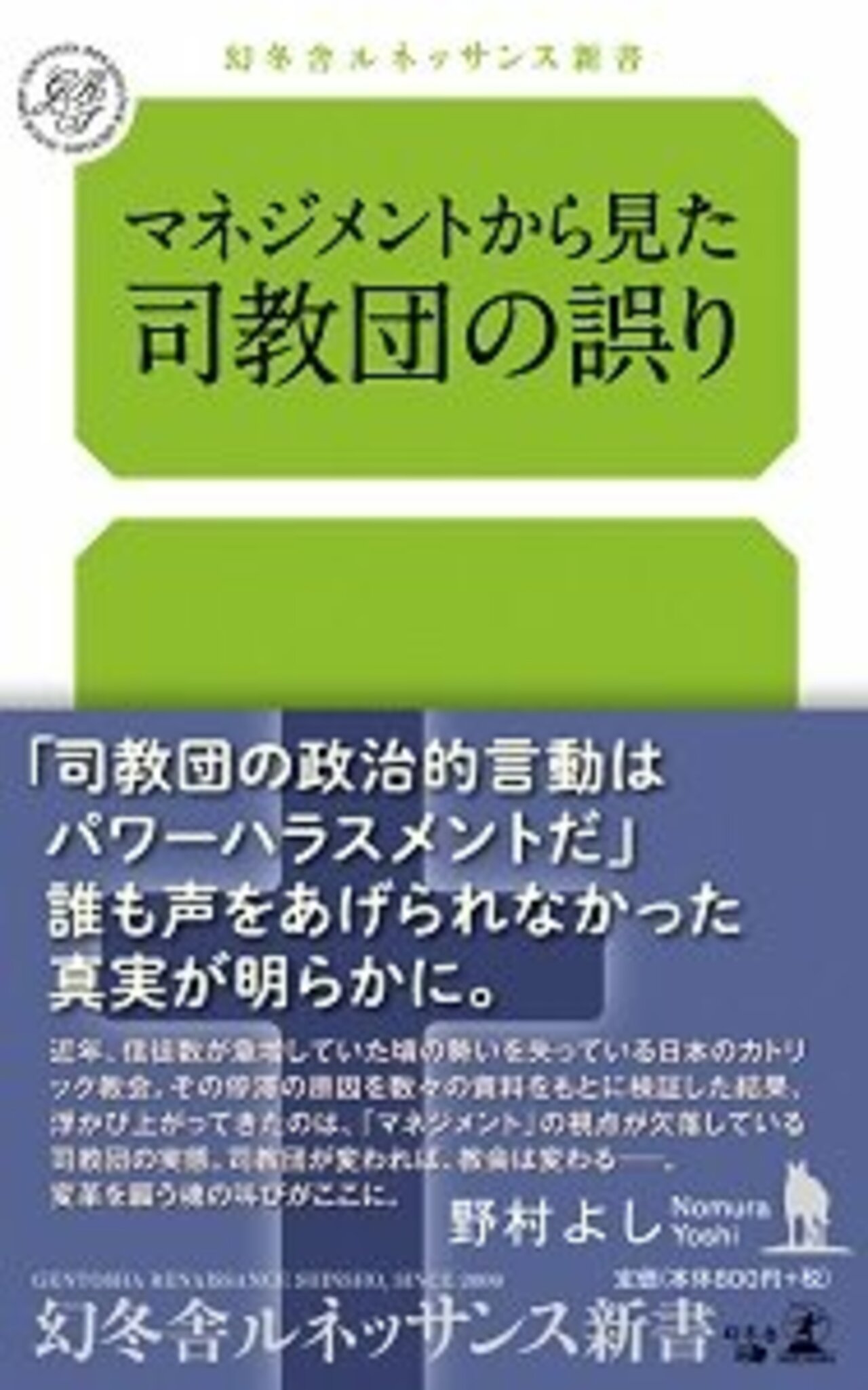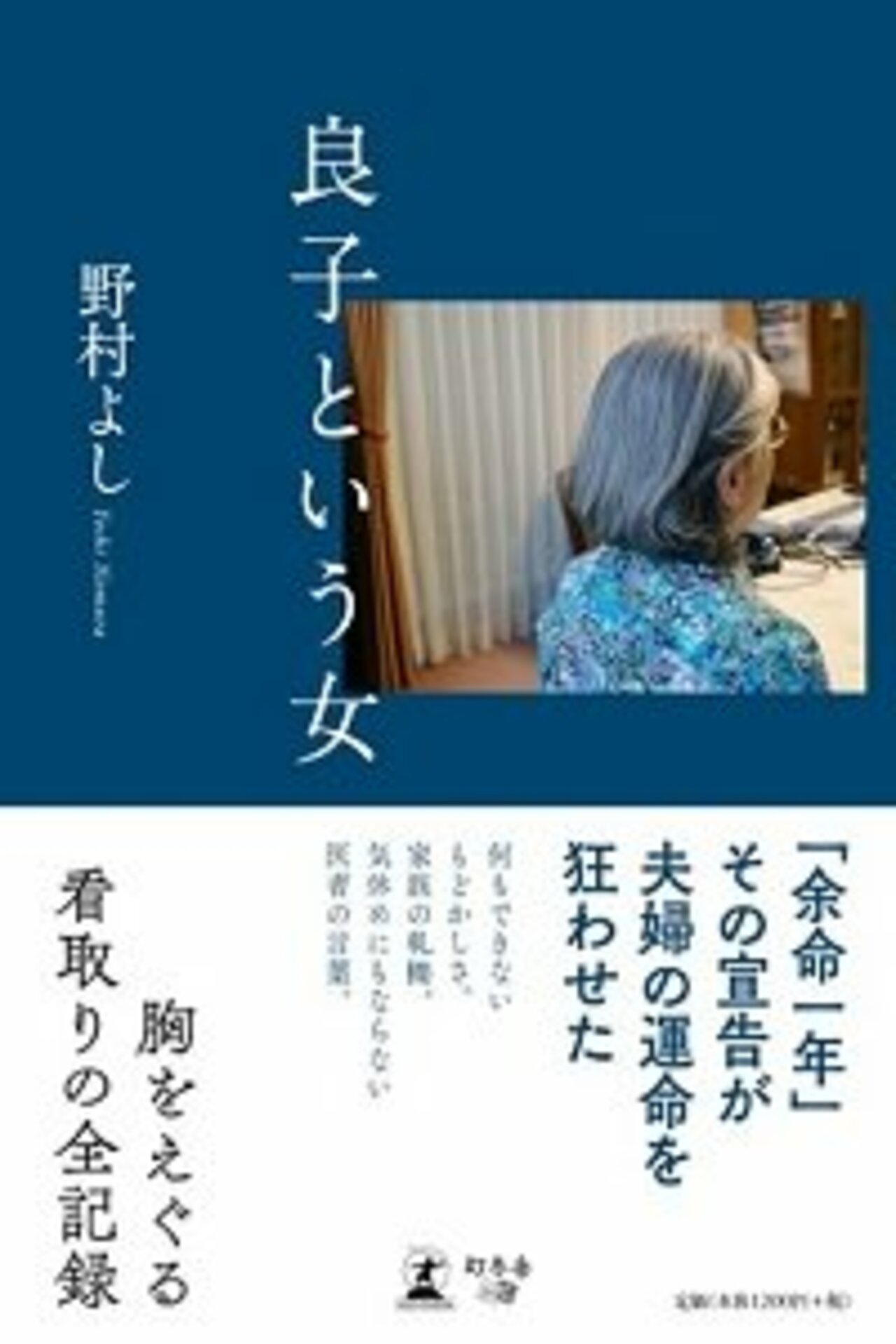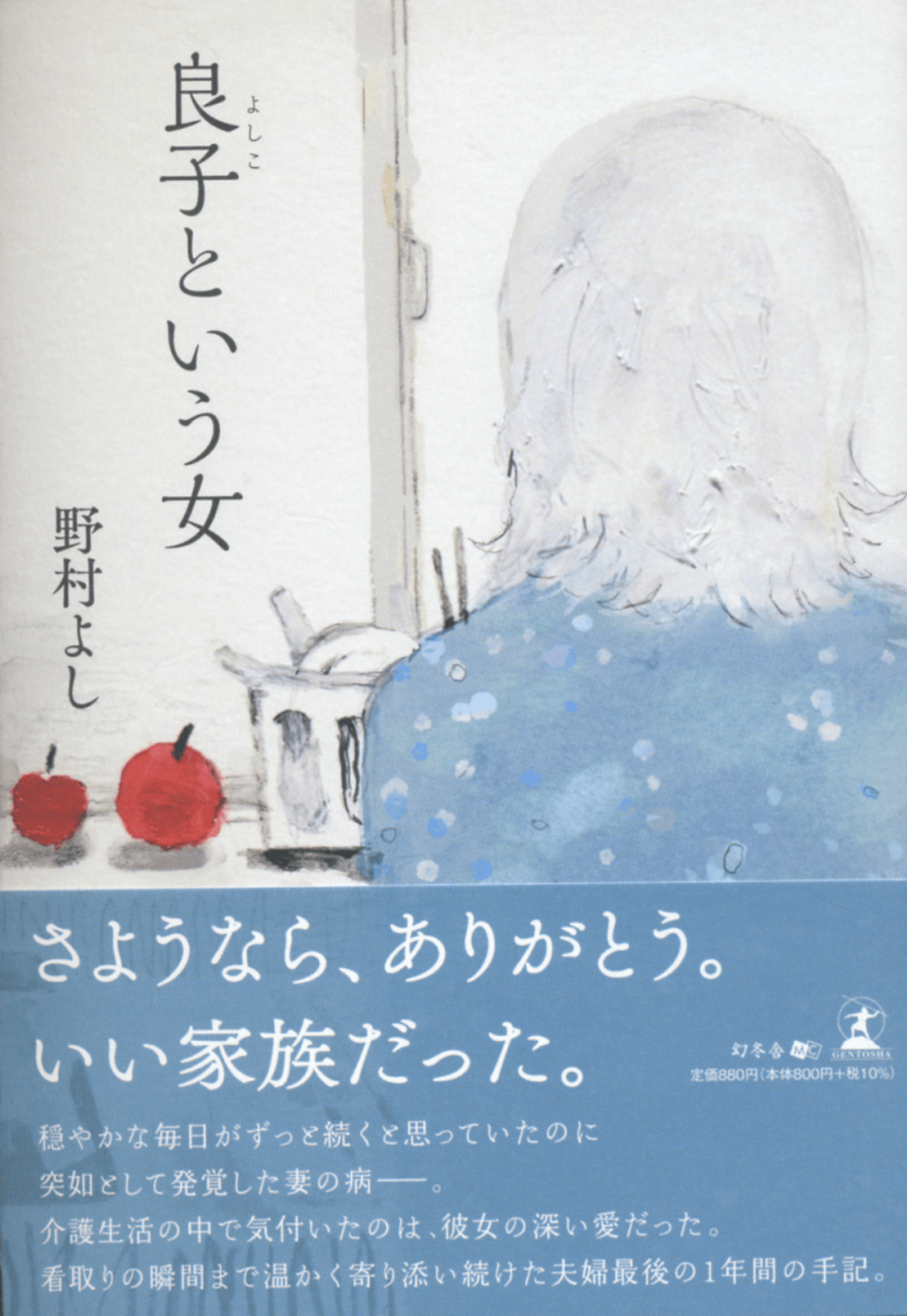11月9日(水)
昭和天皇崩御
私の皇室(天皇並びに天皇制)に関する思いは、ずっと、ほとんど「無関心」と言えた。反皇室であったことは1度もないが、“天皇陛下万歳”だったこともない。父母は愛する長子を南洋で失ったけれど、天皇を相手としてその恨みを語ったことはない。我が家に天皇の画像が飾られたことはない。が、天皇の悪口を聞いたこともない。
皇太子(今上天皇)のご婚約に際しては、美智子さまのお写真を見、世にこのような女性がいるのかと、いわば腰を抜かした。隔絶した気品と美しさだった(そして美智子さまは、その気品と美しさを今に至るまで、ますます高められていると思う。今の世界で最も高貴な女性と思う)。
昭和63年8月15日、日本武道館での全国戦没者追悼式、全国戦没者之霊」と書かれた白木の柱に向かう天皇の足取りが、あまりに遅く、歩くというより立っているのが限度の姿だった。それでも天皇は少しずつ進んだ。それは「行為」というより、肉体を離れた「意志」だった。
自分は戦没者のために祈らなければならない。
「幽鬼」の姿を私は見た。
そのときの昭和天皇ほどに強い祈りの姿を、他に私は見ていない。
私の「皇室」に対する感情は、そのとき、決定的に変わったのである。
昭和天皇は前年、昭和62年9月22日、開腹手術を受けられた。がんだった。
その後、徐々に弱っていかれた。
この63年8月15日「全国戦没者追悼式」のあと、9月19日夜、吐血。
“最後の111日”へ入っていく。
夥しい量の輸血が、当然それだけの下血があって、断行され続けた。
私は傷ましいものと、その報道を聞いていた。日本の医療の偽善と惨酷が、そこには凝縮されていた。
11月19日(土)
八代目 市川團蔵
八代目市川團蔵という人の死が、ただその死によってのみ記憶に残っている。
ウィキペディアによれば、八代目市川團蔵は明治15年(1882年)5月15日に生まれた。
亡くなったのは昭和41年(1966年)6月4日だから、私は24歳である。大阪で機械販売の営業マンだった。歌舞伎は観たこともなかった。市川團蔵の名は、おそらく知らなかったと思う。ただその死が、「市川團蔵」の名を鮮烈に私の心に刻んだ。
市川團蔵の入水自殺を語った作品に、網野菊『一期一会』、戸板康二『団蔵入水』のあることは知っていた。読もう読もうと思いつつ、実に55年が過ぎてしまった。読んだのは今月である。
ここに描かれた團蔵は(作品では団蔵になっているが、本当は團蔵であろう)陰陽を言えば陰の人で、実際、そうであったのかもしれない。そうであったのか、なかったのか、私には知る由もない。そんなことは一緒に暮らしたとしても分からないだろう。私は自身を深い暗さを持った男と思っているが、周辺は、私がいるだけで座が明るくなると言う。
私は芝居をしている訳ではない。芝居するほど思い遣りのある人間ではない。私は私の好きに振る舞っている。それが偽りの私である訳はないのだが、人に見せようのない私も私にあって、(誰もがそうであるように)どこに本当の私があるか、自分にも分からないのである。
いまだに不思議なのは、24歳の私がなぜ、團蔵の入水を深く、心に刻んだか、ということである。
八代目市川團蔵は引退興行を終え、四国八十八カ所の霊場を巡礼し終えた。帰路の途上、84歳を迎えたあと、深夜小豆島沖播磨灘へ身を投じた。
遺体は上がらなかった。
遺体の上がらなかったことが、私の心への刻みには重要であった。
遺体が上がっていたら、八代目市川團蔵の死は多くの出来事の一つとして、私の記憶の底に埋没していたことだろう。
引退興行という仕事の仕上げをし、
四国八十八カ所巡礼を終え、
夜の播磨灘に忽然と消えた、84歳、
24歳の私に、それは強烈なメッセージであった。
12月3日(土)
市川團蔵の死について
網野菊さんの『一期一会』の終わり近くに、團蔵の死についての新聞投書が紹介されている。以下引用する。
“「ただ敬服する団蔵さんの死」といふ題で四十八歳の主婦といふ婦人は「自分なりに精いっぱい生きたといふ自覚をもって、今が人生の最後として最も適したときとみきはめ」て自ら死んだことを八十四歳といふ年齢と思ひ合せて敬服すると書いて居た。それから5日ほどすると同じ新聞に(中略)、四十二歳の主婦といふ婦人の投書が載った。「前者の投書を読むと世の多くの老人たちは自分たちも自殺しなければいけないと考へはせぬか。私にも八十歳を過ぎた、ただ一人の優しい伯母が居る。あの投書を読んで死なれたら困ると心配する。あくまでも人間は天寿を全うすべきだ」”
私がこの文章を誰にも見せないのは、正にこの点にある。私は友人知人に(私自身を含め)「向こうへ行くのを急かす」つもりはない。老父母を、あるいは妻を、介護している仲間がいる。その人たちにとっては気持ちを逆撫でするものだろう。だから誰にも言わない。
妻子には、いずれ正面から告げよう。
ただ妻子は常々私が語っていることなので平然と聞くだろう。
私もまた、当然、「人は天寿を全うすべき」と思っている。
その「天寿」とは何か、ということである。