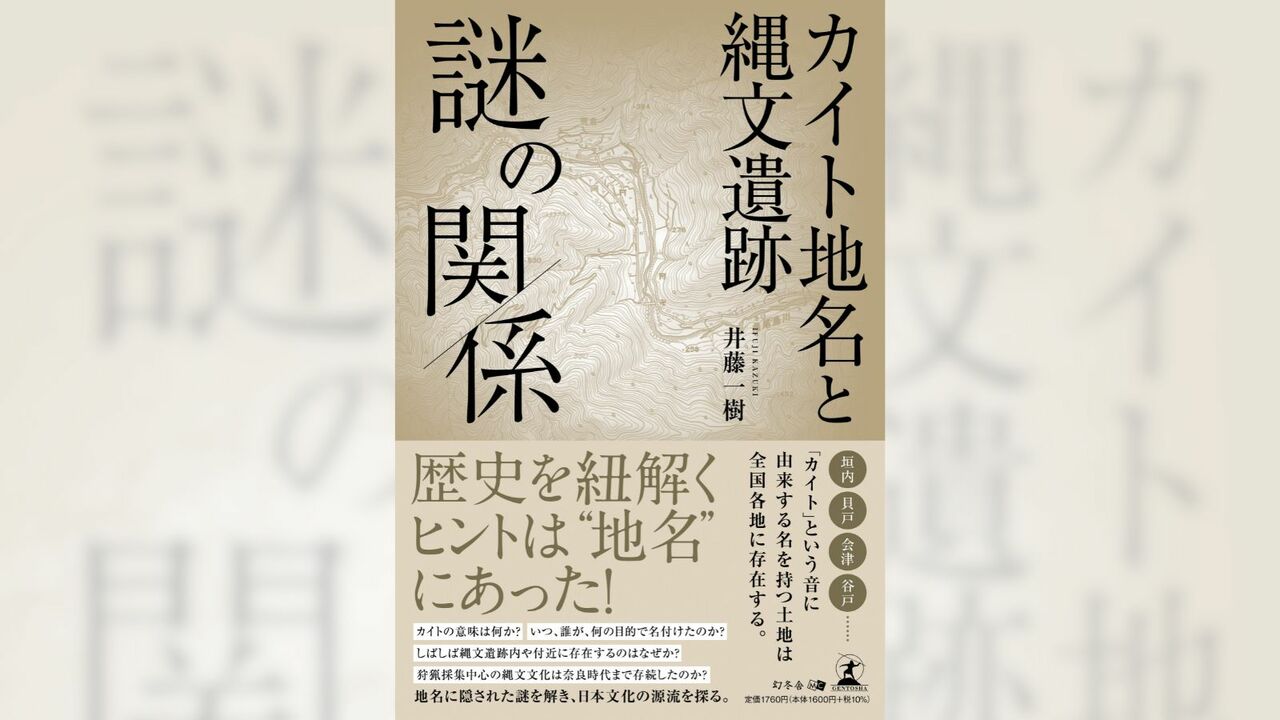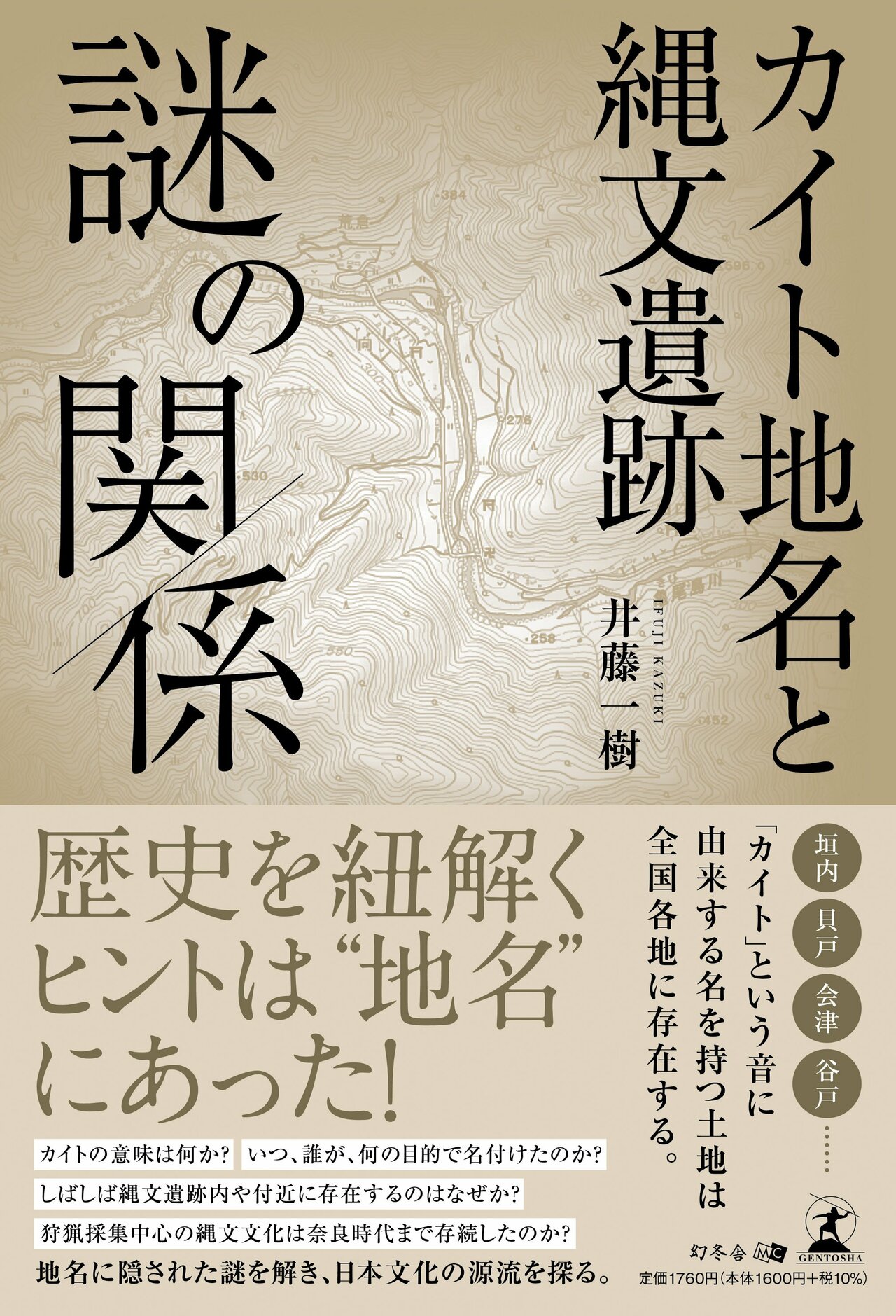【前回記事を読む】【民俗学・カイト地名】垣内、貝戸、会津……漢字は違うが、日本全国に見られる地名。そこにどんな意味があるのか?
はじめに
私とカイト地名の出会い
それが考古学への好奇心を持ったきっかけであり、少しの間夢中でそこらあたりを探して、遺跡の範囲をだいたいつかめたものです。
そうこうしている間に高校進学、就職と忙しくなり忘れていましたが、仕事で岐阜市へ転勤となり、一〇年余りアパートから通勤しました。
そんなある年に久々に帰郷して本当に驚いてしまいました。遺跡のある田畑がブルドーザーによりすっかり削り取られ、もとの様子がわからないほど変わり果てていたのです。耕地整理であり、農家のことを考えれば仕方が無いことですが、少しの間声も出ませんでした。
数年後、郷里に新築した自宅から通勤できる職場に転勤になりました。子供も大きくなり、家の一帯が縄文遺跡であることを話しました。
期待は持てなかったのですが、晩秋の取り入れが終わった田んぼの中を一緒に探して歩くと、以前ほどではないが数点の石器が見つかりました。おそらく表土を再利用したためある程度は残存しているようでした。子供たち二人も夢中になり、夏休みの研究等でも私がびっくりするほどの成果を上げていました。
六〇歳を過ぎた頃、「郡上・地名を考える会」で会員それぞれの居住する地域の小字を調べることになりました。
まず小手調べに私の居住する郡上市八幡町大字那比の小字一五二ヶ所を表計算ソフトに投入して名寄せを実行してみました。結果は○○洞が二三ヶ所、○○平(ひら)と○○谷がそれぞれ一一ヶ所、○○会津・開津(かいつ)が七ヶ所で上位四位の順番でした。
洞・平・谷は山の中の村ですから多いのは妥当でしょう。しかし、会津・開津については全く見当がつきませんでした。