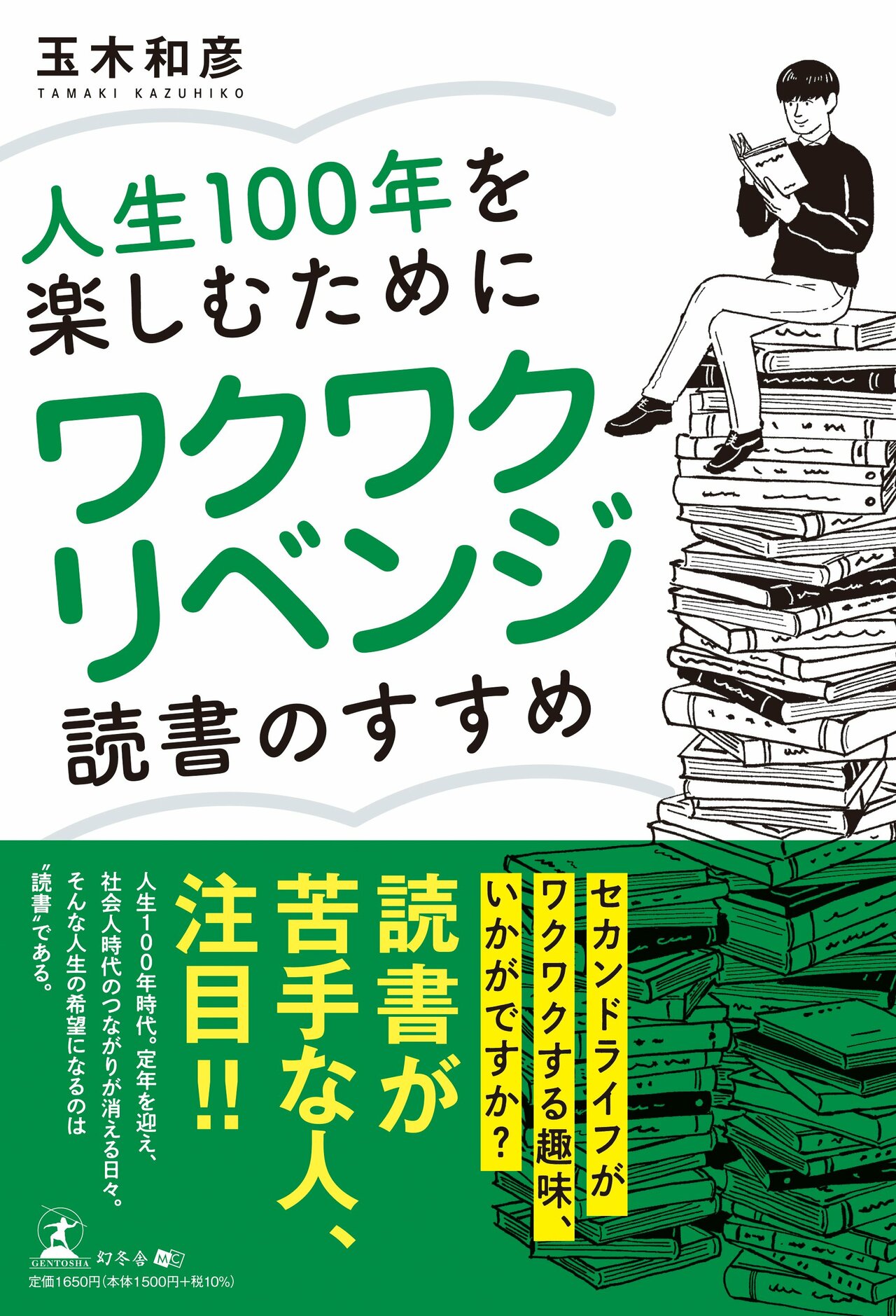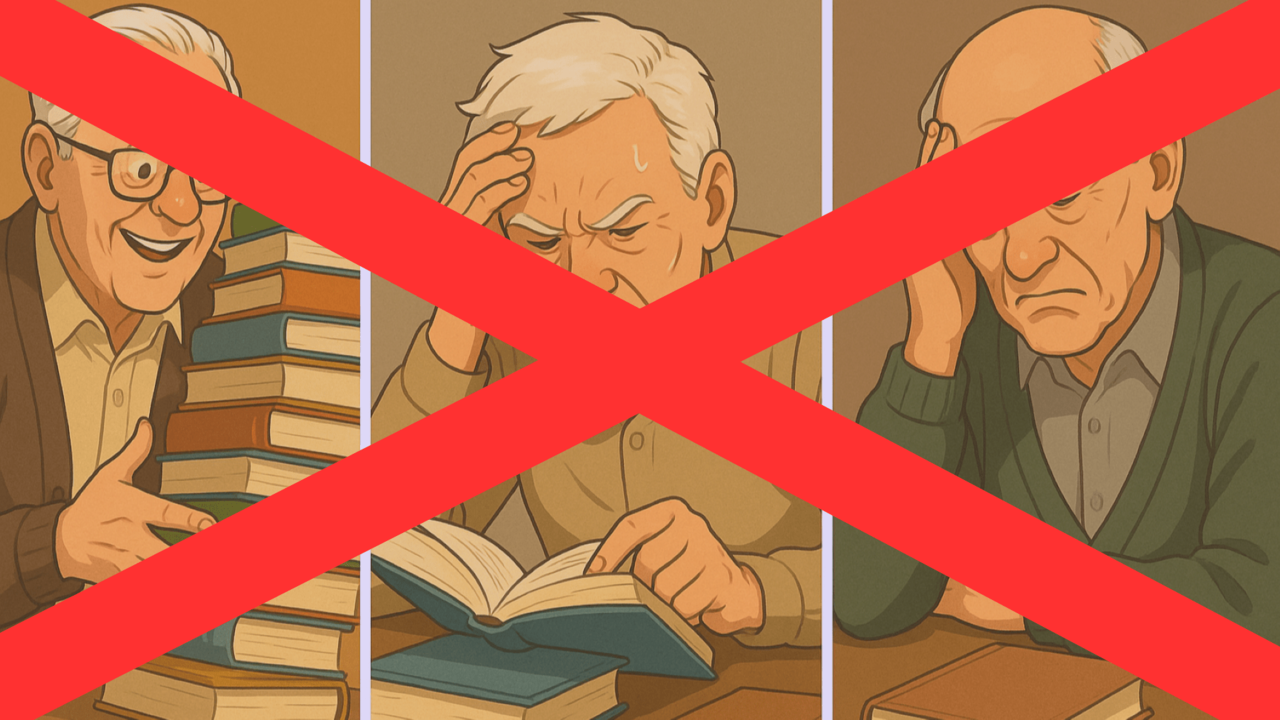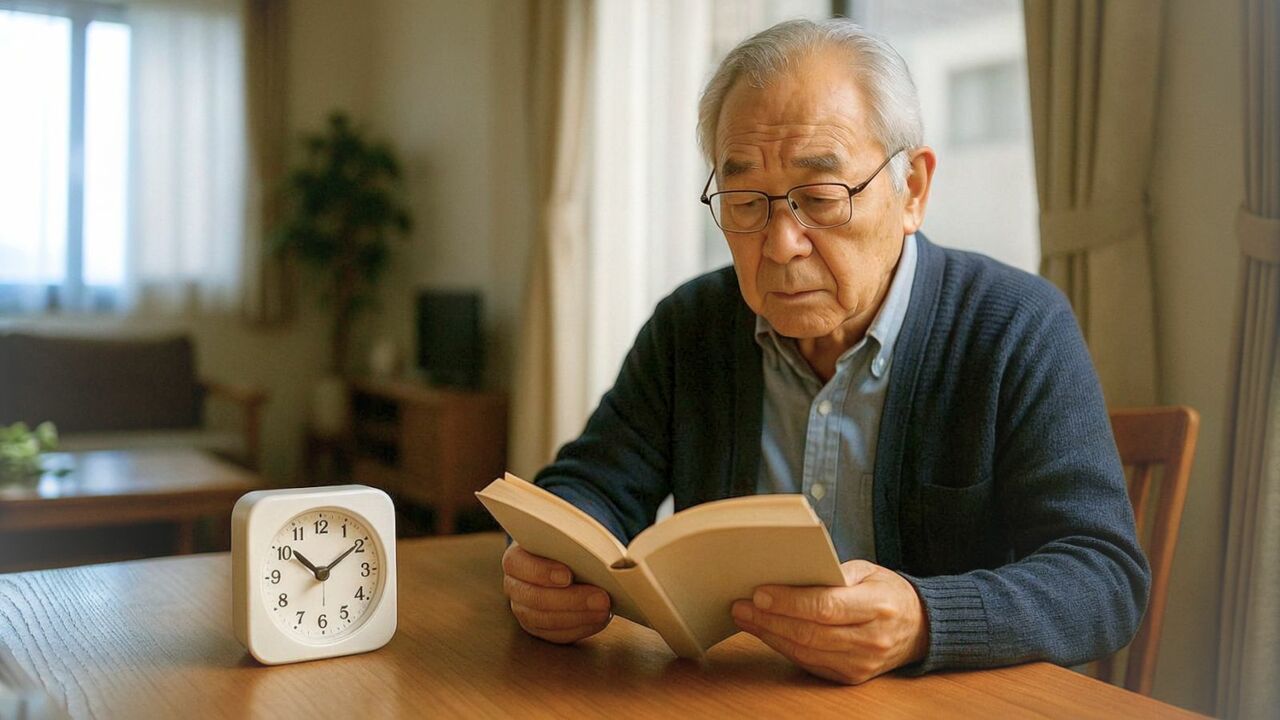私も「フランス革命」についての精読コンテンツを購入した。桑原武夫責任編集『世界の歴史〈10〉フランス革命とナポレオン』(中央公論新社1975年)と安達正勝『物語フランス革命』(中央公論新社2008年)をもとに、1回40分くらいのものを100回以上にわたって解説している。
主宰者は「フランス革命がわかれば西洋文学がわかる」「フランス革命がわかれば政治の仕組みがわかる」と述べていたが、まさにその通りであると思う。このコンテンツは、いわゆる歴史の授業ではない。フランス革命を通じての文学的な情報も案内してくれる。
ディケンズ『二都物語』(新潮社2014年)、アナトール・フランス『神々は渇く』(岩波書店1977年)、モーパッサン『脂肪のかたまり』(岩波書店2004年)、オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』(岩波書店2020年)……。
どんどん私の知的好奇心を刺激してくれた。それと同時に「フランス革命」を教科書とは異なる視点から深く考えることができたのも大きな財産である。まさに信州読書会が、私の名作との出会いを促してくれた。この出会いがなければ、特に西洋文学の名作とはいまだに疎遠なままだと思う。
とは言っても、「名作」の定義は難しい。個人の考え方もある。当然、意見の割れるところである。ただ、「ワクワクリベンジ読書」を進めるにあたっては、「古典(国内外を問わず、古くから今日に至るまでのベストセラー)」や「歴史・文化」を切り口とした書籍を特におすすめしたい。想像力を掻き立て、知識の蓄積につながるものから始められた方が、読書を身近に感じることができると思う。
仕事の関係で経済・経営関係の著書を読まれる方も多いと思うが、あくまで「日々の暮らしに潤い」を与えるものとして、まずは「古典」「歴史・文化」をテーマとしたものをお読みいただけたらと考える。
また、より手軽に読むためにも、単行本ではなく文庫本、大きくても新書がよい。Gパンの後ろポケットに文庫本があるというのも、スタイリッシュである。あるいはジャケットの内ポケットに文庫本や新書を忍ばせておくのも、いつでも・どこでも・好きな時に読書ができる体制作りにもなるだろう。ちょっとした「シニアの身だしなみ」と言ったら大袈裟だろうか。こうしたところにも知的で素敵なシニアライフの一端を垣間見ることができるように思う。
まずは生活の中に読書を取り入れて知識を取得し、知識を日常生活の智慧として生かしていくことが重要である。そうした一連の活動こそが「ワクワクリベンジ読書」であると考えている。一人でも多くの方とこの思いを共有できたら幸いである。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...