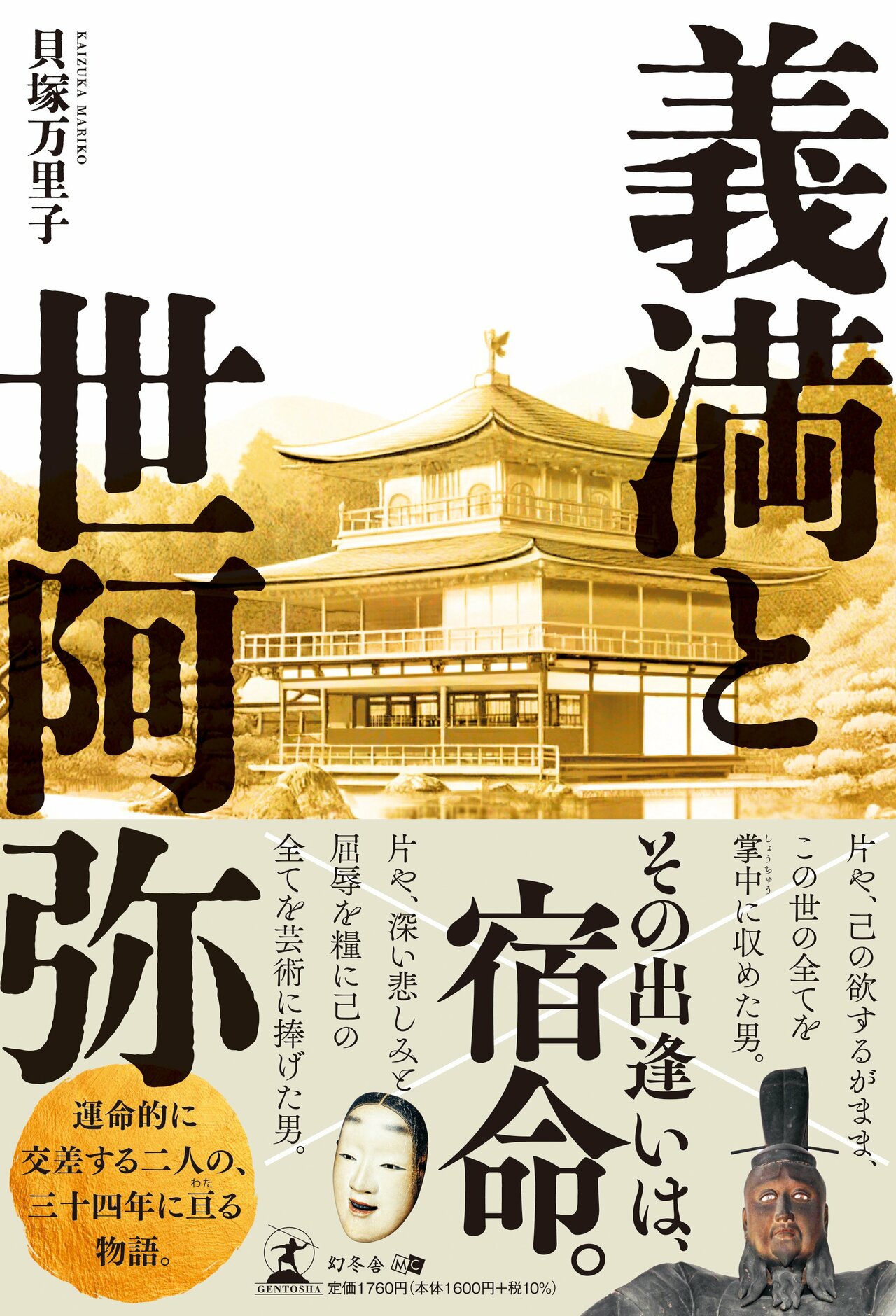――二月の柳の風よりも嫋(たお)やかで、秋の七草の花が夕露に萎れる様より麗しい。
楊貴妃の舞を見ているのではあるまいか。将軍様が賞玩されるのも無理は無い――
舞が終わると、栂尾産の最高級の茶に、経弁手土産の奈良名物、「林浄因の饅頭」が供された。饅頭は当時としては新しい、中国風の菓子。二条良基の好物の一つであった。茶を飲み終えると、経弁はそろそろ帰らねばと腰を浮かせた。
「もうお帰りか、お名残惜しい事。和歌に歌に舞に、この老人はすっかり堪能致しました。お礼に名前を差し上げましょう。この扇子に書かれた様に、『藤若』。如何かな」
扇子には如何にも貴族らしい、流れる様な達筆で藤若の二字と和歌が書かれていた。
『松が枝の 藤の若葉に 千歳までかかれとてこそ 名づけそめしか』
二人が帰ると、興奮醒めやらぬ二条良基は早速経弁宛てに手紙を認めた。
『藤若(世阿弥)に暇があれば是非又一緒にいらして下さい。今日は一日とても楽しく、心がぼーっとしてしまいました。能は勿論の事蹴鞠や連歌にも堪能とは、只者ではありません。何より顔立ち、雰囲気はふんわりしているのに中身はしっかりしており、これだけの名童は滅多にいないでしょう』
以下、春の曙の霞の中の梨か桜の花だの、柳の木だの、秋の七草だの、楊貴妃だの、源氏の花の宴だの、有りと凡ゆる文学的修辞を連ねて絶賛した挙句、こう締め括った。
『私は自分を埋もれ木に成り果てた身だと思っておりましたが、まだ煌めく心を持っていたのだと分かりました。この手紙は読んだらすぐ、火中に入れて下さい』
【前回の記事を読む】生まれた時から将軍と成る事が決まっていた足利義満。義満に気を遣い、誰も対等と話そうとする人はいなかったが、世阿弥だけは…
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。