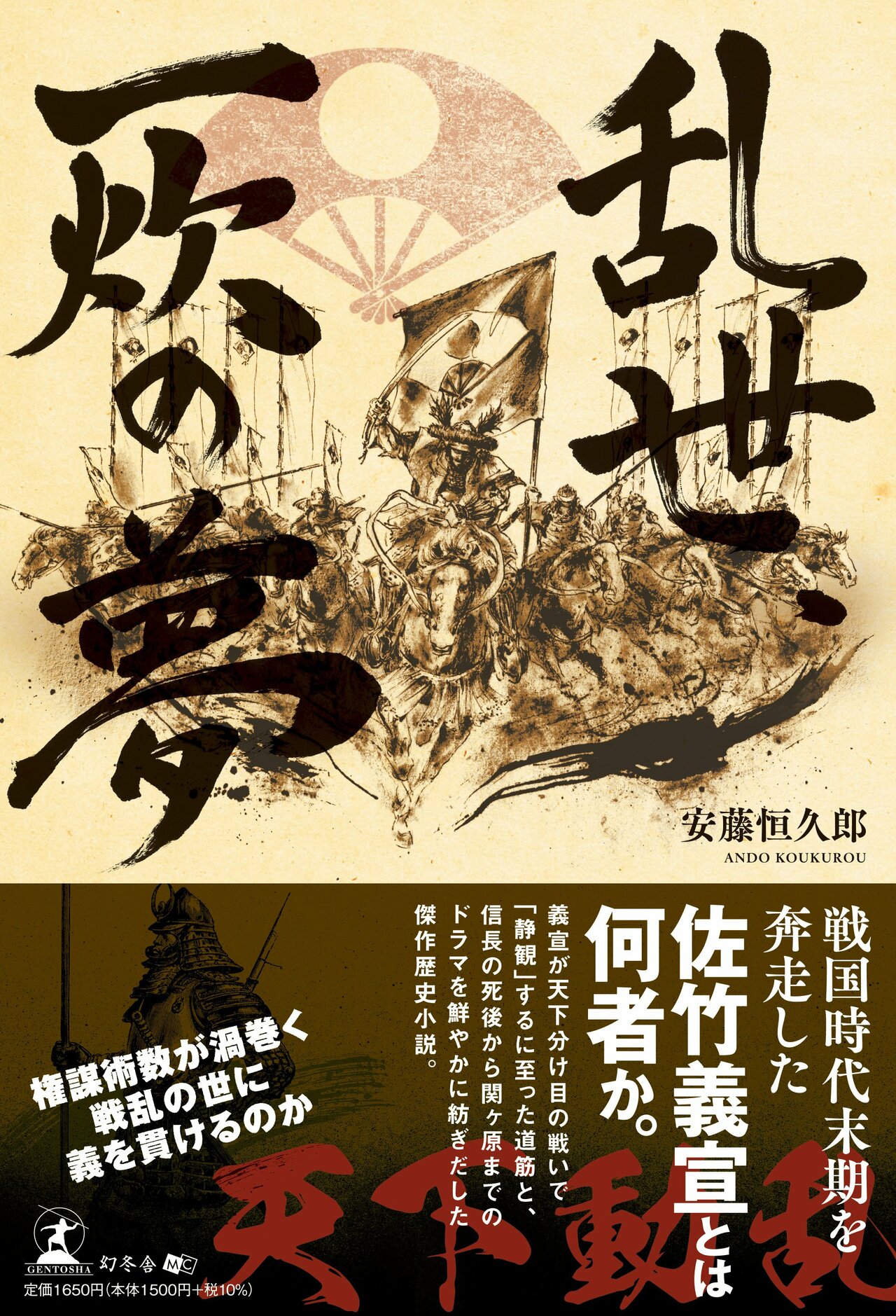「水戸城制圧後は支城の残党狩りを行い、引き続きその勢いのまま府中の大掾清幹を攻撃する。細かな軍割と手順については父上の下知に従うということでよろしいか?」義宣は続けた。
「さらにもう一つ、頼みがある。上洛時のかかりについてだが三百もの兵を三月(みつき)もの間、連れ回すのじゃ。莫大な費用になるであろう。この算用については儂の近習、荒川弥五郎[この時まだ十七歳、のちの渋江内膳政光]に任せるが皆の協力も必要となろう。近いうちに触れを出すことになる。以上が儂の腹案の全てである」
義宣は五人の顔をぐるりと見回した。
佐渡がその後を引き取った。
「何かございませんか? 忌憚のないご意見を承りたい」
すると真崎兵庫が質した。
「同じ大掾一族の鹿島、行方の面々及び額田久兵衛の成敗は如何するおつもりかお伺いしたい」「そは、儂が帰国してから来春頃となろう」これで散会となった。
荒川弥五郎による算用の結果、翌十一月二日に家臣に対して禄高の十分の一を金子にて用意するよう触れが出た。
荒川弥五郎は下野国の小山秀綱の家臣、荒川秀景の子であったが小山氏は小田原征伐時に北条氏の麾下(きか)であったため秀吉の奥州仕置きで改易され荒川氏も浪人となった。
弥五郎の算用の才能を惜しんだ佐竹家家老の人見藤道が義宣に推挙し弥五郎、十七歳の時に佐竹家に仕官した。その後、同じ小山氏の家臣であったが佐竹氏を頼った渋江兵部氏光の養子となり渋江内膳政光を名乗った。これは、のちの弥五郎二十歳の時である。義宣より四歳年下である。
懸案の軍議が終わると義宣は上洛するに当たって秀吉やその重臣たちへの土産物の準備に追われた。