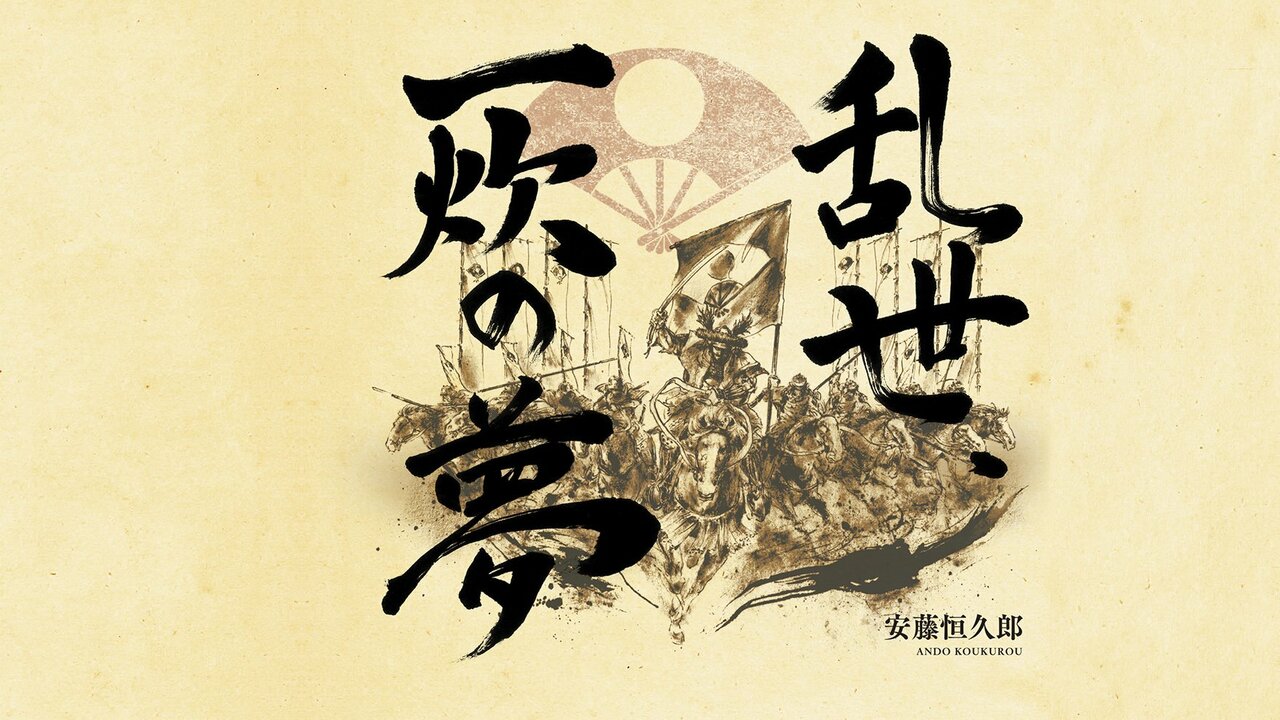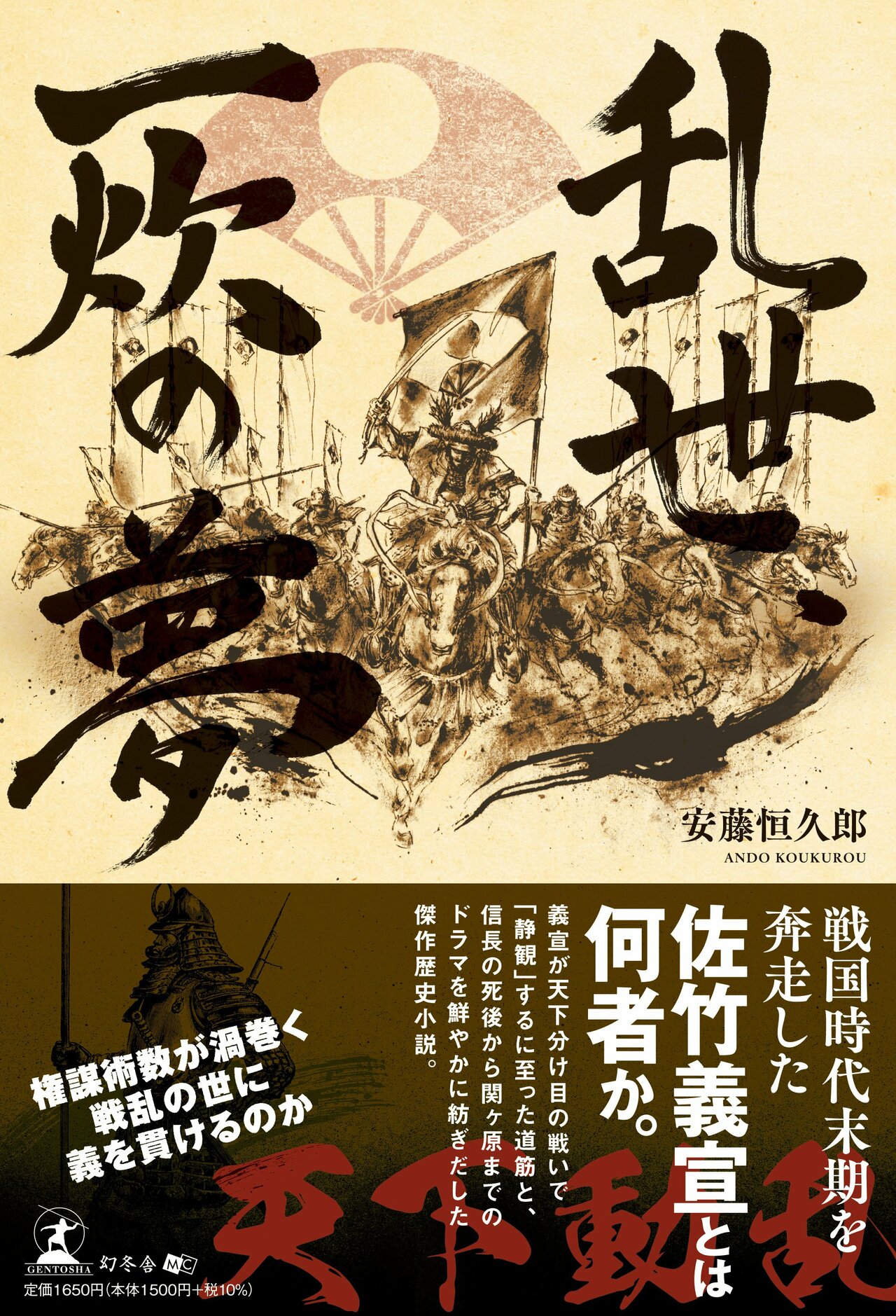【前回の記事を読む】「あの関白秀吉という小男、なかなかやるな。…よほど、帝と、いや朝廷と持ちつ持たれつなのか、さもなくば弱みを握っておるのか」
壱の章 臣従
水戸城攻撃
義宣は進物品の準備の合間にも茶の湯の稽古に余念がなかった。京に上れば茶会に招待されるかもしれない。その時に『恥をかきたくない』の一心である。
小田原の陣では多くの武将たちが眼の色を変えて熱中していたのが茶の湯であった。義宣は茶の湯が武将間の重要な交流の手段であり情報の交換の場であることは知っていたが、それが茶室という槍や刀のない戦場でもあることを知ったのだった。密談には、またとない格好の場所だったのだ。
世は権謀術数の戦国である。
だが残念なことに常陸にはまだ「侘び茶」なるものは広まっておらず豪華な茶道具を使い書院の間で点てる「書院の茶」であった。師匠となったのは在京中に一度だけ千利休の茶会に招待された父であった。茶会のあとで義重は利休作の茶杓"をりため"を拝領した。
こうして義宣はじめとする一門郎党の三百余は天正十八年の十一月二十日、太田舞鶴城をあとにした。水戸城下と府中城下では「五本骨披扇に月」の家紋を染め抜いた旗指物を掲げ馬に跨った義宣らの騎馬はわざとゆっくりと進み上洛を誇示した。三百余の兵と夥しい小荷駄の列は約一ヵ月後の十二月十七日に京都二条の私邸に入った。
常陸ではその二日後、予定通り太田舞鶴城大手門の出陣式で気勢を上げた。
義重は久々の緋縅しの鎧に前立は毛虫の兜を身に纏うと武者震いをした。
「敵は水戸城の江戸但馬なり! いざ、出陣!!」
「えいえいおう! えいえいおう!」
鬨(とき)の声と共に馬上の義重は采配を大きく前に振り大手門を潜(くぐ)った。
和田安房、真崎兵庫の本隊は義重、小貫佐渡の別働隊と城下の外れで二手に別れ本隊は河合方面に進み、別働隊は左に折れて茂宮方面へと向かった。