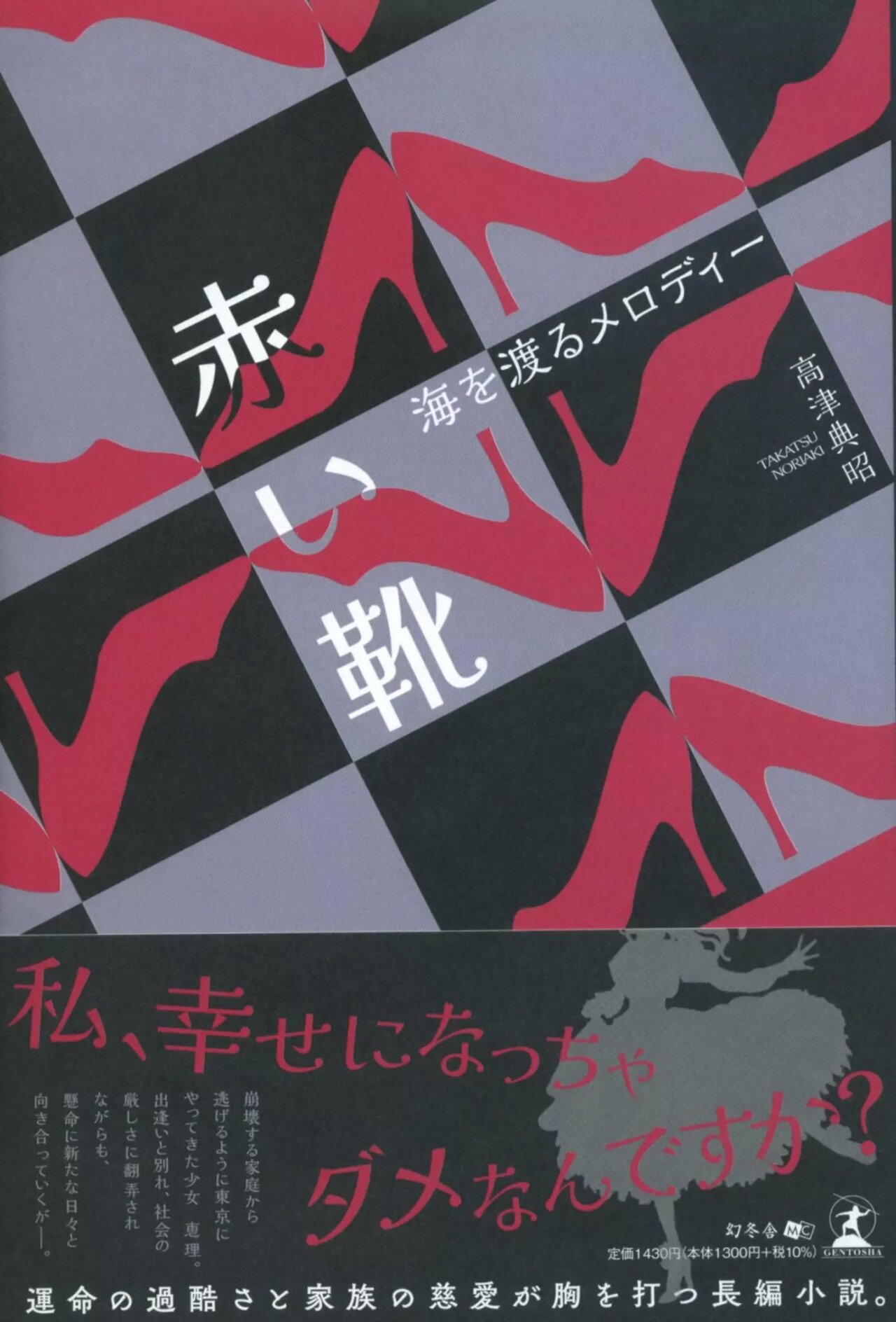恵理はこんな父親でも見捨てない。ところが、祐一はもう既に娘への愛情などなくなってしまっていた。我が身の辛さを誰にもわかってもらえないことを呪った。たとえ妻子でさえ、その地の底から吹き上がるような不幸への恨み節の矛先を向けていたからだ。もはや昔の仲の良かった家族の痕跡もない。
「そうか」
娘とはあまり話をしたくないので何の感想も言わなかったが、実は内心非常に喜んでいた。
もう貯金も底を突いていた。島外へ恵理が進学したら仕送りなどで金がかかる。金はどうするんだと思っていたところに突然の吉報だ。一家に稼ぎ手が現れたのだ。嫌であるはずがない。しかし、ここ何年もまともな会話なんてしていない。だから照れくさくておめでとうも、良かったねも何も言わなかった。
祝福もしてくれない父だが恵理は恵理なりにわかっていた。父の口元が緩んだからだ。
そこがこの家族の素直過ぎる特徴だ。
「そうか、春になったらお前も家に生活費を入れてくれるんだな」
自分の心の内をそのまま素直に口にした。
「お父さん、これからは私も働きます。稼ぎます」
一緒に帰っていた智子が気遣って言った。
「お父さん、褒めてあげてよ。役場なんだから」
「おめでとう」
祐一はポツリと無表情で社交辞令のように言ったが、言い方以上にやはり口元が緩んでいる。家族愛の冷め切ったこの男、要は金である。