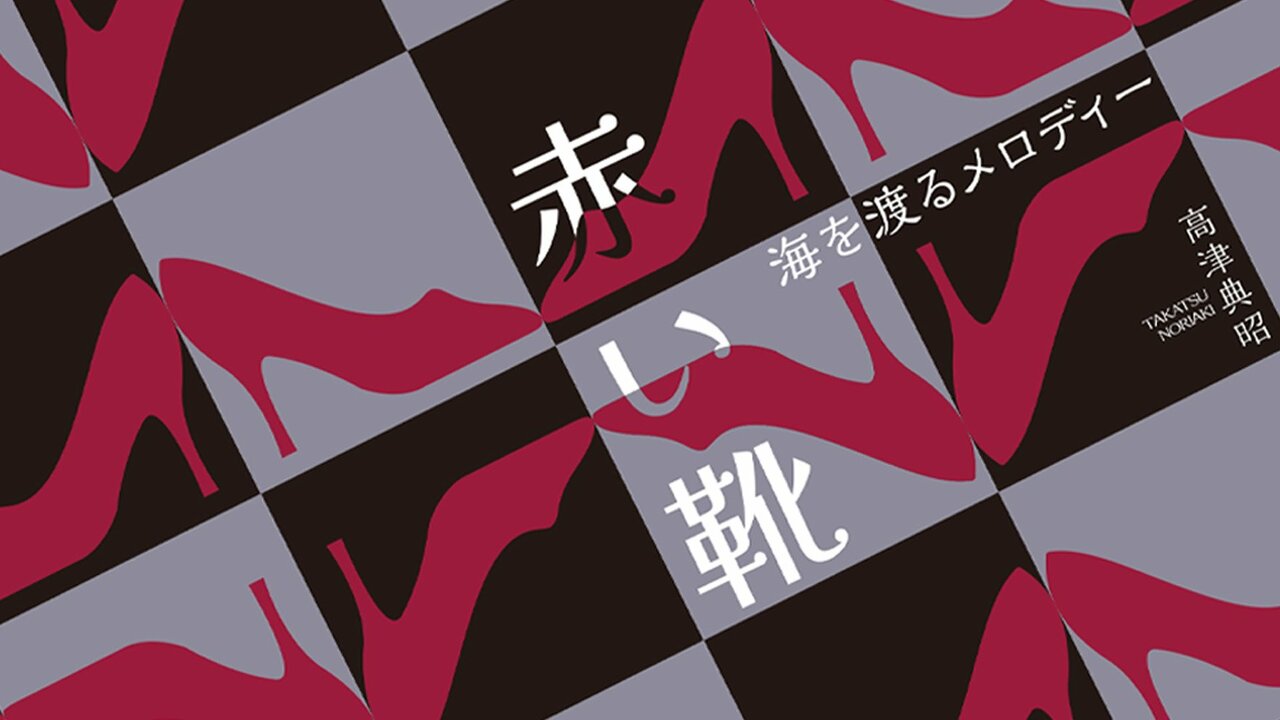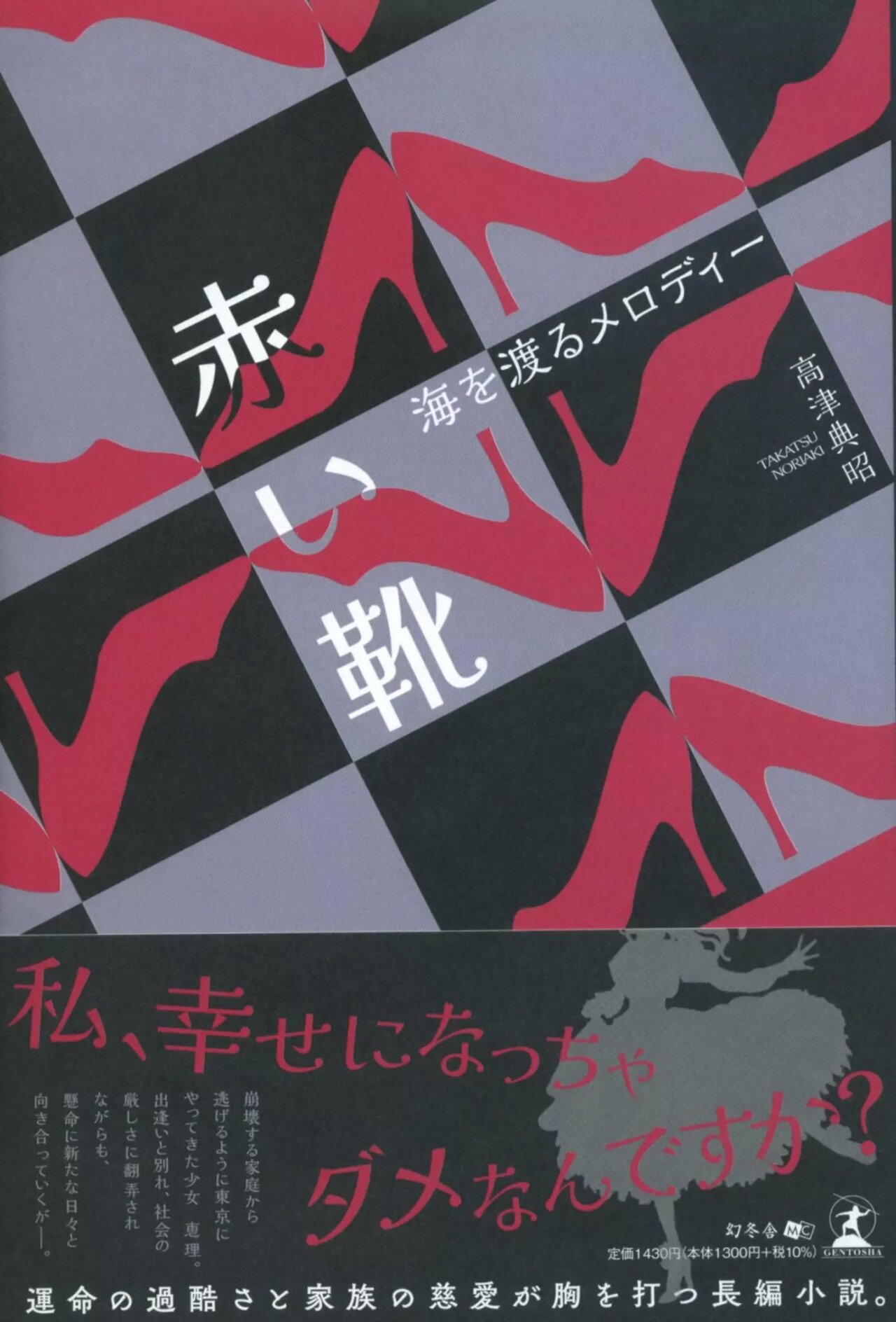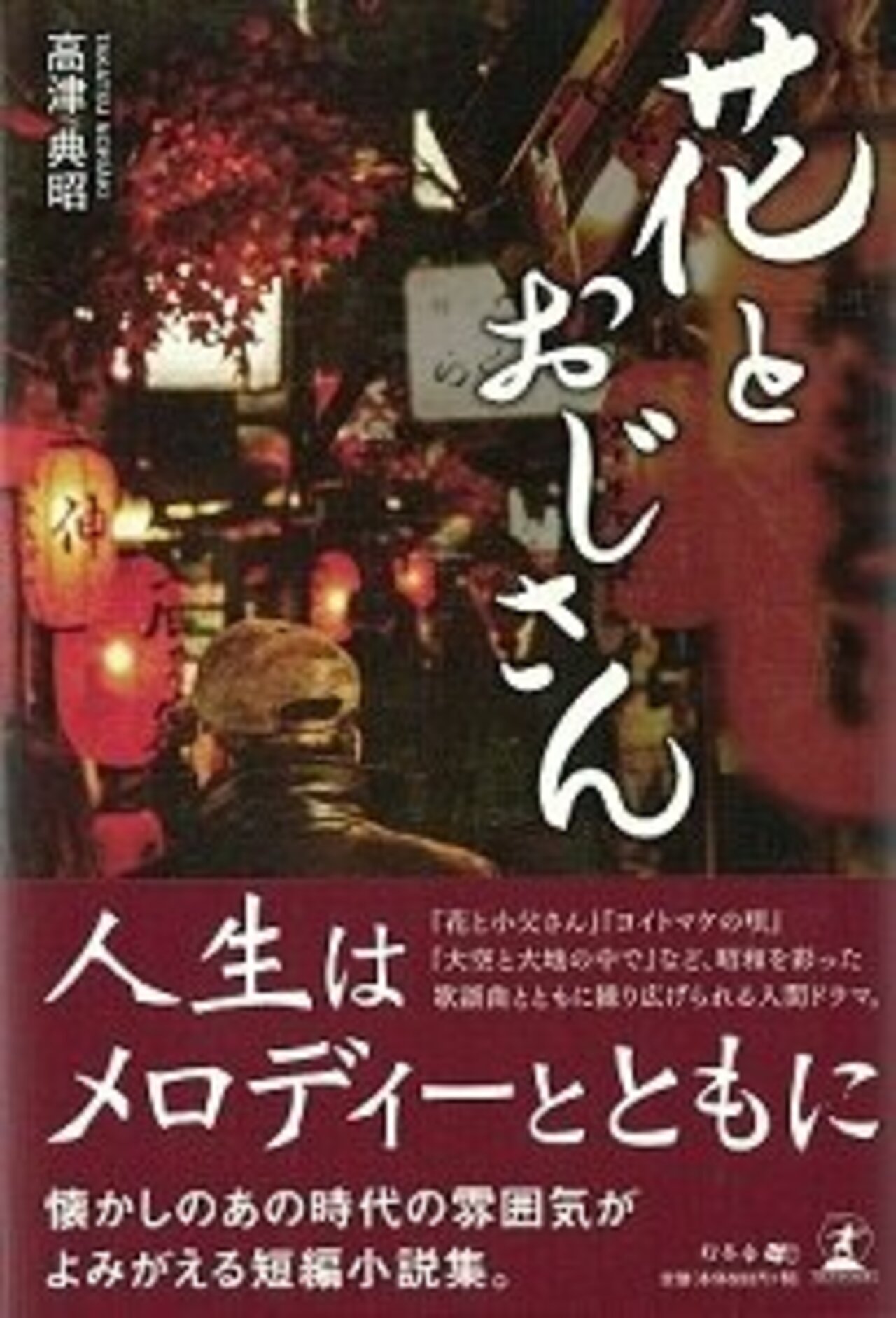【前回の記事を読む】家族愛の冷め切ったこの男、要は金である。昼間から島焼酎を飲んでいる父は、卒業後の仕事が決まった娘に口元が緩んだ。
第一章 壊れた家族
「恵理、その靴は役場にふさわしくないからプライベートでオシャレする時に履きなさい。いいよ、買ってあげる。ただし、仕事の時はこの黒いのにしなさい」
靴屋の店員は、2足も買ってもらえるので、気が変わらないうちにと、話をまとめにかかった。
「お嬢さん、それでは勤めの時にはこの黒い靴で。そしてプライベートではその赤い靴にしましょう。お母さん、いいですか?」
「そうですね」智子は(内心2足も買うようになるとは、大丈夫かな?)と思ったが、
「うわあ、この赤い靴、ほしかったあ。お母さん、ありがとう」
恵理のこんな嬉しそうな顔が久しぶりなので納得できた。
「それじゃあ、お靴を箱に入れましょう」
店員は大事そうに、2足をそれぞれの箱に入れた。
八丈島と沖ヶ島間は週に3回、フェリーが出ている。こんな小さな沖ヶ島でも車は必需品なので客船ではなくフェリーだ。ただし、沖ヶ島航路は、風浪や、潮流の影響を受けるためダイヤ通り運航できないことは多くある。
所要時間は3時間となっているが、きっちり時刻表通りに到着することは少ない。更に、沖ヶ島から八丈島までの95キロメートルは沖ヶ島を13時に出港して八丈島に16時前後に到着するので、必ず八丈島には泊まらなければならない。日帰りはできないので小旅行のようだ。
フェリーは黒潮の影響をもろに受けるのでその就航率は約70%だそうで下手したら1週間も欠航が続くことがあり、八丈島での宿泊費は予想が付かない。ただ、運良く、風浪・潮流が安定していたので恵理親子は翌日、無事に沖ヶ島に帰ることができた。このフェリーの名は「おきがしま丸」という。乗船券は2等席で大人1名、2800円だ。この日は出航が遅れていた。急ピッチで荷役作業が行われたが、定刻より22分遅れて出航した。
この日は波が高く揺れたので智子は船酔いした。恵理は父に似て船に酔ったことはない。智子は酔って気持ち悪い。沖ヶ島がだんだん大きく見えてきて少しは気休めになった。沖ヶ島は西方の青ヶ島ほどは険しくない。青ヶ島の場合は、島一周、高さ約200メートルの断崖絶壁が海面からせり上がっているが、沖ヶ島の場合、やはり高さ約100メートルの断崖絶壁で覆われてはいるものの、前述したように、1か所だけ入り江がある。そこが青ヶ島との違いで、船を繋げる入り江があるため、江戸時代から漁業が村の基幹産業である。