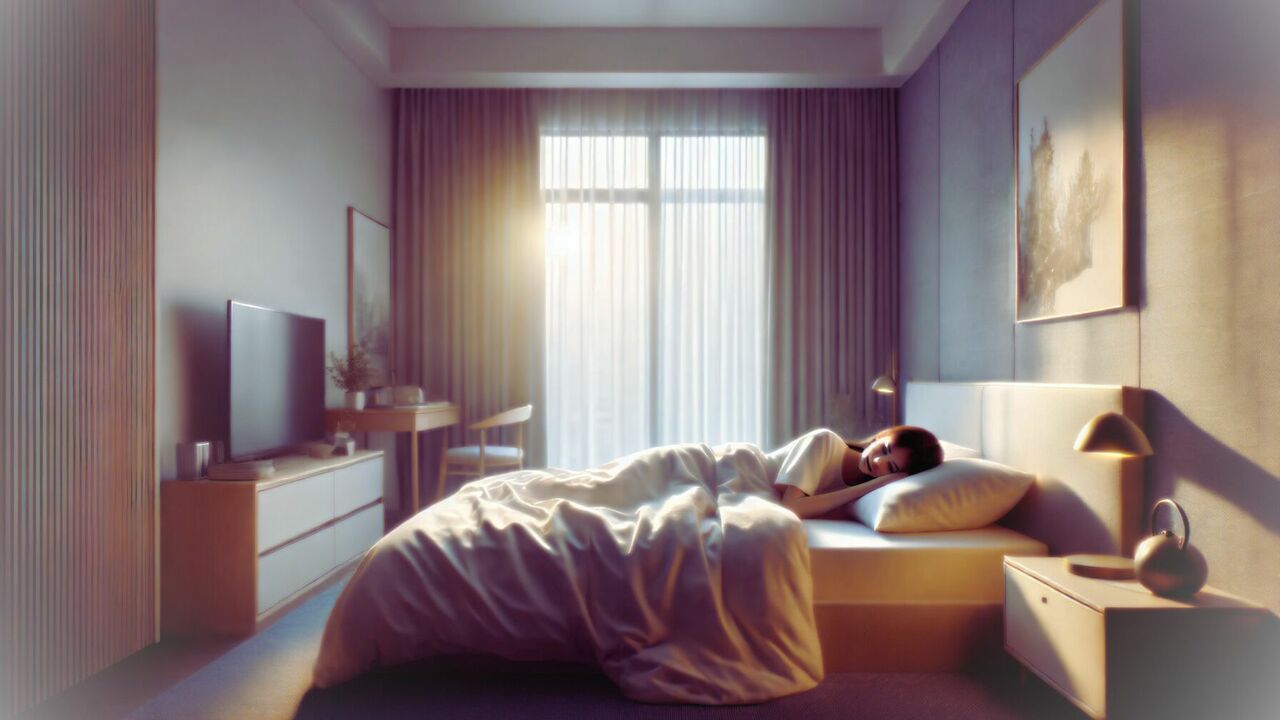第3章 香澄のこと
今夜も川村が訪ねて来るだろうということで、祐介は授業が終わったあと美沙と待ち合わせ、安田が一夜を明かしたという美沙のアパートを初めて訪ねた。
国立(くにたち)の天橋(あまばし)大学近くの閑静な住宅街にそのアパートはあった。そのアパートの入り口にある門扉に祐介は思わず立ちすくんだ。その門扉は青銅色の金属でできたものだが、デザインを見ると葡萄の蔦が門扉に絡まり、更にトカゲが何匹も貼り付く彫金が施されていた。
その気味悪さは、侵入者を拒むだけの迫力があった。それも、そこをくぐったら最後、何者かの餌食にされ無事には出られなくなりそうな、そんな雰囲気さえ漂わせていた。
「祐介君、そこで突っ立ってないで早く中に入って」
美沙は、自分の部屋の鍵を開けながら、門扉の前で入るのをためらっている祐介を振り返り、小声で、しかし語気を強めてそう促した。男が出入りするのをアパートの住人に見られたくないらしい。気にする割には、安田や川村を引き入れているではないかと、祐介は不機嫌な気持ちを心の内にぶつけた。
八畳の部屋は、本棚とセミダブルの大きなベッドが占領していた。その間にあるステンレスの脚にガラスの天板が載った小さなテーブルを挟んで、美沙と向かい合って座った。
部屋の隅には描きかけのカンバスが立てかけられていた。壁には美沙が描いた絵が掛けてあった。その絵は、背景が橙色(だいだいいろ)で明るく、建物群が強固な漆黒(しっこく)で塗り込められている。そのコントラストが絶妙なバランスを保っている。
美沙には絵の才能があった。この才能は、当然のことながら個性的であり、なおかつ如何(いか)に見る者にインパクトを与える絵を描けるかにかかってくる。
美沙の、画面せましと大胆に描き切る構図の巧さは、祐介など到底及びもつかぬものと思われた。画家として将来認められるには、才能五割、運五割と祐介は踏んでいる。彼女の場合は、そのうちの才能は十分に満たしていた。そうなると、後は運がいかがなものかである。
その壁の絵の話から始まって、やがて好きな画家の話になると、絵が好きなもの同士、話は尽きなかった。気が付くと部屋の時計が夜の十二時を廻っていた。結局その晩は、川村は来なかった。祐介は終電を逃し、そのまま美沙の部屋で夜を明かしてしまった。