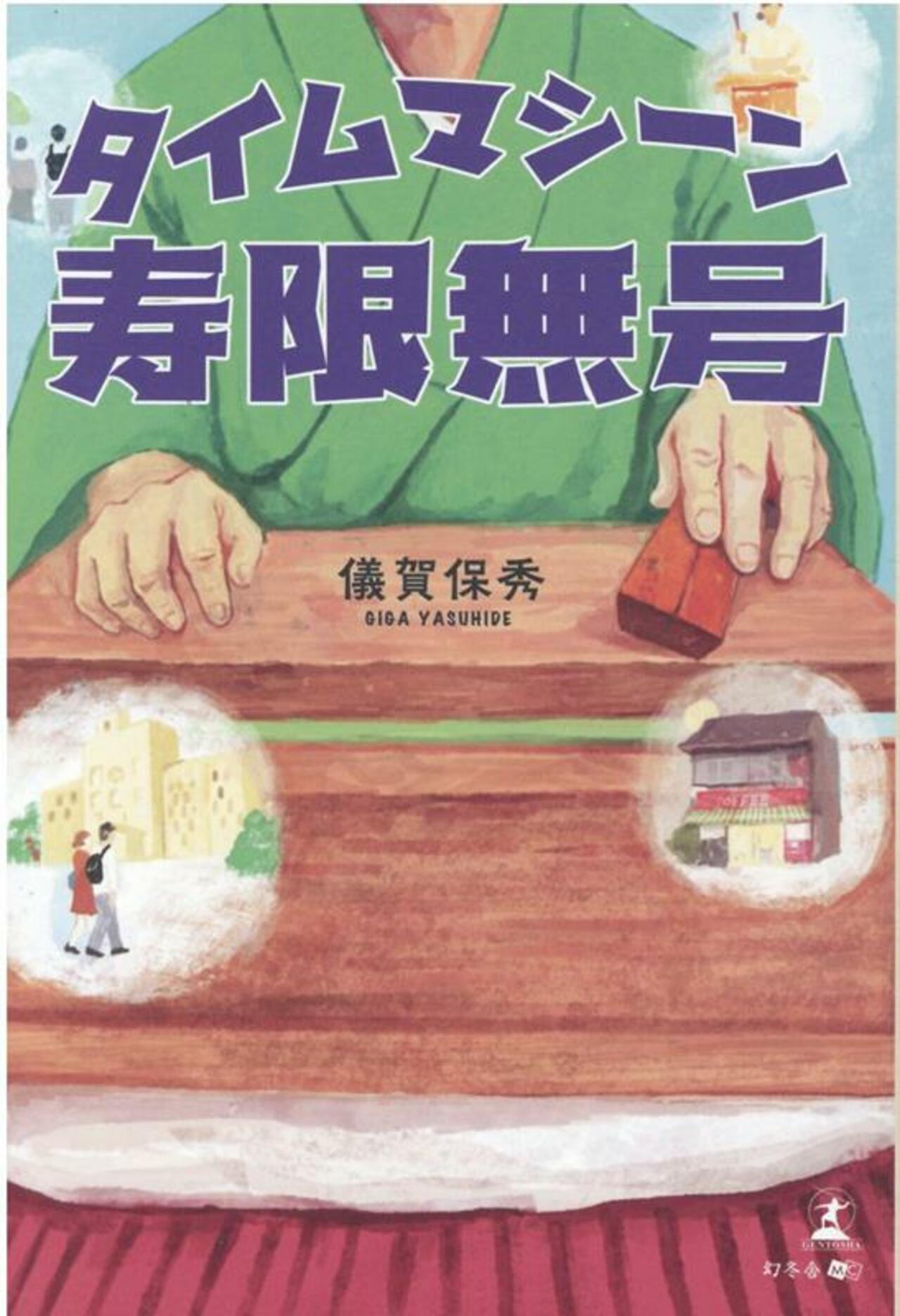そんな彼がいるような気がしたのだが、ザっと見た限りその姿はなかった。
ちょっとホッとした。
客席にデーンと構えていられると、やはり落語がやりにくい。
芸と人柄に惹かれて……。
そう言われた相手の前で落語を披露するとなると、何か審査をされているような気分でどうもやりにくい。相手は弟子志願者なので、立場的にはこちらが上のはずなのだが、なぜか向こうのほうが強い立場に立っているように思える。
それは何とか避けられた。
だが、落語をやりつつ、あのイケメンの顔がしきりに浮かんできて、どうも集中できない自分がいた。お世辞にも良い出来とは言えなかった。入場料を払って見に来ていただいたお客様には申し訳ない。そんな気分だった。
何だか落ち着かない。身体に浮遊感がある。ふわふわ。
楽屋には出演する落語家の身の回りの世話をする若手落語家が控えている。入門して一年ほどの落語家だ。東京でいう前座。上方には真打、二つ目、前座という明確な地位の制度はないのだが、東京と同様に寄席には、こういう役割の落語家がスタンバイしている。その若手落語家が自分を見て何か様子のおかしさを気にする姿が見てとれた。
やはり、弟子志願者が来たことが自分にとってかなり大きな出来事であり、普段と様子が違っているのだ。
後日連絡するとメールをしたが、どれぐらい間を置いて連絡したら良いものだろうか?
今度会う時は、どのような対応をすれば良いのだろうか? そもそも自分はあのイケメンを弟子にするつもりはあるのか?
色んな思いが交錯して、ボーっとしている時間が増えた。
「どうかしはりましたか?」若手落語家が気を利かせて聞いてきた。
「いや、別に。何もないで」喜之介は慌てて否定。その様子自体がやはり普通ではなかった。
そして、出番を終えて天神亭を出た。
頭の中は弟子志願のイケメンのことでいっぱいだった。
「あのう、すいません!」
誰かが声をかけてきたことに最初は気付かなかった。
「あのう、すいません!」また声をかけられた。
これは確実に自分に用事があるのだ。
声の主は喜之介と同年代と思しき男性であった。