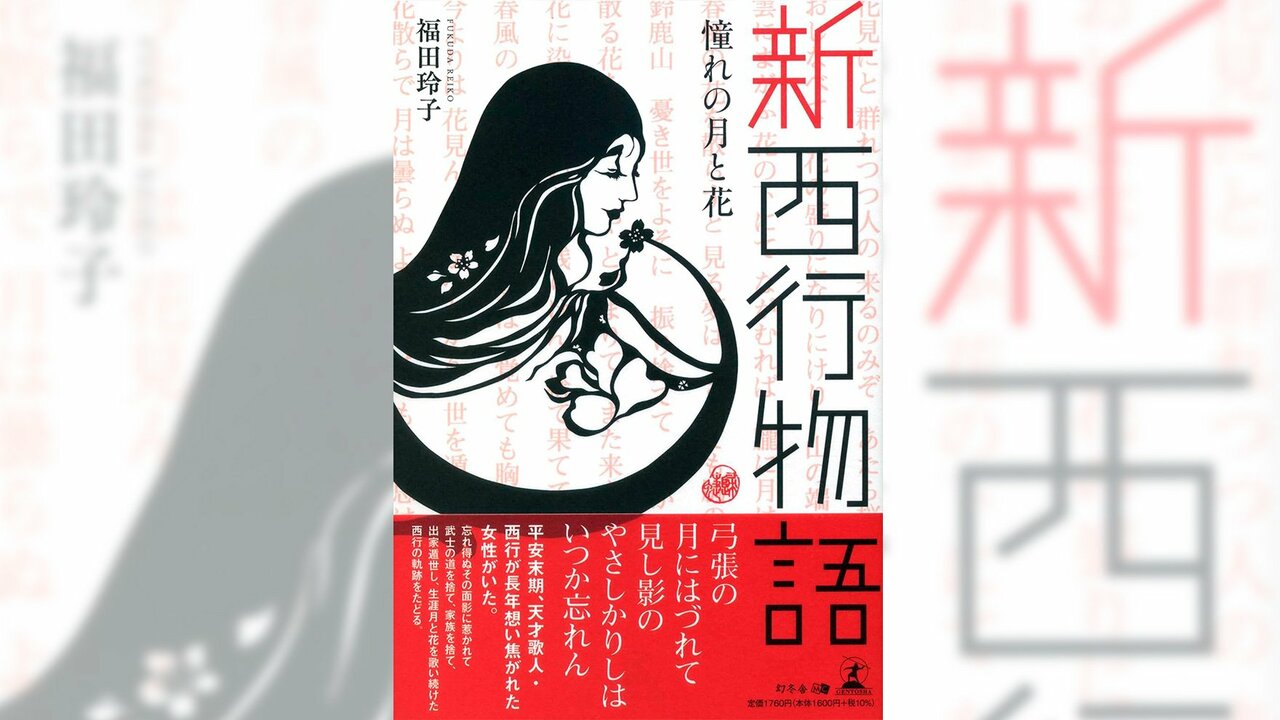序章 旅立ち
南都(なんと)(奈良)の寺々は平重衡 (たいらのしげひら)に焼き払われた。武力を持つ者が権力を持つ世となり、文化も伝統も失われてしまった。
こんな時勢でも、戦乱で荒れ果て仏道など忘れ去られたこの世に再び大仏像を造り、人々にその慈悲深い姿を見せることは、できるのだろうか。そしてまた、実の兄源頼朝にも後白河上皇にも裏切られた源義経を奥州 (おうしゅう)に送り届けるという途方(とほう)もない企(くわだ)ては、できるだろうか。
世を捨て年老いた自分にはまだ、その力が残っているだろうか。
「円位上人(えんいしょうにん)が奥州 (おうしゅう)をご覧になれば、素晴らしき歌が生まれると存じます」ぴしり、と盤上 (ばんじょう)に碁石(ごいし)を置くような口調で、重源 (ちょうげん)は西行に言った。
重源(ちょうげん)は自分の一言が老西行の心に埋もれていた何かに火を点(とも)す過程が、掌(たなごころ)を指(さ)すようにわかった。
やられた、と思う暇(ひま)もなく、西行は深く重源 (ちょうげん)に頷(うなず)いてしまっていた。
時は春だ。今から旅支度(たびじたく)を調(ととの)えれば、やがて奥州 (おうしゅう)にも夏が近づく。真冬の奥州 (おうしゅう)は自分には、もう到底 (とうてい)無理だ。だが暖かい季節ならば、行けるかもしれない。
二、三年後では無理であろう。だが今ならまだ、自分は作ることができるかもしれない。
未だこの世に生まれ出ていない、新しき歌を。
重源(ちょうげん)の立ち去った庵室 (あんしつ)で、西行は、にやりと笑った。それは重源 (ちょうげん)が見たら驚くに違いない、僧形(そうぎょう)に似合わぬ不敵な笑いだった。
行ってみると、するか。
西行は狭い庵室 (あんしつ)を見回した。惜しい物など、一つもない。我が身一つさえ、この先(さき)老いさらばえていくばかり、今更 (いまさら)惜しくもなかった。
西行庵(あん)を囲む雑木(ぞうき)の枝々越しに、二見が浦(ふたみがうら)の碧(あお)い海と美しい島影が見えた。海の向こうの空が、茜(あかね)色に輝いていた。