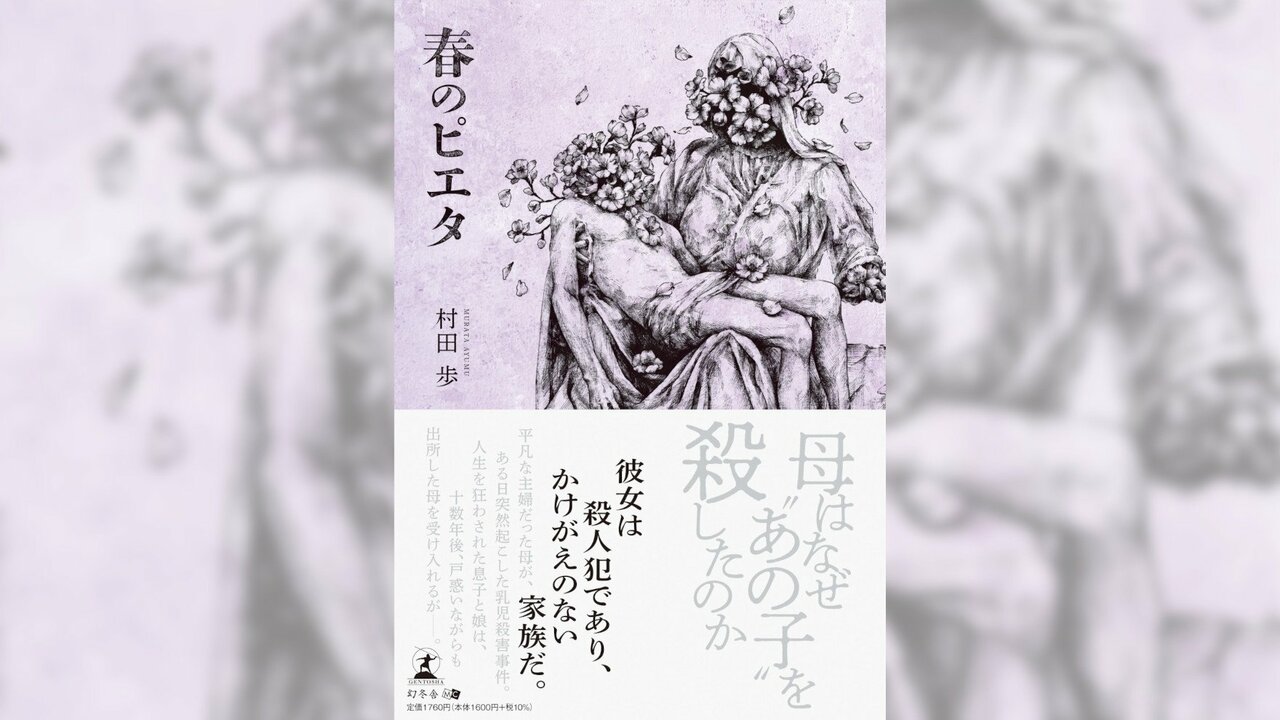優子 ―夏―
考え始めると、いつも足元から自分の身体がねっとりと溶けていって、終いには黒い地面に吸い込まれていくような心持がする。あとには汚い小さな水溜まりが残るだけだ。そうした感覚に襲われるときの無力感といったらない。そしてこの無力感は、きっとあたしだけのものだ。
人を殺す縁とか、魔の風とか、とても人には話せない。相手がおにいちゃんだったら完璧にやり込められるだろうし、家族以外の人に話したら、眉を顰められるだろう。
犯した罪は犯した人のものだということくらい、あたしだって頭ではわかっている。だから裁判があって、罪を犯した人は罰を受けるのだ。そんなことくらい、わかっている。わかってはいるけれど、それが自分の身内のこととなると、簡単には割り切れなくて、いろいろなことを考えてしまう……。
美津子さんの、自分の外からやってくるの、ダイナミックに襲われる感じ、といった言葉を家に帰ってから思い出したら、自分の奥深くに閉じ込めてあったあの無力感が蘇ってきた。
興奮気味に話す美津子さんと、自分の身体の奥底に巣食う、どんな努力や前向きな気持ちも殺(そ)いでしまう無力感と、両極端のふたつのものを交互に眺めるようにして、あたしはしばらくのあいだぼんやりしていた。
まだ明るい空の東の方に、園児の折り紙細工のような白い月が掛かっている。そろそろ出かける時間だ。聖を抱っこひもで胸に抱いただけで、身体が汗ばんでくる。家を出たところで、まだ就学前の女の子が三人、浴衣姿で駆けていくのにすれ違った。もしかしたら今夜は近所で盆踊りがあるのかもしれない。
ふと、回り道して島田製本を覗いてみようと思い立った。そろそろおかあさんが仕事を終える頃だ。
出産のときは慎さんが付き添い、退院後の三週間あまりは、夫の実家で過ごした。慎さんもその間だけは実家から会社に通った。あちらの両親には結婚を反対されたから、あたしには少し抵抗があったけれど、お義父さんもお義母さんもそうするのが当然という感じで温かく迎え入れてくれた。
少なくとも表面上は、わだかまりは消えていて、二人とも初孫に夢中だった。家のことを手伝おうとすると、寝てなさい、寝てなさい、と言われた。滞在中、あたしの実家の話は一度も出なかった。