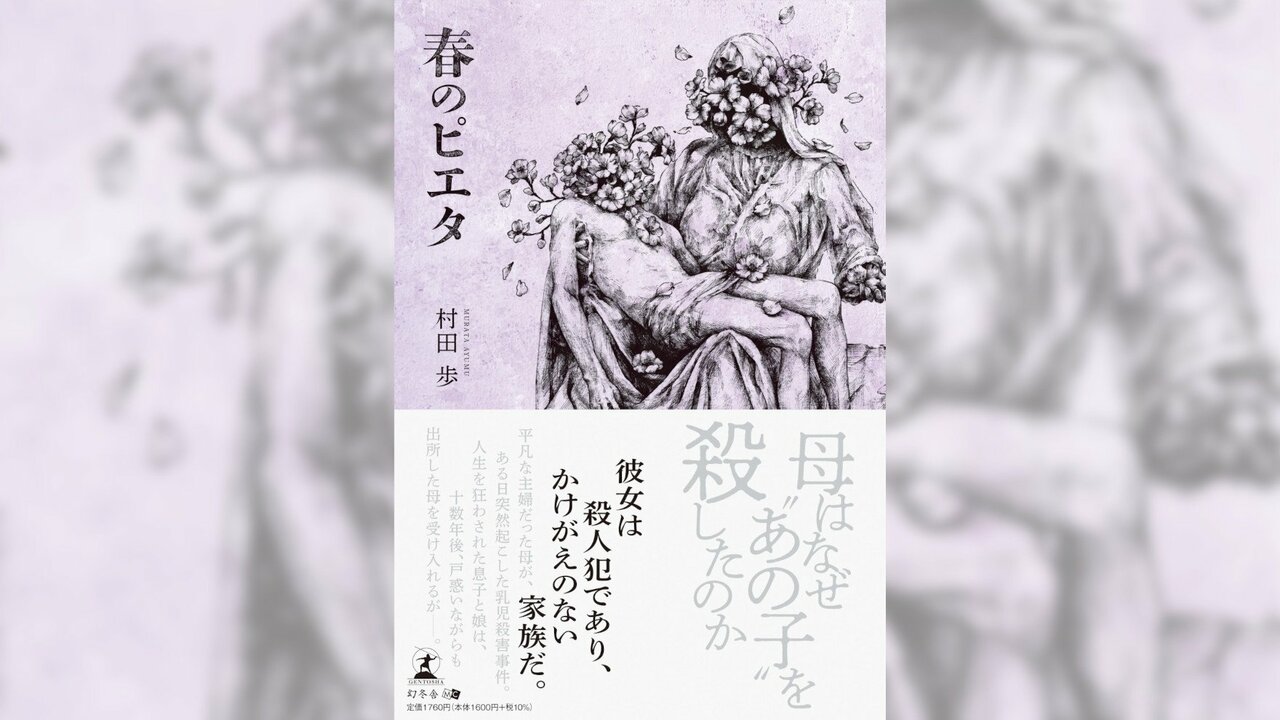優子 ―夏―
あたしは相槌も打たずに話に聞き入った。思い出すとか懐かしむという言葉を、美津子さんは忌々しいことのように口にした。それから声を潜めて、
「予感……いえ、やっぱり気配ね。でも、気配っていうと、弱すぎるか……。
とにかく、自分の中から出てくるものじゃないの。外からやってくるの。静かに、でもダイナミックに襲われる感じ。わたしたち、まだ終わっていない、また新たなかたちでめぐり合う、そのときが刻一刻と近づいている……。続いているのよ、地下水脈みたいに、ずーっと。それがまた地上へ吹き出しそうになっている。不思議なエネルギーがわたしに迫ってくるの。
たしかなのよ。たしかに迫ってくるの。自分の力じゃ抗えないものが……そんなとき、優子ちゃんから電話をもらった」
美津子さんは、なにかのお徴(しるし)のようにあたしをまじまじと見つめた。
あのときの美津子さんの話を思い返すと、あたしの気持ちはひどく個人的な気分に染まってしまう……。
高校のとき、おにいちゃんの蔵書の一冊を盗み読んだことがあった。家が狭いから本棚は共有で、そこに並んでいる本はおにいちゃんのものでも、大学の教科書とか大事な本でなければあたしも手に取ることがあった。
しかしあたしが盗み読んだのは、そうした陽の当たる場所に並んでいた本ではない。おにいちゃんの勉強机の下、段ボール箱に入れられた本の中の一冊だった。
そこには凶悪犯罪に関して書かれた本が何冊も隠してあった。どれも事件を取材したり裁判を傍聴したりして書かれた本だった。あたしはその箱を開けたとき、きっとこの中におかあさんの起こした事件に関する本があるはずだと、どきどきしながら探した。でも見つからなかった。
代わりに手に取ったのは、殺人犯十数名に手紙や面会でインタビューしてまわった人の本だ。
その本を読んで不思議に思ったのは、インタビューに答えた人たちの何人かが―― 割合からいうと半数以上だった――人を殺す瞬間を、外からなにかにけしかけられたような感じ、と答えていたことだ。殺れ、と声がしたという人もいた。