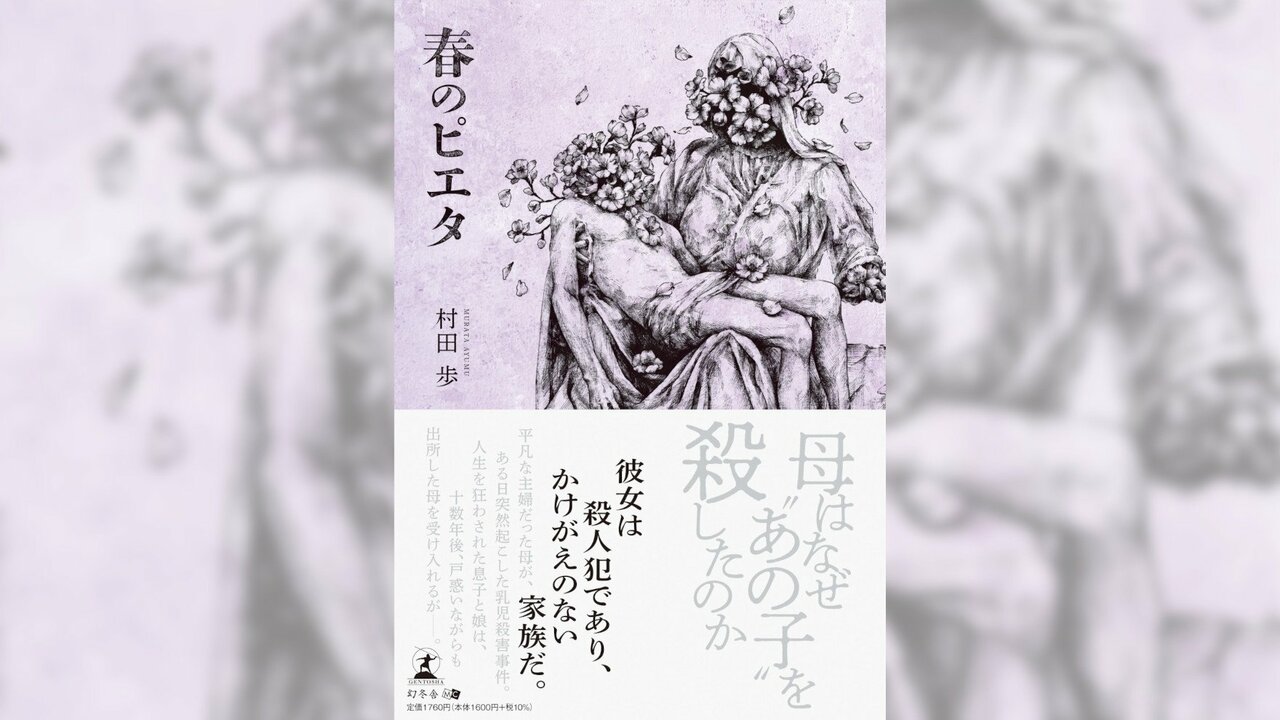優子 ―夏―
美津子さんは大学のサークルで後輩だった佳香さんの勤めるクラブに訪ねて行って、劉生さんを返してほしい、と言ったそうだ。
ランチコースの一品として出てきた北京ダックロールを上品にかじりながらそう告白した美津子さんには、究極のお嬢様の持つ人の思惑などまるで気にしない凄みのようなものがあって、あたしはすっかり気圧されてしまった。
おにいちゃんはモノじゃないんだから、取られただの返せだのというのはおかしい、とちらっと思ったけれど、そんなリクツなどとても通用しないと、美津子さんを前にして感じた。
これを未練などと呼んではいけない。そこいらの男と女のありふれた感情といっしょにしてはいけない。フカヒレの入ったとびきり美味しいラーメン――ラーメンとは言わないんだろうな、あれは――を啜(すす)りながら、あたしは魔法をかけられたようになった。
美津子さんは、女優としてデビューする前の、まだブルネットの髪をもこもこパーマにしていた頃のマリリン・モンローに、顔だけ似ていた。色素が薄いのか髪も目も天然の茶色で、肌はボーンチャイナのようなこくのある白さだった。こんなに綺麗で上品でしかもとびきり頭のいい女性が、なんでまたおにいちゃんなんかを好きになったのだろう。
たしかにおにいちゃんは身長が百八十センチを超える長身で、見てくれもまあまあだけど、困ったことに性格がよろしくない。あの捻くれ者のおにいちゃんと、こんな稀有といっていいほどピュアなハートのお嬢様と……まったく合点がいかない。
しかもまかり間違ったら、美津子さんはあたしのお姉さんになっていたかもしれないのだ。そう思うと、夢のような気がする。いや、夢で終わったのだから、まさに夢そのものだ。
デザートの杏仁豆腐まできて初めて、美津子さんは顔を曇らせ伏し目がちになった。
「劉生さんの抱えているものを、わたしはちゃんと理解してあげられなかった……」あ、話がそんな方へ行っちゃうの、なんだか困ったな、嫌だな――あたしは身構えた。
どんなに美津子さんが頭がよくても、どんなにおにいちゃんに惚れていても、あたしたち兄弟のことはわかりっこない。あたしは誰に対してもそう思っている。意地悪してくる人、好奇心で近寄ってくる人、憐れむ人、親切な人、どんな人にもわかりっこない。