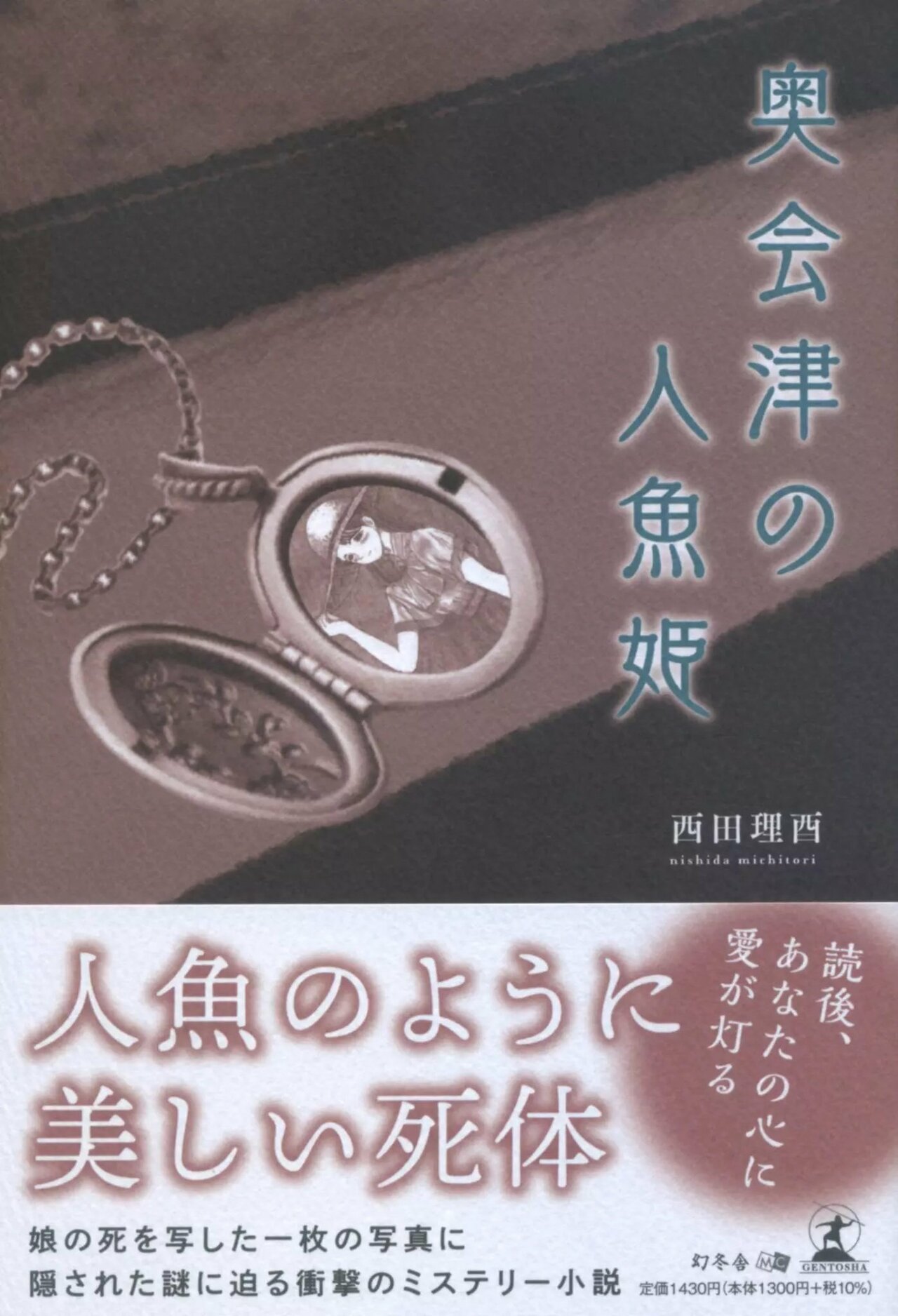正直、小山内の答えに、それほど大きな情報を期待していた鍛冶内ではなかったが、それにしてもそれは、肩透かしと呼べるくらいに意外なものだった。
続けて聞こうと思っていたことを、前段でくじかれた形の鍛冶内は、なす術なく、茫然とその場に立ちつくすしかなかった。立ち去る小山内の背中に、鍛冶内の力ないお礼の言葉がむなしく響いた。
「記憶が飛ぶ症状はなかった…………。では印刷所で聞いた由紀ちゃんの話とは一体何だったんだ」
ぶつぶつと独り言を言いながら、未練げに病院のほうに一瞥をくれると、鍛冶内は会津若松駅に向かうタクシーに乗り込んだ。駅周辺なら、飛び込みでも泊まれるビジネスホテルくらい見つかるだろうと思いながら。
「もし記憶が飛ぶのが本当のことなら…………」
もしその症状があるのに、心療内科の主治医にも言わなかったとするなら、汐里の心の中には、一体何が隠されていたというのだろうか。
それともそんな症状など最初からなかったのか。由紀ちゃん一人の話を、あまり真に受けないほうがいいのだろうか。
定食屋を探して駅のまわりを散策した鍛冶内だったが、彼にとってちょうど良い店がなかなか見つからず、仕方なく最後は諦めて地元の居酒屋に入り、酒は頼まず、何種類かメニューを注文して遅い夕食にした。
次の朝、ビジネスホテルで時間潰しの朝食をゆっくりと食べ、10時待ち合わせの喫茶店へと足を運んだ。待ち合わせの相手は、会津若松市に住んでいるという、有島という女性で、汐里の高校時代の同級生だった。
「忙しいところ、ごめんなさい。僕は汐里ちゃんの父親の友人の鍛冶内です」鍛冶内にぺこりと頭を下げたのは、凄く小柄で華奢な女性だった。
「忙しくはないです。私、保険会社辞めて、プーしてるんで」
「来ていただいただけでも、ありがたいですよ。これはほんの気持ちですが……」
と言いつつ、鍛冶内は5000円分の商品券が入った紙包みを、有島に渡した。
何度か断った有島だったが、最後は根負けして、丁寧なお礼を鍛冶内に言った。
「有島さんは、汐里ちゃんとは高校3年間一緒のクラスだったそうですね?」この場で鍛冶内は、汐里のことをあえて、ちゃん付けで呼んだ。
「ええ。あまり親しいってことはなかったけど、3年間一緒でした。というか、うちの学校、基本的にクラス替えはないんです」
「親しくないっていっても、大きな保険に入ってくれと頼めるほどの仲だったってことでしょ?」
すると有島は、少し苦笑いのような表情をしながら、届いたばかりのアイスカフェオレをちょっとだけ口に含んだ。
【前回の記事を読む】どんな女性にも愛憎の目的を達するための魔性の気質が備わっており、男の自分にはどうしても理解できない領域がある...