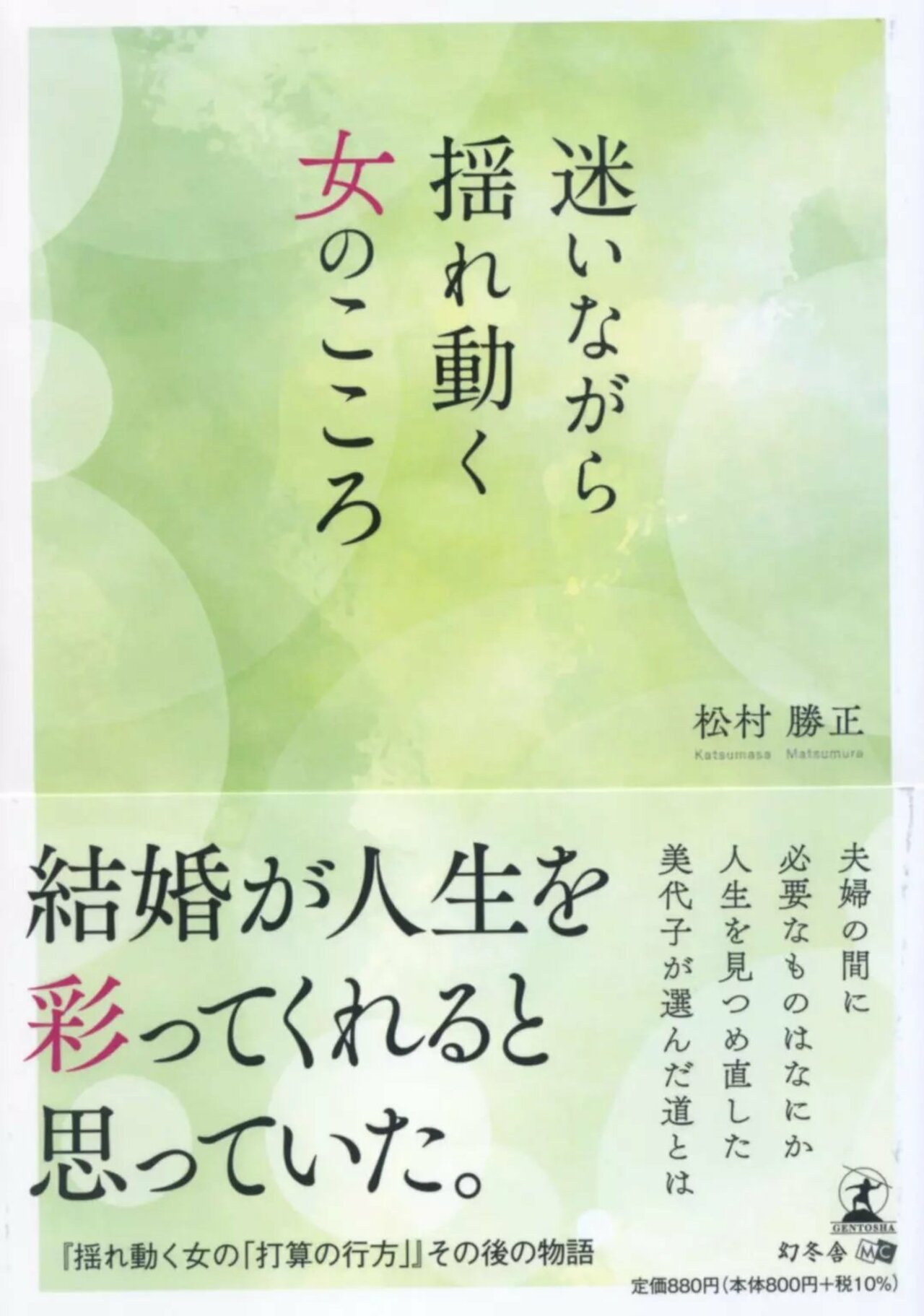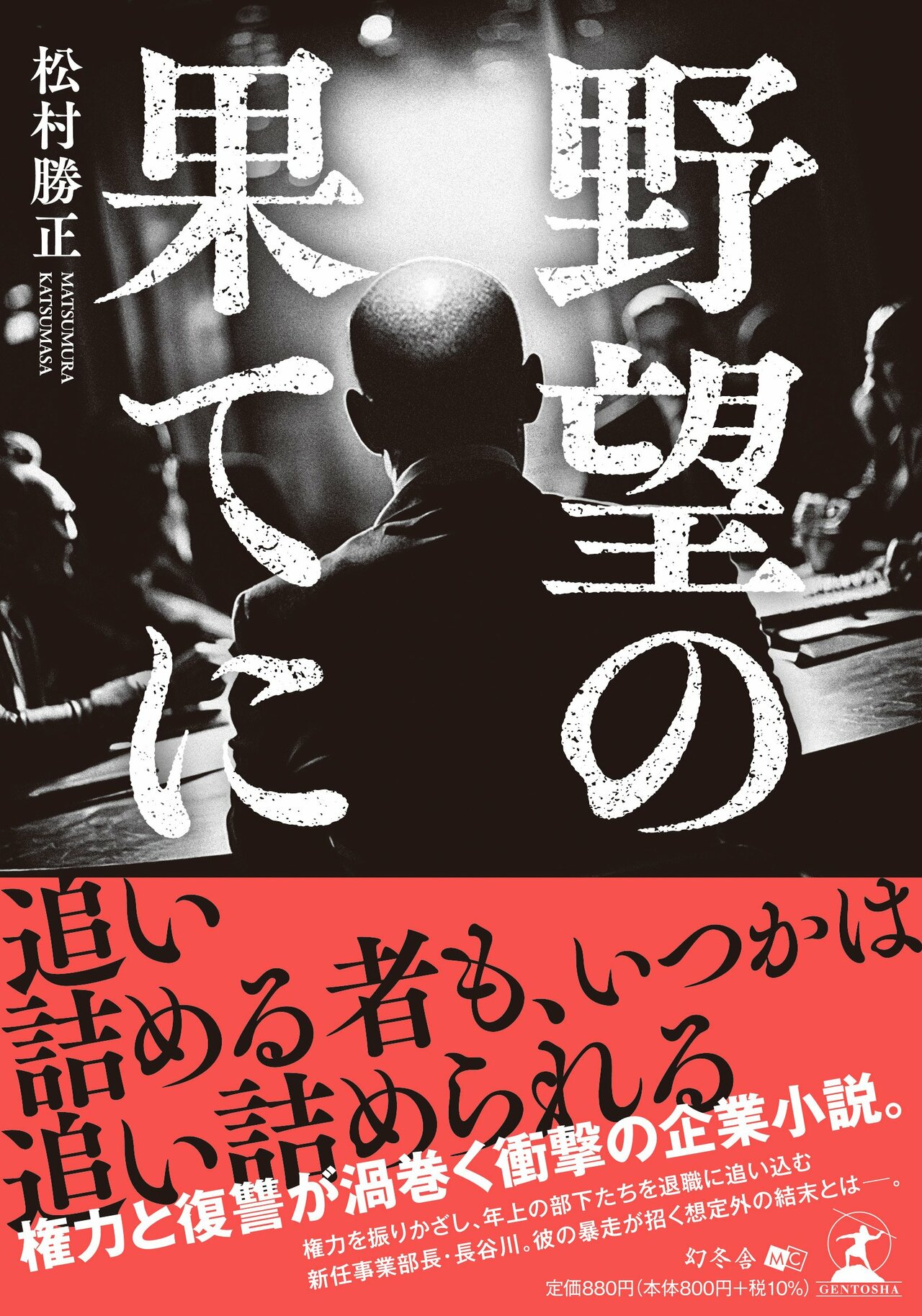「ご主人は納得されたのですか?」篠田さんは少し間をとってから、
「主人の実家は福井県で、お父様が地方公務員、そして母親が地元の中学校の教師という、保守的な家庭に育っているものだから、嫁は家にいて家庭を守るもの、というのが子供の頃から植え付けられてきている。
だから結婚生活四、五年経った頃に仕事を辞めてくれないかという発言が増えてきた。私たちには子供がいないから、私にも言い分があって、毎日家にいて何をすればいいのか、お互いに口数が少なくなっていった。彼はお酒も飲まない真面目人間を画に描いたみたいな人だから、家庭内から潤いが消えていたね」
少し沈んだ話になって来た時、オーダーしたランチプレートが目の前のテーブルに置かれた。プレート上がお花畑みたいにカラフルに仕上げされていた。美代子はバッグからスマホを取り出し、食事前のプレートをカメラに収めた。
「山形さんはいつもそうなさるの?」と美代子の一連の仕草を眺めていた。
「レストランで食事する時など、珍しい食事は後々の話の種のために、一応記録しておきます。よく若い女性たちは『映える』と言いながらスマホで写真をとっていますよね。おばさんには似合わないかもしれませんが」
「おばさんだなんて、山形さんは十分若見えしますよ」
「ありがとうございます」
二人はきれいに盛り付けされたプレートを見つめながら、右手にフォークを持ってどこから手を付けようか、と迷っていた。
そして篠田さんが「盛り付けを壊すのがもったいないね」と言いながら、最初にサラダから手を付けた。美代子も「ドレッシングのかけ方が絵画のようで、流石、フランス流ですね」
しばらく、無言でプレートの盛り付けを壊し始めた。ほぼ終わりに近づいた頃、店員さんが来て、「飲み物は何にされますか?」とタイミング良く聞いてきた。
【前回の記事を読む】ジムで気が合いそうだなと思っていた女性に誘われて一緒にカフェへ。「独り身になってから、気が向いた時に空の人になっているわ」と香水の甘い香りを漂わせながら話す彼女