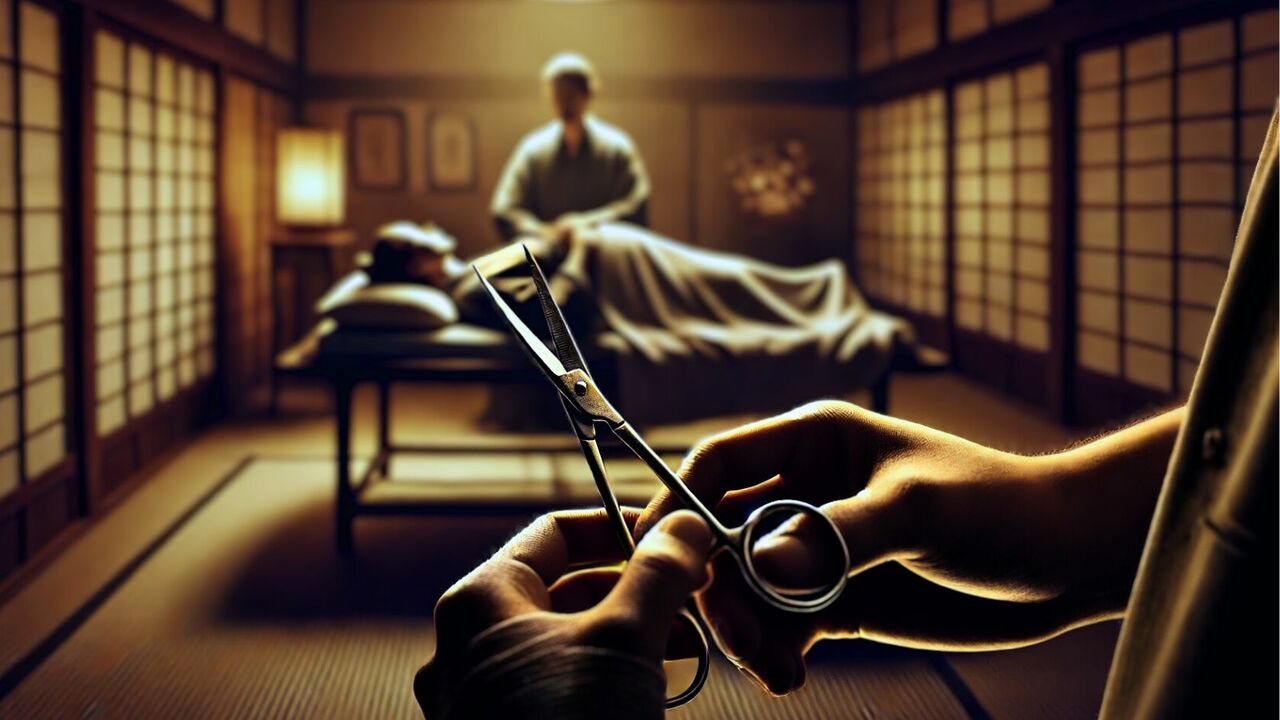第一章
五
明治五年九月二十六日(一八七二年一〇月一八日)
「中村屋か……」
黒々と墨書された看板を見上げながら、万条が感慨深げに言った。日暮れとともに、万条はヨンケルを、祇園八坂神社の境内にある老舗料亭の中村屋に案内した。
京都では知らぬ者のいない名店で、この夜、京都療病院の設立に関わった主役たちにより、ヨンケルの歓迎会が催されたのだ。その末席に、万条は安妙寺とともに加えてもらうことになった。仮診療所が開業してから、すでに十一日が経っていた。
万条にとって八坂神社など、自分の庭のようなものだった。しかし中村屋には、これまで一度も足を踏み入れたことがなかった。若い万条にとって、まだまだ敷居の高い場所だったからだ。
室町時代の創業とされる中村屋は、向かいの藤屋とともに二軒茶屋と呼ばれていた。
十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の中にも描かれており、長崎出島のオランダ商館長が名物の田楽(でんがく)豆腐を好んだことが伝わっていた。また明治維新の影の立役者とされる、土佐の坂本龍馬もその常連だったという。
ヨンケルは門をくぐるなり、「オー、バッケ!」と、思わず感嘆の声を上げた。
こうした場所は初めてのはずだった。京都に着くなり診察を始め、まだどこにも遊びに行けなかったからだ。
女将に先導され、座敷に入ると、明石博高と大木玄洞が待ちかねていた。他に二人の先客もいて、明石がさっそくヨンケルに紹介した。
「こちら、京都府の──」
明石の右に座っていたのは、なんと大参事(だいさんじ)の槇村正直(まきむらまさなお)だった。元長州藩士で、維新早々に新政府から京都府へ出仕してきた重鎮だ。
万条が驚いていると、次に左の人物が口を開いた。
「山本です」
眼を閉じたまま、背筋を伸ばすのに苦労している様子は、京都府顧問の山本覚馬(かくま)に違いなかった。覚馬は会津藩の出身で、長州の槇村大参事とは、かつて敵どうしだった。しかし今は、親密そうに肩を並べていた。
時代の移り変わりを感じざるをえない光景に、安妙寺が身を縮めて呟いた。「大物ばっかりやな……」
万条も同じ思いだったが、そのときふと、三条実美公のことが頭に浮かんだ。維新の動乱も収まり、三条公が久しぶりに里帰りしたときだった。京都に残った公家たちに、こう苦言を呈したのだ。
『東京遷都で、京都の衰運は目を覆うばかりとなった。しかるにその障害は、京都市民の人情にある──』と。