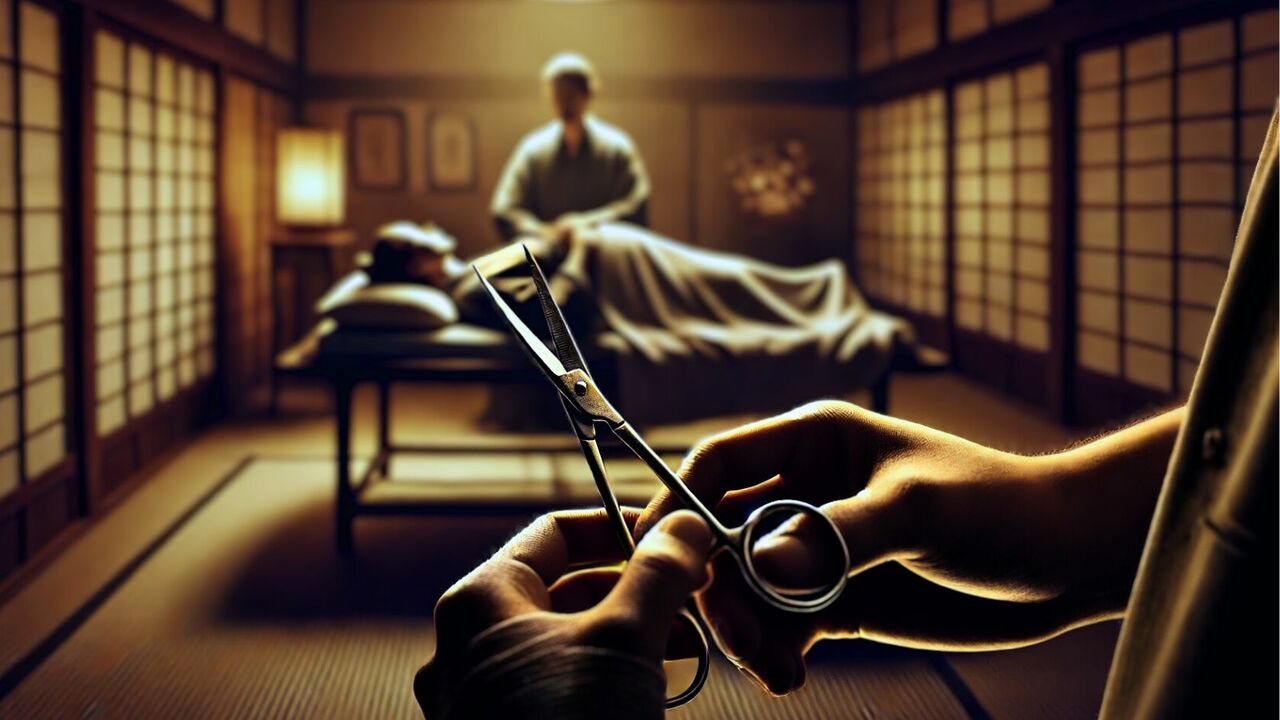序章
明治二十一年(西暦一八八八年)十月
「森 鷗外です──」
森は酌をしながら、気恥ずかしそうに答えた。
「鷗外?」
万条が訊き返すと、森は色紙に、万年筆ですらすらと書いて見せてくれた。
「はい、こんな字です」
「でも、どうしてそんな筆名にしたんだ?」
横から大御門が、興味深そうに尋ねた。その隙に、仲居は鍋を炭火の上に置き、手早く支度を調えて行った。
「千住のかもめの渡しの外、という意味です。つまり吉原のような遊興の地には、決して近付かないという決意ですね」
「なるほど……」と、万条は感心しながら盃を飲み干した。
この日、森 林太郎、万条房輔、大御門不比人の三人は、帝国大学の龍岡門から出てすぐの、江知勝という牛鍋屋の座敷にいた。
森は先月、ドイツ留学から帰国したばかりだった。軍医として陸軍大学校に就任することが内定したとのことで、その前祝いにと、先輩の大御門がこの宴席を企画してやった。だがその直前、森が文学を始めたという噂が伝わってきた。大御門が確かめてみたところ、森はそんな筆名を教えてくれたのだ。
「鷗外か……」
大御門が改めて繰り返した。そしてしばらくの間、三人はその話題で盛り上がった。やがて、鍋からいい匂いが漂って来た頃、「そろそろ食えそうだな」と、大御門が中を覗き込んで言った。
「それにしても、時代は変わったものだ──」
感慨深げに漏らしながら、真っ先に肉を取ったのは万条だった。明治の世も、すでに二十一年となっていた。牛肉を食べるなど、徳川幕府の時代には考えられないことだった。
木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通の維新三傑は、西南戦争の前後に相次いで死んだ。公家の岩倉具視も、帝国大学の御雇い外国人医師ベルツに看取られ、五年前に癌で亡くなった。明治維新もすでに遠くなり、人々の記憶からも忘れられかけていたのだ。
「生き残っているのは、三条実美公だけになってしまったな……」
しんみりとしながら、大御門が牛肉を頬張った。万条は夢中で食欲を満たしつつ、主役の森のことなど、すっかり忘れたように尋ねた。