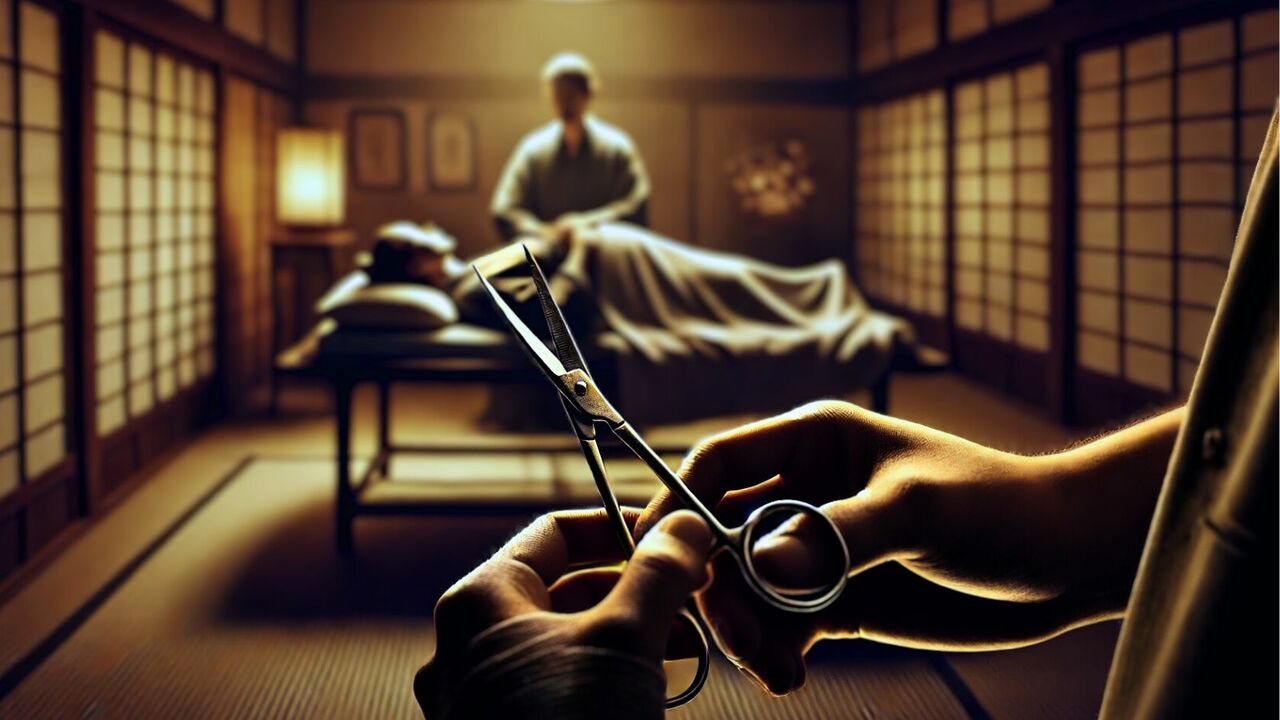「それで三条公は、相変わらずお元気なのか?」
「ああ、ますますお盛んだ。来年の憲法発布にも、並々ならぬ意欲を示しているらしい」
「でも、あの三条公が、あそこまで偉くなるとはなぁ……」
万条が嫌みったらしく言った。
「まったくだ」と、大御門も苦笑いしながら同意した。
実は、二人は京都の公家の生まれで、幼なじみだった。
三条公とは子供の頃、御所の近くの屋敷でよく遊んでもらったのだ。今はともに、医者として働いているが、大御門はかつて東京医学校と呼ばれていた、帝国大学医学部の出身だった。森の先輩にあたり、ドイツ留学から帰国すると、母校で教鞭をとっていた。
一方、万条は京都にある府立療病院の医学校出身だった。卒業してからは、全国の医学校を転々とした後、二年ほど前に母校へ舞い戻っていた。この夜は急遽、万条が森の祝宴に加わることとなったのだが、お互い久し振りの再会でもあった。
そして森をそっちのけにして、ひとしきり三条公の思い出話に花を咲かせていると、二本目の酒が運ばれてきたときだった。
「ところで、あの件は何とかならないか?」万条は突然、真剣な表情となり、大御門を上目遣いで見た。
「そうだな……」大御門は箸を止め、眉根を寄せた。
「子供の頃から、おまえは本当に無鉄砲だったからな。大人になっても、あまり変わってないようだ……」
ため息をつきながら、大御門は呆れた顔をした。それには万条自身も、思い当たることがあった。京都がまだ、維新の動乱に巻き込まれていない、のどかな頃だった。