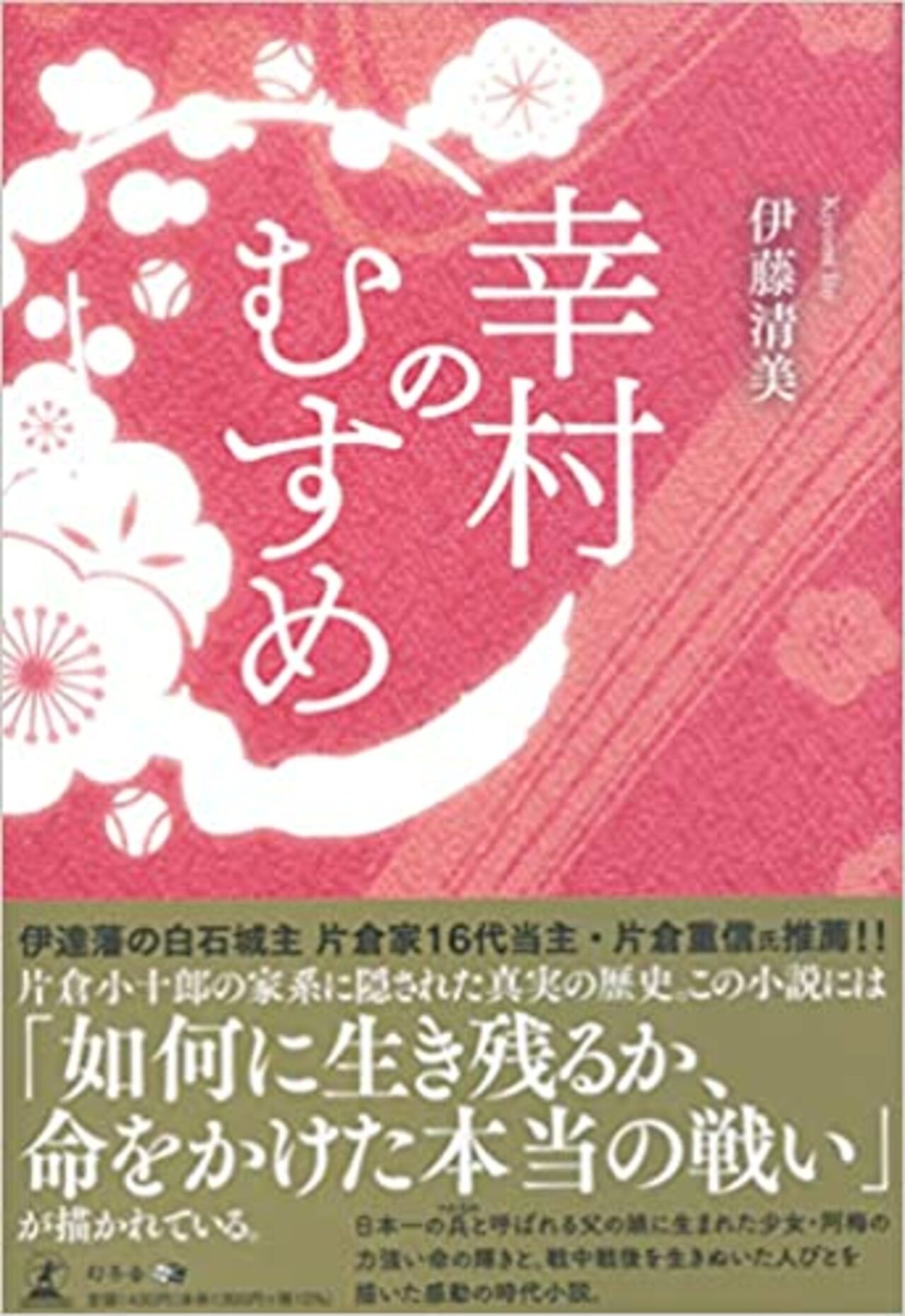ふと五十歳になられる伊達陸奥守さまのことが頭をよぎった。大掛かりな堀の開削を始めておられる。城の堀ではない。大量の木材を運搬するための堀だ。公方さまの江戸の街づくりにも息を呑むが、仙台のお城下も大変なものだ。
伊達陸奥守さまというお方は、不屈の心を持っておられる。
仙台は以前から幾度となく地震がつづいていた。そしてそれまでの揺れが前触れだったように、今から六年前の慶長十六(一六一一)年、未曽有の大地震と大津波が三陸沿岸を襲ったのだ。仙台の領内だけでも死者が二千人。三陸沿岸を含めてすべての死者は、五千人とも言われている。家屋は流され、押し寄せた海底の泥が田畑を覆いつくした。
伊達さまは、関ケ原合戦の翌年の、慶長六(一六〇一)年に居城を岩出山から仙台に移されていたのだった。十年の努力とその成果が地震で押しつぶされ、津波によって海の底へと押し流されていったのだ。
大津波から三年後、大坂冬の陣、翌年夏の陣と戦がつづいた。そして戦は終わったが、城や町の復旧はまだ途上である。片倉領からも応援を出しているが、海水と泥に埋まった田や畑に作物が実るようになるまで、これから何年かかるか思っただけでも気が滅入ることだ。
壊滅的な城下の再建のためには、木材が大量に必要だ。しかも急を要するのだ。その運搬のためには水路を利用する方が、道路を移動するよりもはるかに速い。そこで伊達さまが考えられたことは、阿武隈川(あぶくまがわ)と名取川(なとりがわ)を結んで運河を開削することだった。そしてその大事業が始まっているのだ。
丸森(まるもり)や角田(かくだ)方面から切り出された木材は阿武隈川を下り、開削された木曳堀(きびきぼり)と称される運河に導かれて、名取川河口の閖上(ゆりあげ)に至る。木材はそこから名取川を遡上し、仙台の南材木町(みなみざいもくちょう)まで運ばれるという。
遠大な事業だ。津波で田畑を奪われた民百姓が、復旧工事と開削事業に人足として動員され、日当が支払われている。その事業がなければ今のいま百姓たちは、糊口(ここう)をしのぐこともかなわぬであろう。
それを考えているうちに、身内に熱い血が巡ってくるような心地がした。来たぞ、来た、来た、熱い血が寄せて来たぞ。
うんっ、と声をあげて儂は思いっきり両腕を高く突き上げてみた。儂を窺っていたらしい者がほっとしたように顔を見合わせていた。
【前回の記事を読む】「油をつかわないそうめん」を特産に?悩む片倉重長にお方の提案