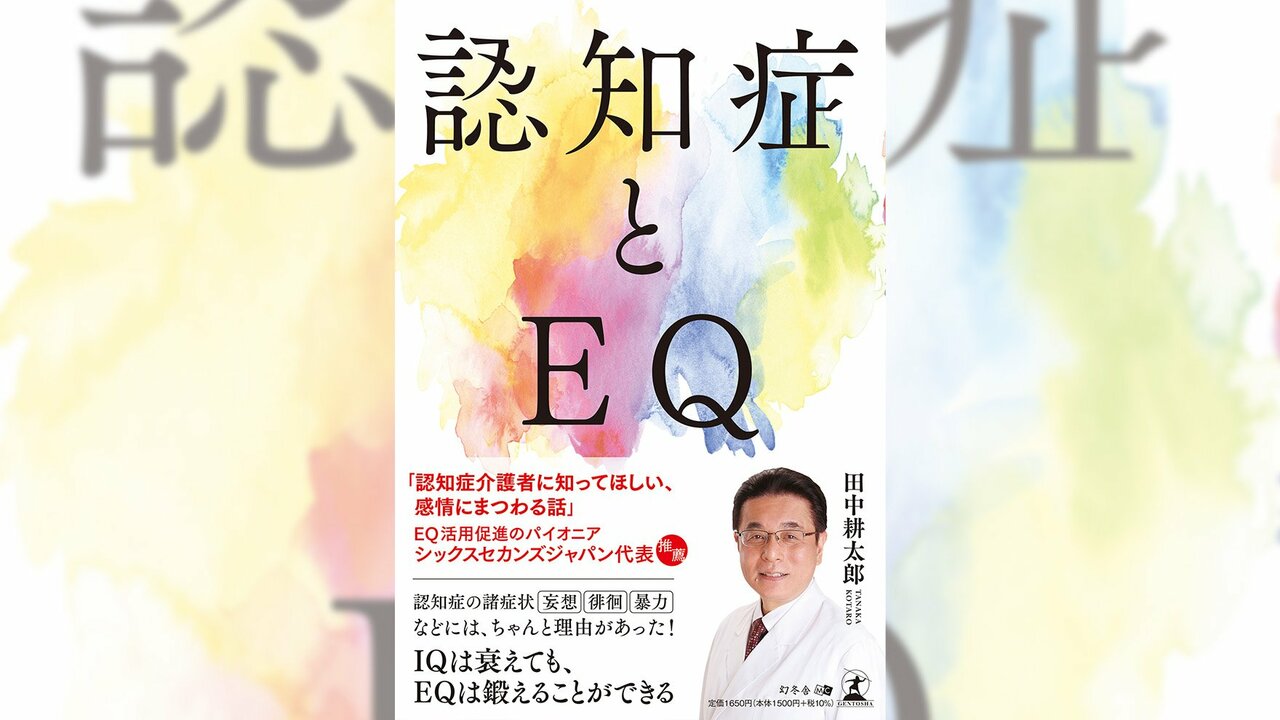まえがき
通所介護や訪問介護、訪問看護の方々と一緒に仕事をしながら、介護困難となり自宅での生活ができなくなった方々のために最終的には老人ホームの経営にも乗り出しました。
そんな診療の日々の中で、出会うようになったのが認知症の患者の方々です。
私が子どもの頃、認知症はとてもひどい病気なので、将来医者になってもできたら関わりたくないと思っていました。
その頃は「痴呆」と言われていましたが、特に症状の激しいおじいちゃんが近所にいて、父や母を通して徘徊や夜間の暴言などの激しい症状について噂話を聞いていました。その影響もあって子どもながらに認知症は大変な病気だというイメージを強く持ってしまっていたのです。
医師免許を取ったばかりの頃、最初に関わった認知症の患者さん達は精神科病棟に入っている方々でした。つなぎのようなファスナー付きの病衣を着て、勝手に服を脱げないようにされていました。
そしてロの字の構造をしている閉鎖病棟の中で一日中、終わりのない散歩を続けていました。意思疎通はあまりできず、ただただ一日を過ごし、予想できないタイミングで叫んだり歩いたりされているように私には見えました。
そのような方々が発熱したり転んでケガをしたり、嘔吐されたりした時に内科的な処置をするのが私の仕事だったのですが、入院されている重症の方ばかり最初に診ましたので、外来や自宅で実際に自分がそのような方々の診療をすることになるとはとても想像できませんでした。
ところが開業後、在宅医療や介護職との連携を通して出会うようになった認知症の患者さん達は、それまでの私が持っていたイメージとは違う姿をしていたのです。
自宅で生活されている患者さんには生活感がありました。認知症ではあるのですが生活されているので、一見病人には見えません。そういう患者さん達と接することを通して、患者とそうでない人との境目が本当は存在しないことが自然に理解できました。
日々の診療を通して「誰でも認知症になる」ということが心の底から理解でき、そして高齢者の生活に寄り添うということは、この病気とつきあっていくことだと覚悟を決めさせられたのです。