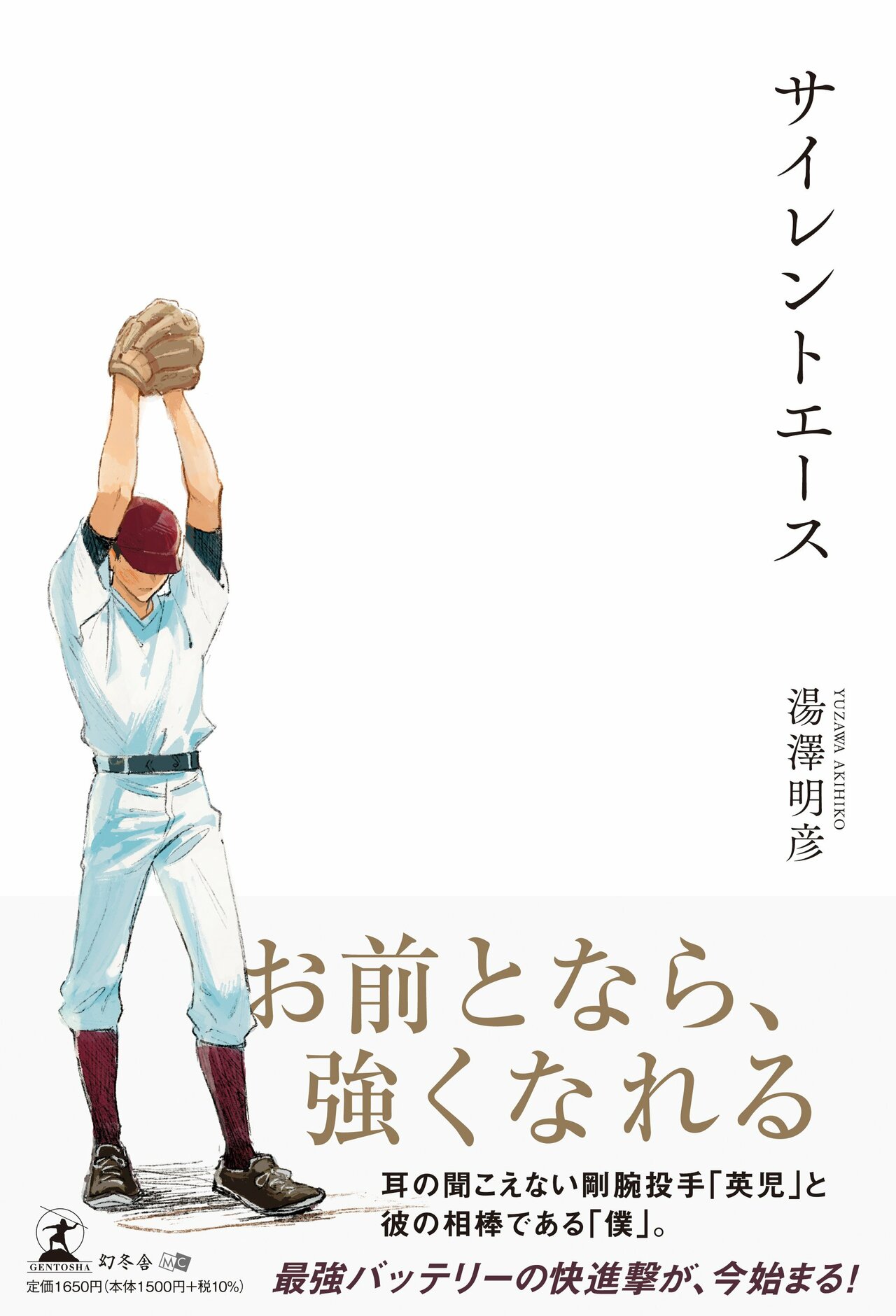けがでもさせたら、学校では責任が取れないからだ。そして英児はいつしか、町中で知らない者はいないピッチャーに成長していった。
実際、大人の草野球チームが彼に助っ人を頼んだとき小学生のボールをまともに打ち返すことがほとんど出来なかったのだ。来る日も来る日も多摩川の堤防を走り込んで身に着けた強靭な下半身によって培われた正確無比なコントロールも、英児の類稀なる武器の一つだった。
そのコントロールされたストレートを、野球好きな大人たちですらバットの芯に当てることはほとんど出来なかった。
彼の聾学校と僕が通っていた小学校で、たまたま野球チームの監督の先生が知人であるという縁から練習試合をすることになり、そこで初めて僕、湯浅太郎(ゆあさたろう)は沢村英児と出会った。
僕はというと地方公務員の一人息子で、住んでいた家も官舎だった。特段豊かでもなく、運動が出来たというわけでもない。野球は本当に何となく始めた。親戚のお兄さんがリトルリーグに所属しており、野球用具をお下がりで僕にくれたのがきっかけだった。
野球の道具はどれも値段が高く、市役所の総務課長だった父に買ってもらうには少々ハードルが高かった。せっかくお兄さんからもらった道具だから、と近所の草野球チームに入るところから野球に親しんでいった。
もらったのがキャッチャーミットと金属バットだったので、自動的に志望するポジションはキャッチャーになった。バットは宝物だったので、毎日素振りを近所の公園で繰り返しやっていた。