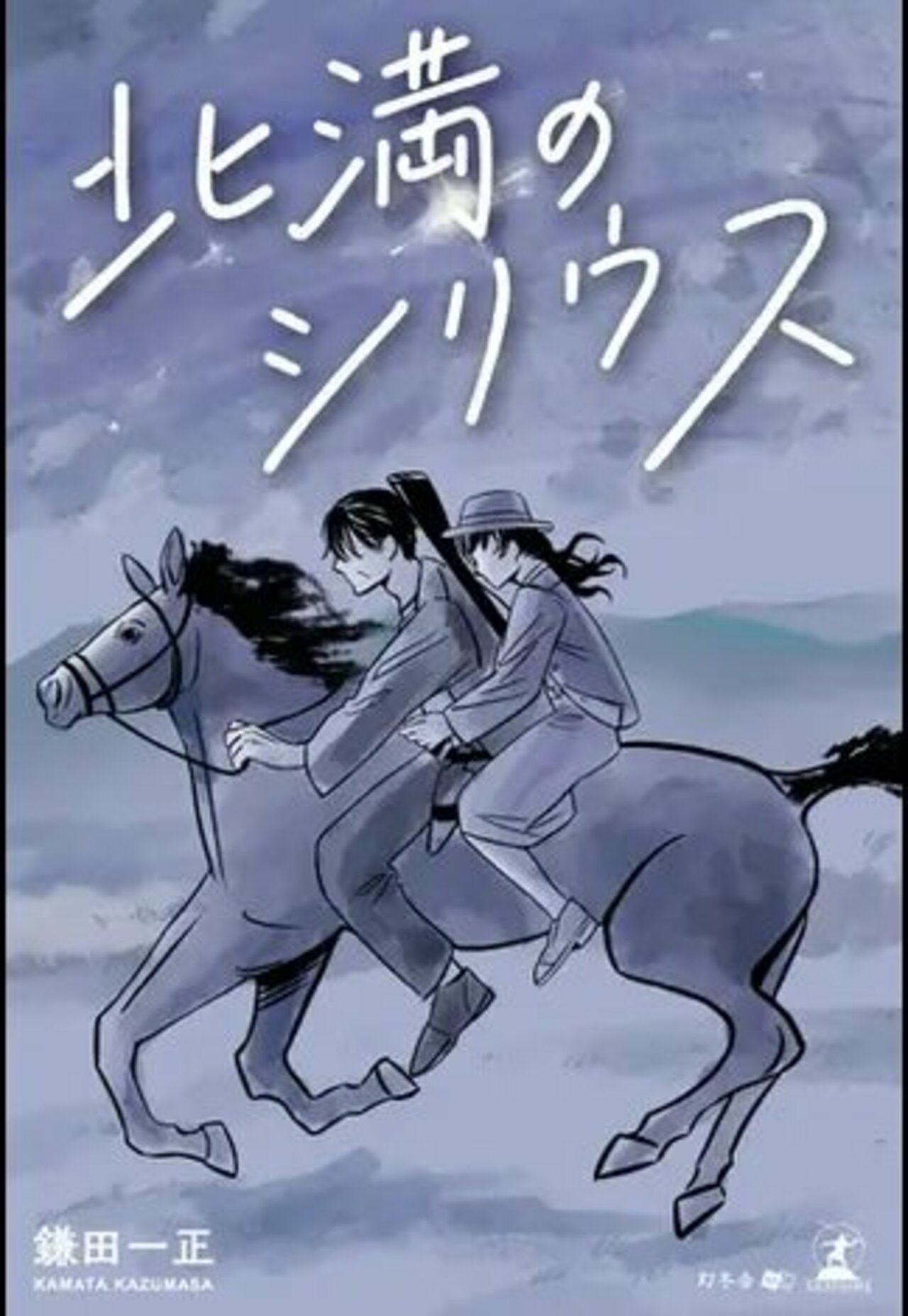ナツは、そのハルの顔に目を向けた。
「あれ、お姉ちゃん、お化粧は、し直さないの?」
「朝、一度、してあるからいいわよ」
「ダメよ、ダメよ。キタイスカヤなんて、いっぱい人がいるんだから、どんな素敵な男性と出会えるか、わからないのよ。いつでも、恋のきっかけがつかめるように、常に女としての自分を磨いとかなきゃ」
「いいのよ。出会いなんてないから」
ナツは、人差し指を立てた右手を振り上げた。
「ダメだなあ。三十八歳、まだまだ、あきらめるのは、はやいのだ!!」
「いちいち、三十八歳なんて、大声で言わないで!! それに、私、まだ、あきらめてなんかいません!!」
これには、ナツと茂夫が嬉しそうに顔を見合わせた。
「ところで、今日は、信雄さんは来ないの?」
「信雄さんなんか来ないわよ」
この、やりとりには、ベンチに座ったままの茂夫が反応した。
「信雄って、あの南満州鉄道に勤めておる鈴木信雄くんか? 彼が、どうしたんじゃ?」
ナツが、すかさず答えた。
「そう! あの鈴木信雄さん。シゲじい、知ってた? 実は、お姉ちゃん、信雄さんと付き合っているんだから」
「おお、そうじゃったのか? それは悪くない話じゃ!」
ハルが叫んだ。
「付き合ってなんかいないわよ! いい加減なこと言わないで! お父様が帰国する前に、熱心に勧めてきたから、一度お見合いしただけよ。でも、ピンと来なかったから、あの時、ちゃんとお断りしたはずなのに、その後、しつこいの」
ナツが、いたずらっぽい表情になった。