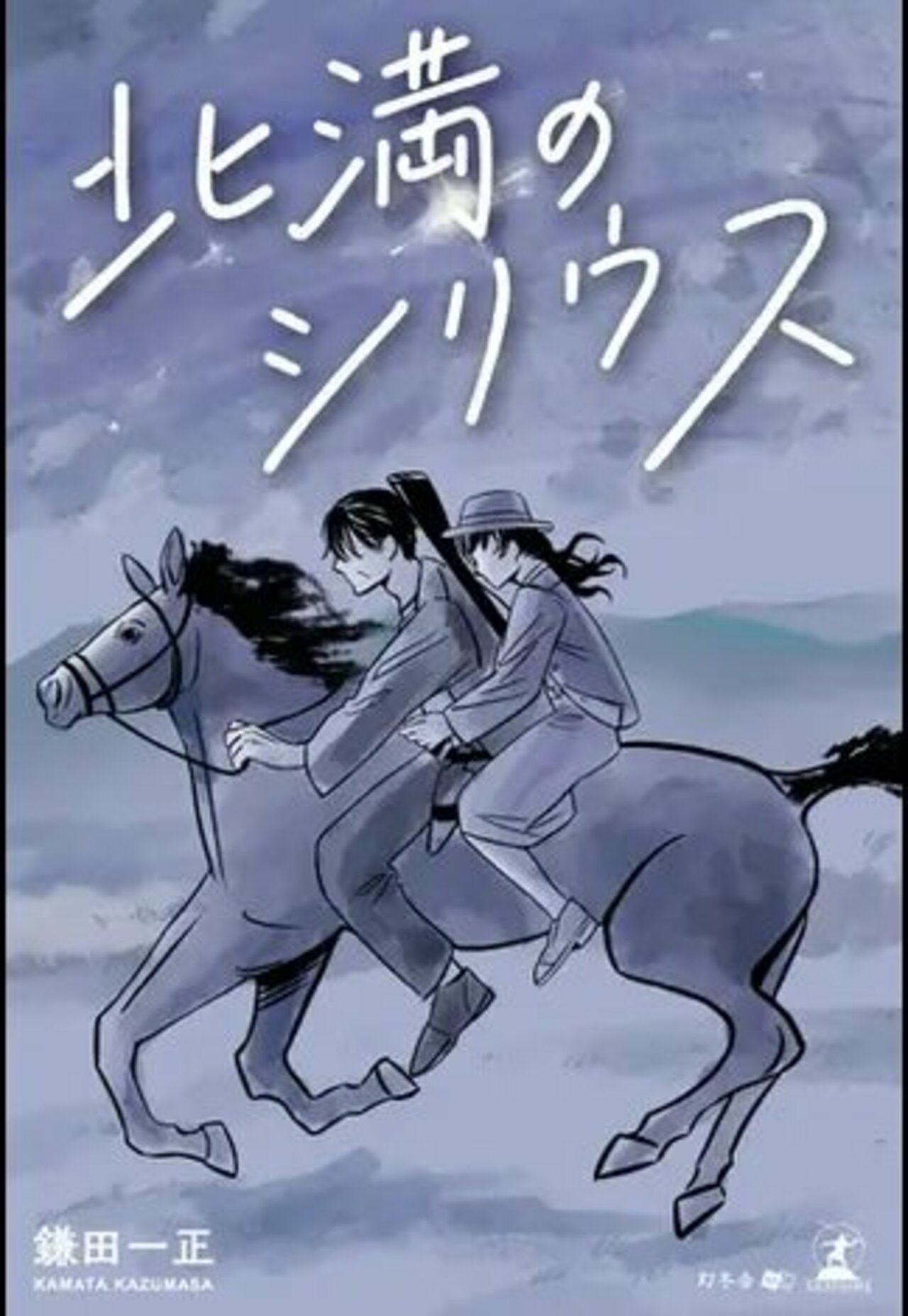だが、無邪気なナツは、自分こそが男性にとっての究極的に理想の女性なのだと、何を根拠にか、信じて疑わなかった。恋の苦さを知らないというのもあるのだろう。十七歳のパワーは、無限なのだ。二人とも異性から恋愛感情を持たれるよりは、飾らない性格も手伝って、同性から好感をもたれるタイプだと言っていい。
「シゲじい! 今日、私達、キタイスカヤのほうに行くのよ!!」
「ハルさんから聞いたわい」
ナツは、シゲオの返答を特に聞いていないようだった。
「う~ん、石頭道街まで行って、名古屋ホテルのグリルで久々に日本料理の焼き魚定食を食べるか、それともキタイスカヤのモデルンホテルでロシア料理を食べるか……。こりゃ、難問ねえ……。ねえ、お姉ちゃん! どっちがいい!?」
奥の部屋から、ハルが返事をした。
「う~ん、今日は、あっさりめのものがいいな。日本食がいいわね」
「アキオは、どっちがいい?」
「う~ん。僕も焼き魚とみそ汁がいいなあ」
「フユは?」
「フユは、チョコレートが食べたい!」
「よ~し、じゃあ、ロシア料理に決定!!」
奥から、ハルの声が響いた。
「何よ! みんなに聞いた意味がないじゃない!!」
「だってえ、チューリンデパートでお買い物をして、その後、モデルンホテルでお食事をして、最後は、マルスでチョコレートとケーキだなんて、最高に素敵な流れでしょう? それに、どれも近くにあるから歩き回らなくてすむしねえ。そう、そう、ついでにモデルン劇場で映画鑑賞なんてどうかしら? 今、何を上映しているのかなあ」
ハルは、着替えを済ませて出て来た。
「全くう!!」