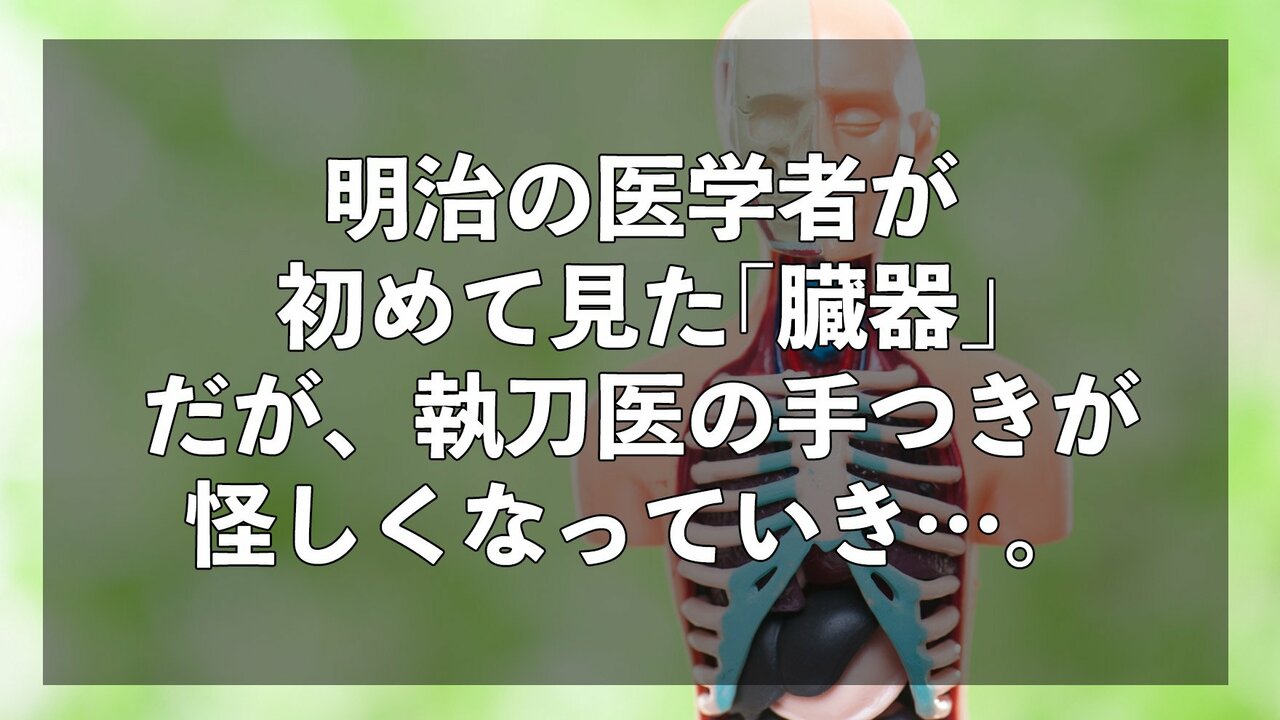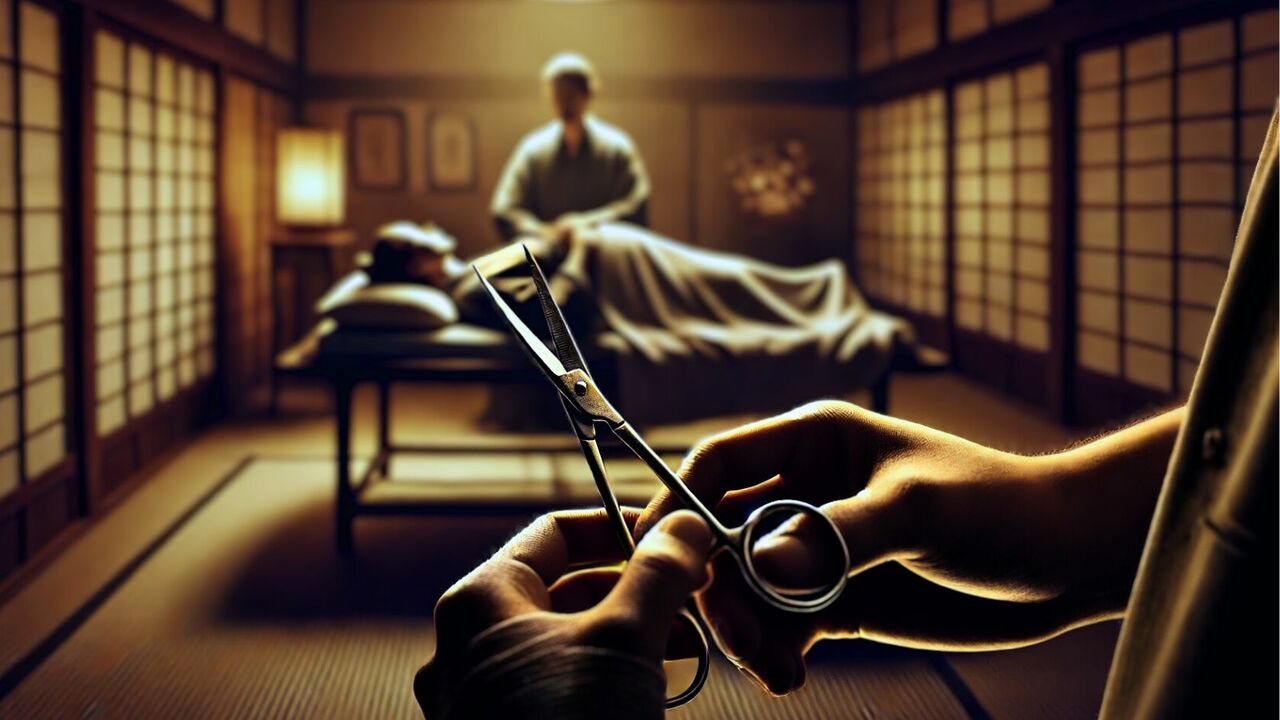第一章
二
間もなく腹の内部が露わになり、執刀医が中に手を突っ込んだ。そして細長い管のようなものを引っ張り出してきた。
「これが、十二指腸──」
横から別の蘭方医が、書物を片手に大きな声で言った。
十二指腸の上には、やや太い胃が連なっていた。下に行くと小腸で、さらにその先は大腸と呼ぶようになるとのことだった。それらに接するように、肝臓と命名されている大きな塊があった。
やがて執刀医が、悪戦苦闘の末に肝臓を摘出し終えたときだった。
「すごいな……」と、万条が思わず呟いた。
「ほんまやな……」
安妙寺は瞬きもせずに、その光景に見入っていた。
腹の内部が想像以上に複雑だとわかり、蘭方医たちはみな、すっかり度肝を抜かれた様子だった。念仏を唱えている者さえいて、解剖は次に、胸部へと移っていった。
肋骨が外され、風船のように膨らんだ二つの肺が露出してきた。その間には、卵のような形をした、赤い心臓が姿を覗かせていた。
冬にもかかわらず、執刀医の額には玉のように汗が滴っていた。それを補助する者たちも、同様だった。
ところが、解剖が首のあたりまで達した頃からだった。
しだいに万条は、違和感を覚えるようになってきたのだ。執刀医の手つきが、明らかに怪しかったからだ。
さほど手慣れたようには見えず、どこかおどおどしている態度だった。また町医者たちの質問にも、きちんと答えられないことが多かった。
やがて猿の解剖は、中途半端にバラバラとなった時点で、突如終了が宣告された。手足は皮を剥いだところで終わっており、首から上は手つかずのままだった。
「やったこと、あんのかなぁ……」
執刀医が後片付けを始めたとき、安妙寺が首を捻った。すでに陽は傾いており、町医者たちも、解剖所を後にしようとしていた。
「うーん……」と、万条も頷いた。
確かに自分もそう感じたからだが、安妙寺は執刀医を、疑り深そうな目で見た。そして、「ちょっと訊いてくる」と、走り寄って行った。
しばらくして戻ってくると、がっかりした顔で言った。
「やっぱりや」