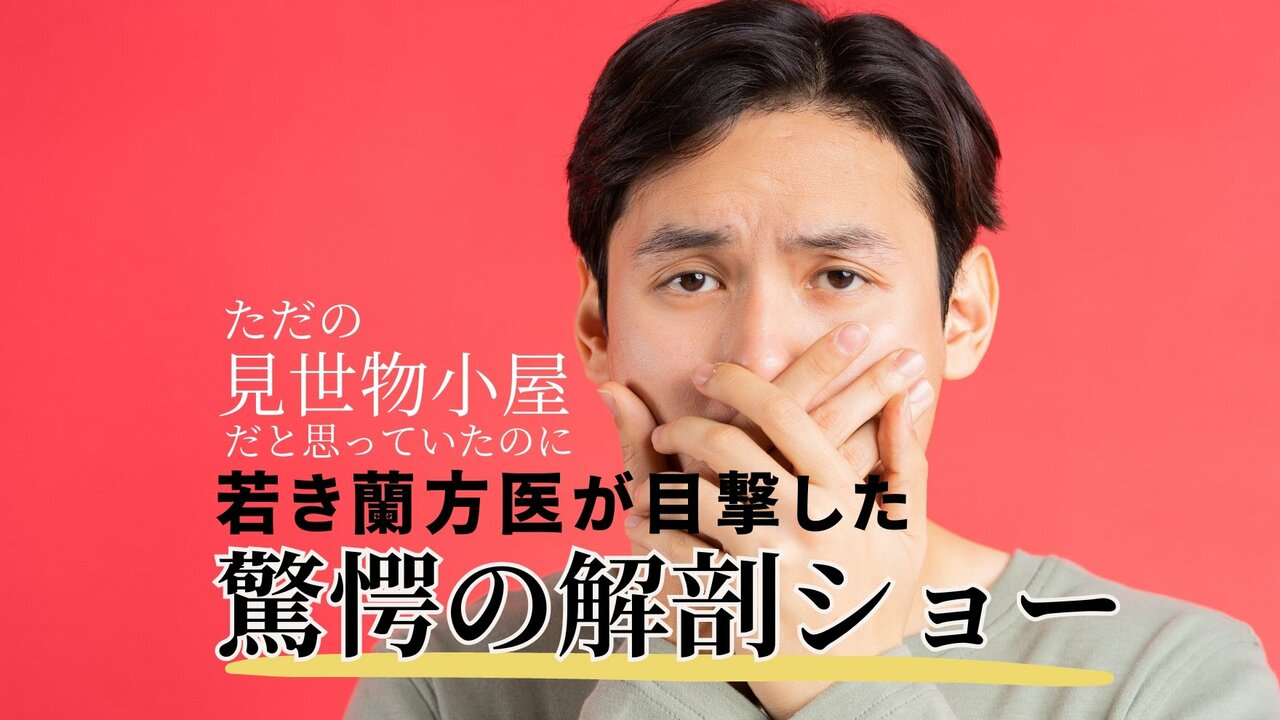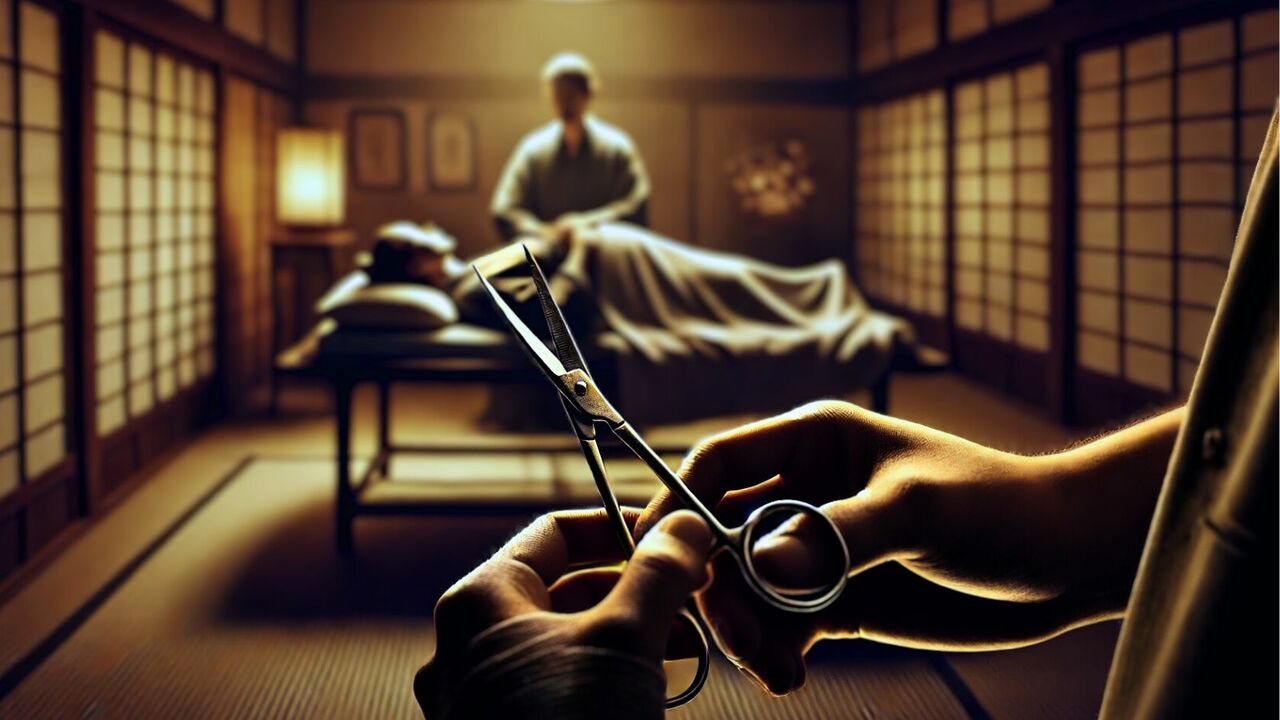第一章
一
「おう、万条──」
振り返れば、そこにいたのは幼なじみの安妙寺一久だった。ここに来るよう、自分をそそのかした張本人だ。
「やっぱり来たんやな」
「どうせヒマだったしな。でもこれが、お前の言う見世物小屋なのか?」
「その通りや」
安妙寺がにやりと笑った。だが急に、うんざりした表情となった。
「相変わらずおまえは、関東の言葉が抜けへんな……」
「そうかぁ?」
万条は首を捻った。すぐには納得がいかなかったからだ。とはいえ、万条がかつて親元を離れ、関東で暮らしていたのも事実だった。
公家の嫡男である万条は、十歳のときから三年間、徳川家康ゆかりの日光山輪王寺と、江戸の上野寛永寺で修行をしていたのだ。宮門跡の一つ、上野東叡山寛永寺の貫主のお供をするよう、父から命じられたためだった。
門跡とは、皇族や公家が住職を務める特定の寺院のことだ。そのうち、宮門跡の門主は皇族が就任することになっており、輪王寺はその一つだった。表向きは、行儀見習いと学問修業のためだった。しかし無鉄砲な性格を直すため、父が強制したのが実情だった。その間に、万条は江戸言葉が身に染みついてしまったらしい。
また、そんな門跡寺院の坊官の家系だったのが、安妙寺だった。坊官は貴族の端くれであるものの、御所の清涼殿には昇殿できない『地下』の官人だ。それが明治二年の『百官の廃止』で、職位を失ってしまう。しかも昨年の明治四年に門跡制度が廃止され、坊官は貴族でも僧侶でもなくなっていた。
さらに、新政府は廃仏毀釈の方針を打ち出し、京都でもその影響は無視できなくなっていた。安妙寺も寺を追い出されそうになり、ここのところ冴えない顔をしていたのだ。
それに対し、万条は堂上公家のうち、羽林家の出身だった。堂上とは『地下』に対する言葉で、清涼殿に上がれる家格の高い公家のことだ。
最上級が摂政と関白になれる近衛・九条・二条・一条・鷹司の摂関家五家で、次いで精華家と大臣家があった。万条家はその下の羽林家に属し、名家と半家よりは高位だった。
家格でいえば、中くらいの公家だった。しかし御蔵米は、たったの五十石しかなかった。典型的な貧乏公家で、維新のさいに天皇の東下に付き従うことも叶わなかった。
代わりに京都御所の留守居役を命じられた形となり、万条家は京都に残らざるを得なかった。
天皇あっての公家なのに、その側にいられないのは致命的だった。やむをえず万条の父は、和歌や茶道の教授で糊口を凌ぐことにした。その裏では、祇園のお茶屋に無心したり、屋敷を賭場として博徒に貸したりしていた。
お陰で万条は、比較的不自由なく暮らすことができた。生きて行くには清濁併せ呑むほかなく、そんな父の苦労を、万条は恩にも感じていたのだ。