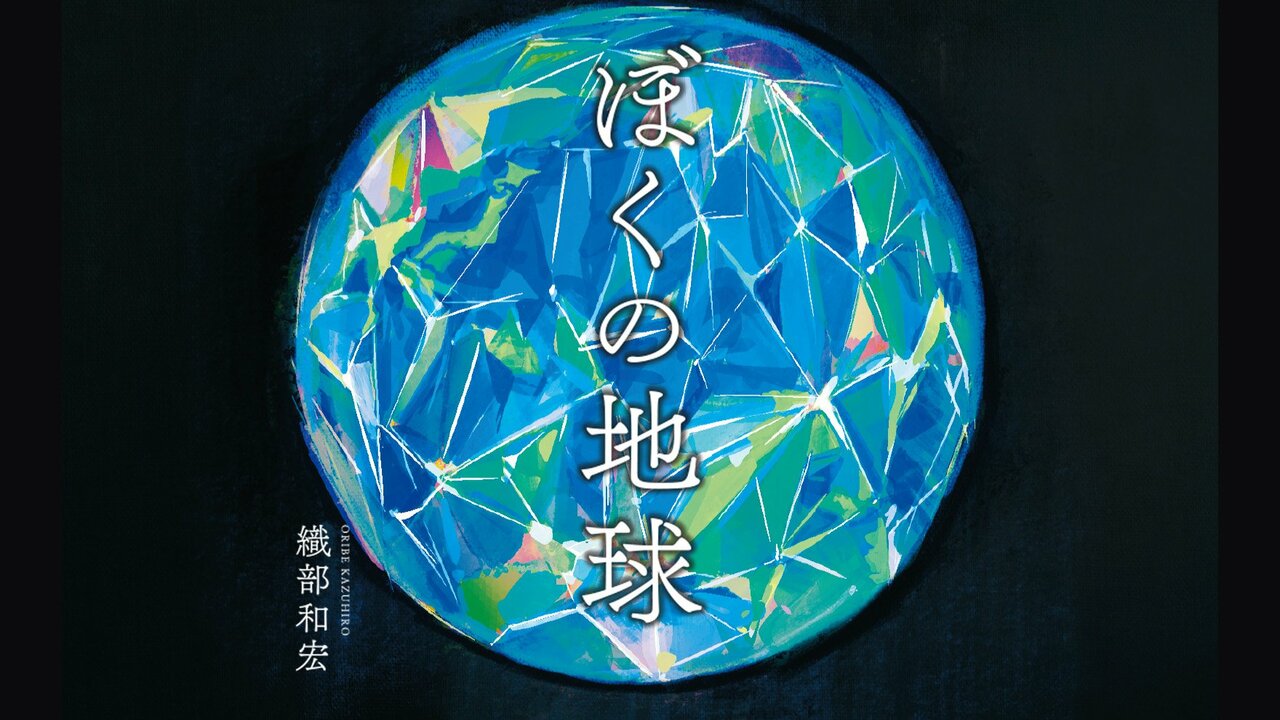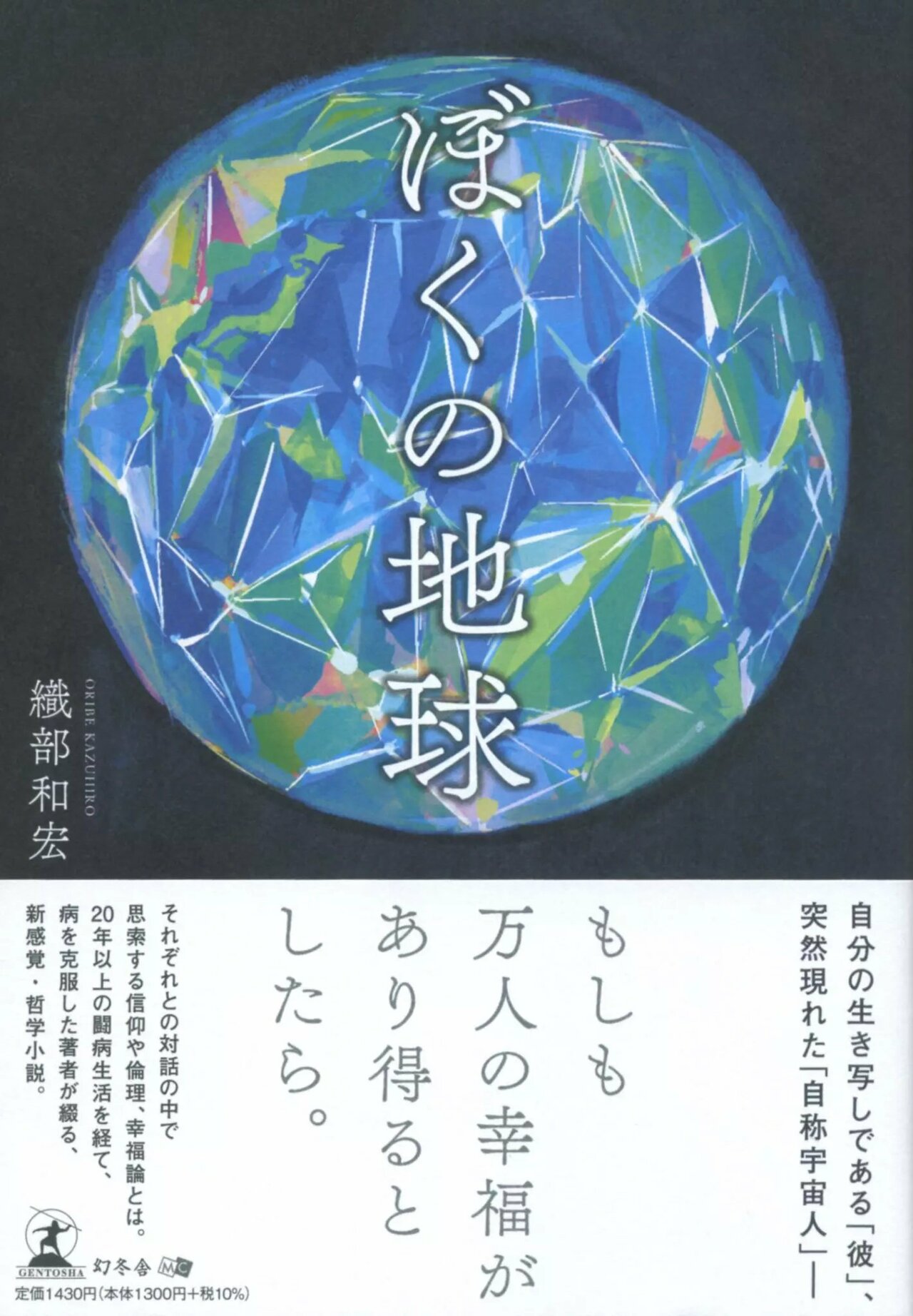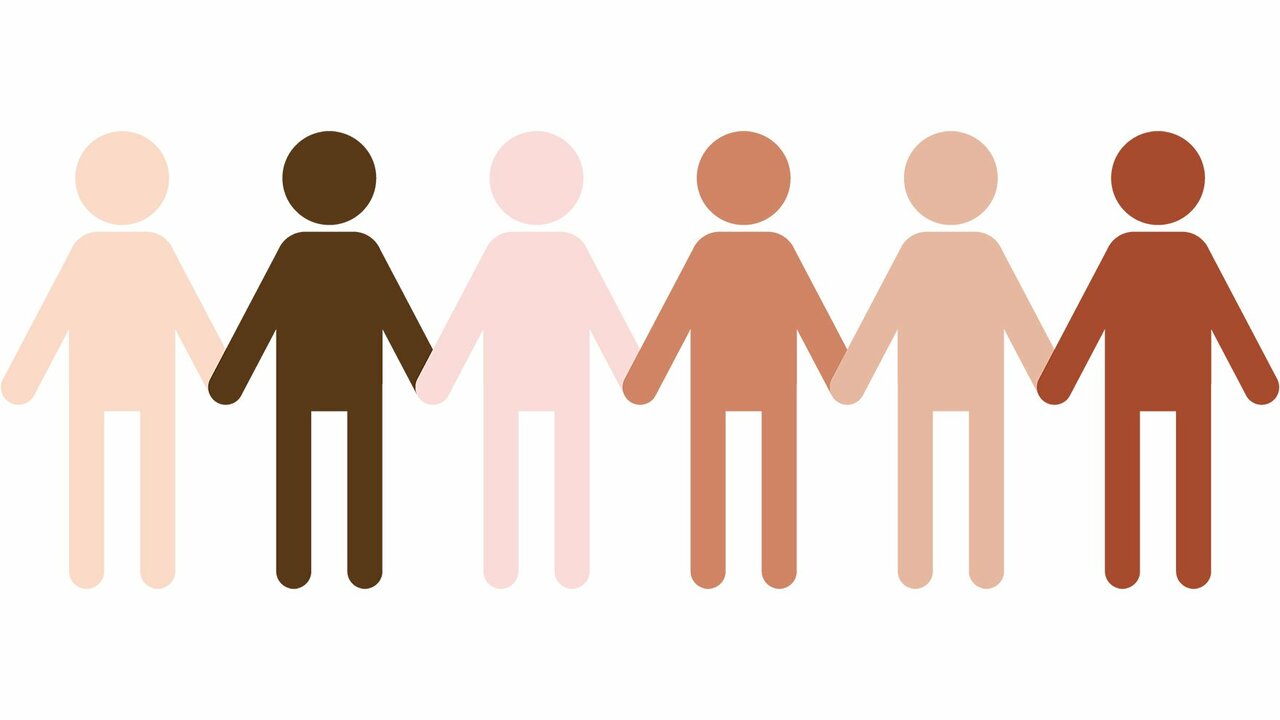ぼくの地球
第一章 目覚め 春
「何を」ではなく「如何に」
このフリーズには、一般的に見て出自またはその属性が異質であると判断されたすべての青春の特殊性も、同様に含まれることとなる。克服されなければならない過去は、時に個の感覚を先鋭化し、またその行動を協調性のないものへと変化させる。
彼もきっとそうであったに違いない。私たちは、しばしば精神面において攻撃的だったのだ。存在のための負は、個性がその終着点を見出せないうちは、容易に迷走する。
さらに、経験不足故のハードランディングがそれに追い打ちをかける。なるほど、平均的な個性であったとしても、青春とは暗闇の迷路を駆け抜けるが如く、である。彼と私の場合は、そこに輪をかけてということだったのであろう。
彼はこう言ったことがある。
─「克服する」と「取り戻す」は似ている。そこでは「逸脱する」が共有されているのだ、と。
「逸脱する」とは何とも苦々しい表現だ。だが、本来個性がその本領を発揮できる場を探すのが青春時代なのだ、と仮定できるのであれば、この「逸脱する」は、むしろ肯定的に見做されなければならない表現のはずだ。
しかし現実には、一度逸脱すると、容易にはかつてを取り戻すことはできない。そこには、まさかと思えるほどの時間が横たわっているのであり、彼も、今後その足枷から逃れるのに、かなりてこずることになるのであろう。私は彼にこう返すべきだったのかもしれない。
人生はあまりにも短く、克服を達成した時には、もう薄暮であると。
暗闇が迫りくる中、ようやくほんとうの人生が始まる。だが克服すべき過去に苛まれた者にとって、それは何ら不思議なことではない。損得の境界線を流れる狭いグレーゾーンから負の方に転げ落ちないようにするためには、「異」を選択することは、そこに如何なる理由があろうとも許されないのだ。
ここには常識という名の高い壁がある。「異」の烙印を押された者は、その瞬間において、すでに異邦人となる。そしてそこから、果てしない単独紀行が記されていくこととなる。友人と呼ばれるためには、私たちは二人称で表されるべき対象とならなければならない。
だが私も彼も、十代において早くも三人称の対象として周囲に対処しなければならなかった。すでに記した私と彼の潜在的攻撃性は、このような環境の中でにもかかわらずアイデンティティーを放棄しようとしなかったことの結果であり、そのことは一方で、青春時代の個性が持つ洞察力を高めることになったが、しかしもう一方では、共有スペースの著しい減少により孤立感から生まれる焦燥感にも似た反協調性を育むことにもなった。