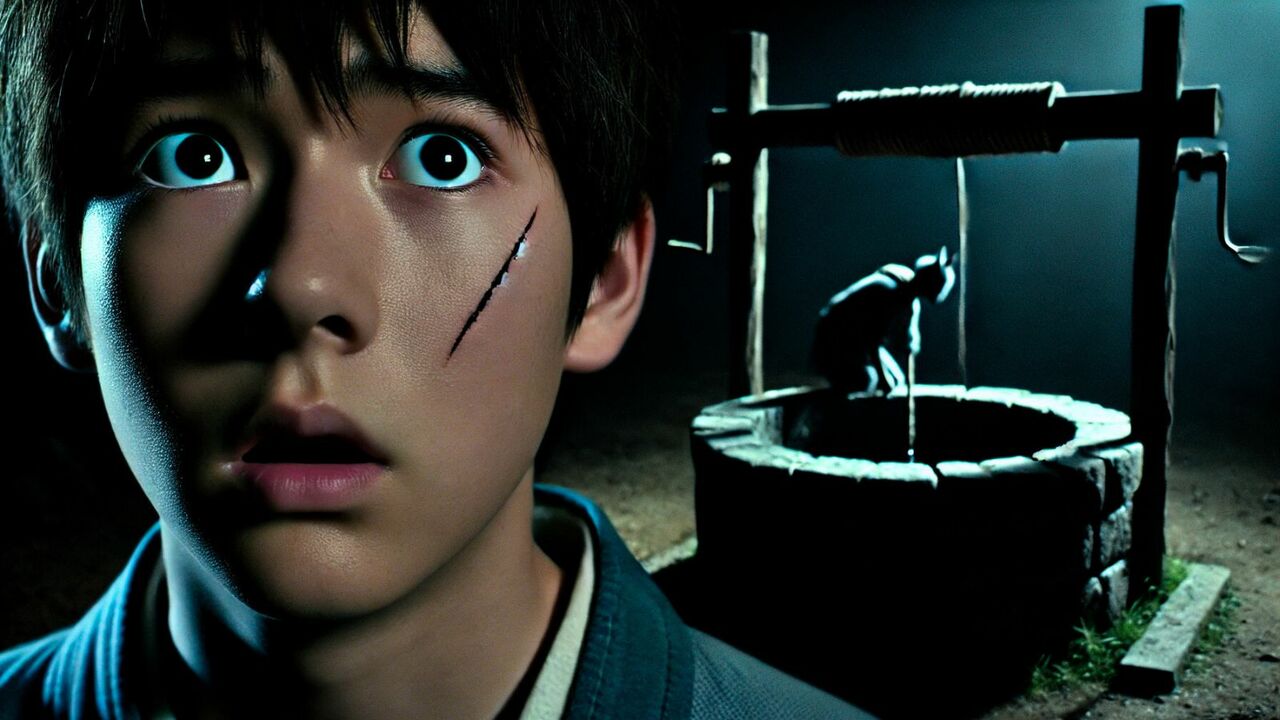「今川氏輝様も寿桂尼様の名で、かわた彦八という長吏小頭に皮革を調達せよとの命が、下ったようでございまする」
「という事は、武田は今川と一戦交える気か?」
「恐らくは……」
物流という物の流れを見るだけで、国の狙いや動きが垣間見える、という事を源五郎は学んだような気がした。
後に海道一の弓取りと名を馳せる今川義元の兄氏輝と、戦国最強の虎と恐れられた武田信玄の父信虎が、駿河を舞台に戦を始めようとしていたのである。
太田道灌の流れを汲む戦国の武士の血が熱くなるのを感じ、それを冷まそうとするかの如く聞いた。
「邪魔をしたな。また何か新しい情報があれば知りたい。またここに来てもよいか?」
「え~え~、いつでもお越しくださりませ」
血で血を洗う戦乱の波音が、元服前の源五郎の耳にも否応なしに聞こえ始めていた。
過ごしやすい初夏の夕暮れに、城を取り囲む大きな水堀の至るところから蛙の鳴き声が聞え、暮れなずむ地平線には燃え上がるような夕陽が広がっている。
岩付城に戻った源五郎は赤く染まる中庭で、つき丸に餌を与えながら考え込んでいた。
つき丸は居館の縁の下に板で囲い、藁を敷き詰め犬小屋とし、麻縄で首輪と首紐を作り、それを地面に打ち込んだ杭に結び付けてある。
自由にしてやりたかったが、仔犬の好奇心であらぬ所に入り込み、心無い人間に虐待や殺傷でもされぬように、目の届く身近に置く事にしたのだ。
源五郎は一心不乱に餌を食べているつき丸を見ながら、善右衛門の家で知った武田と今川の開戦の兆候と、それが太田家を含む関東の情勢に与える影響について考えていた。