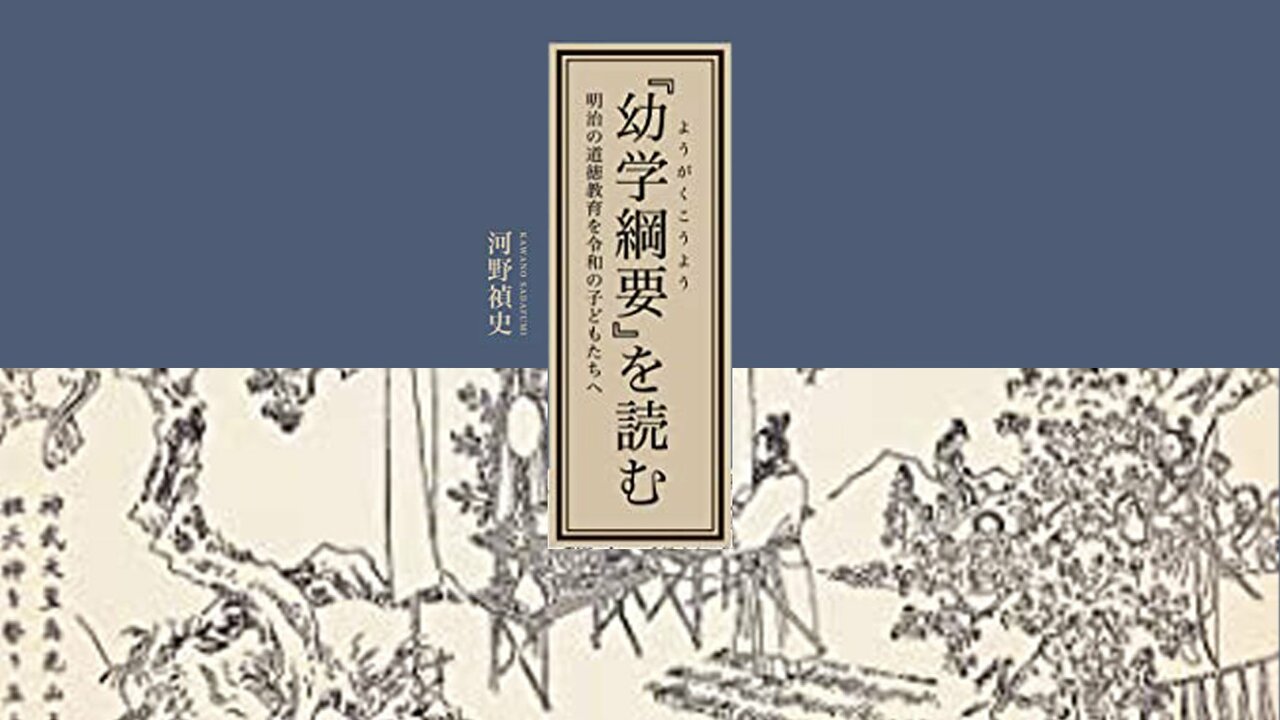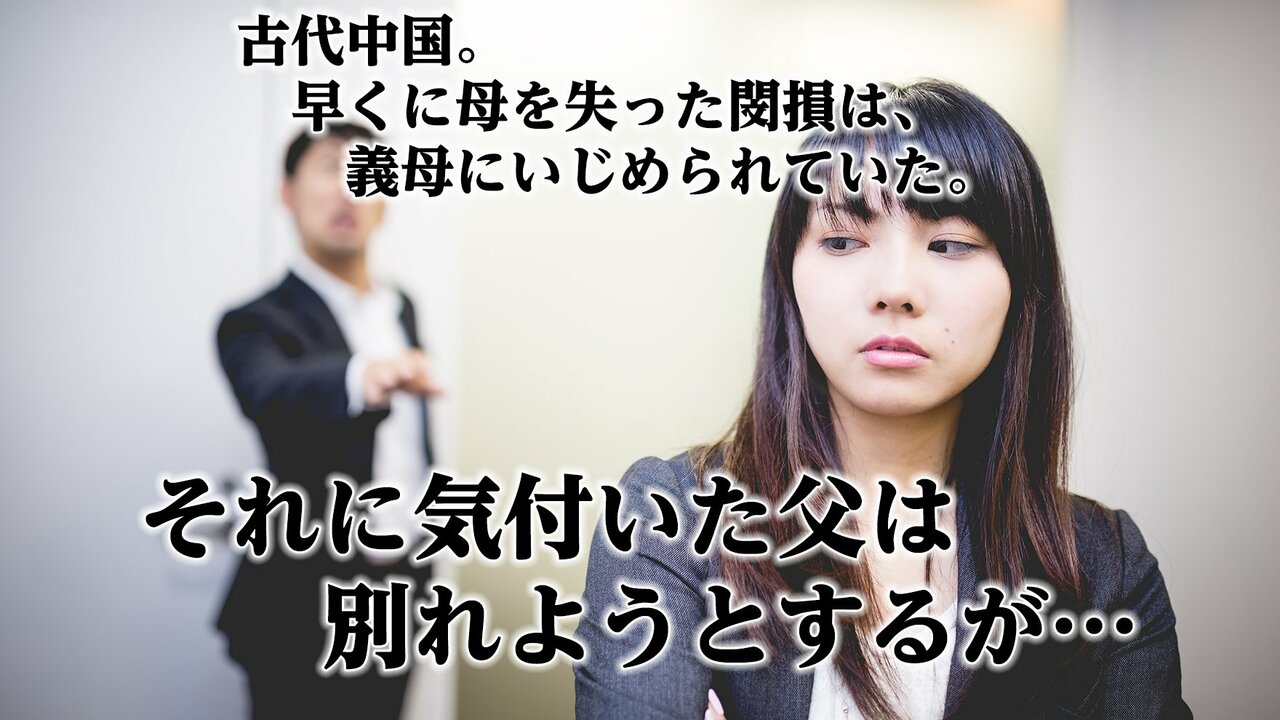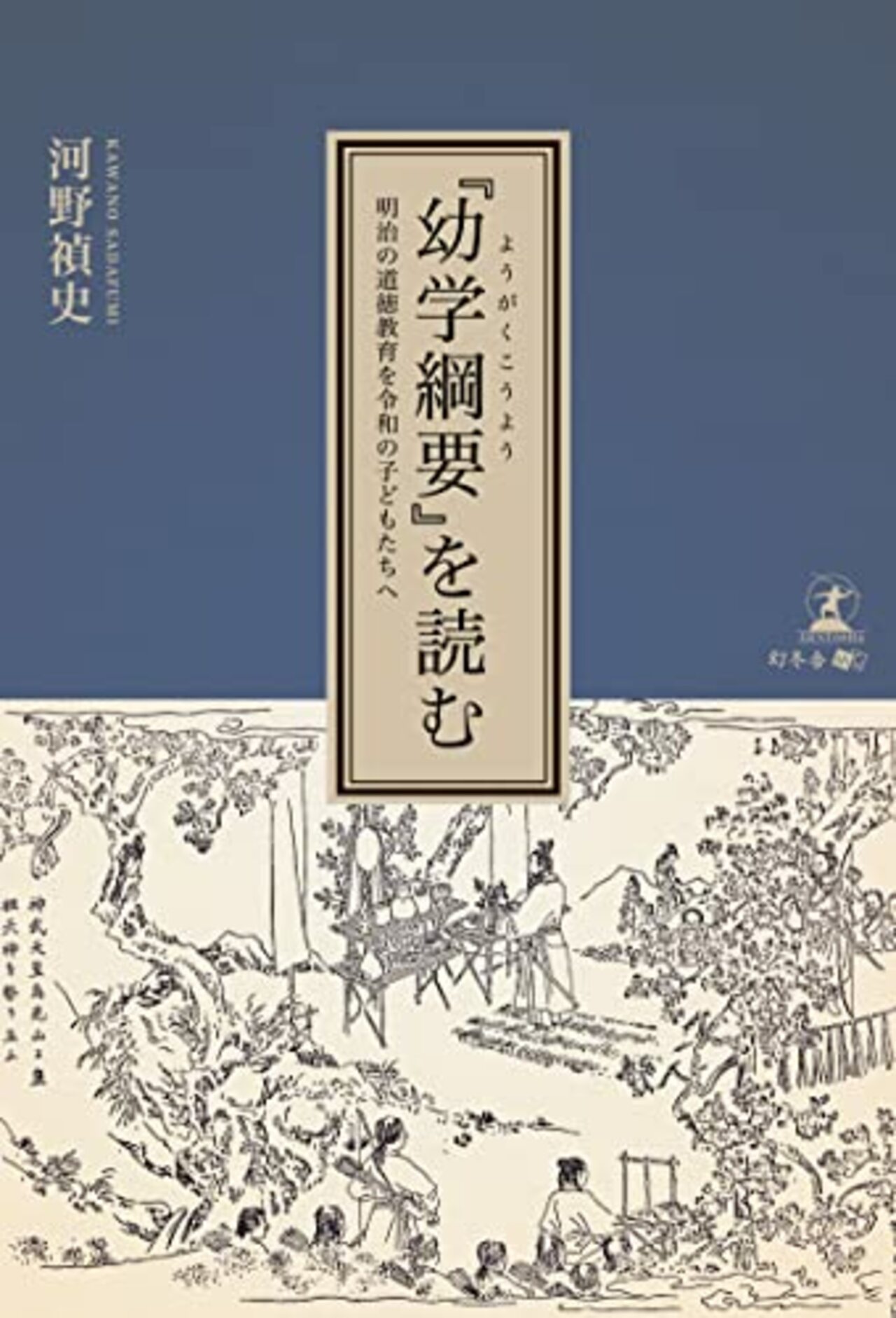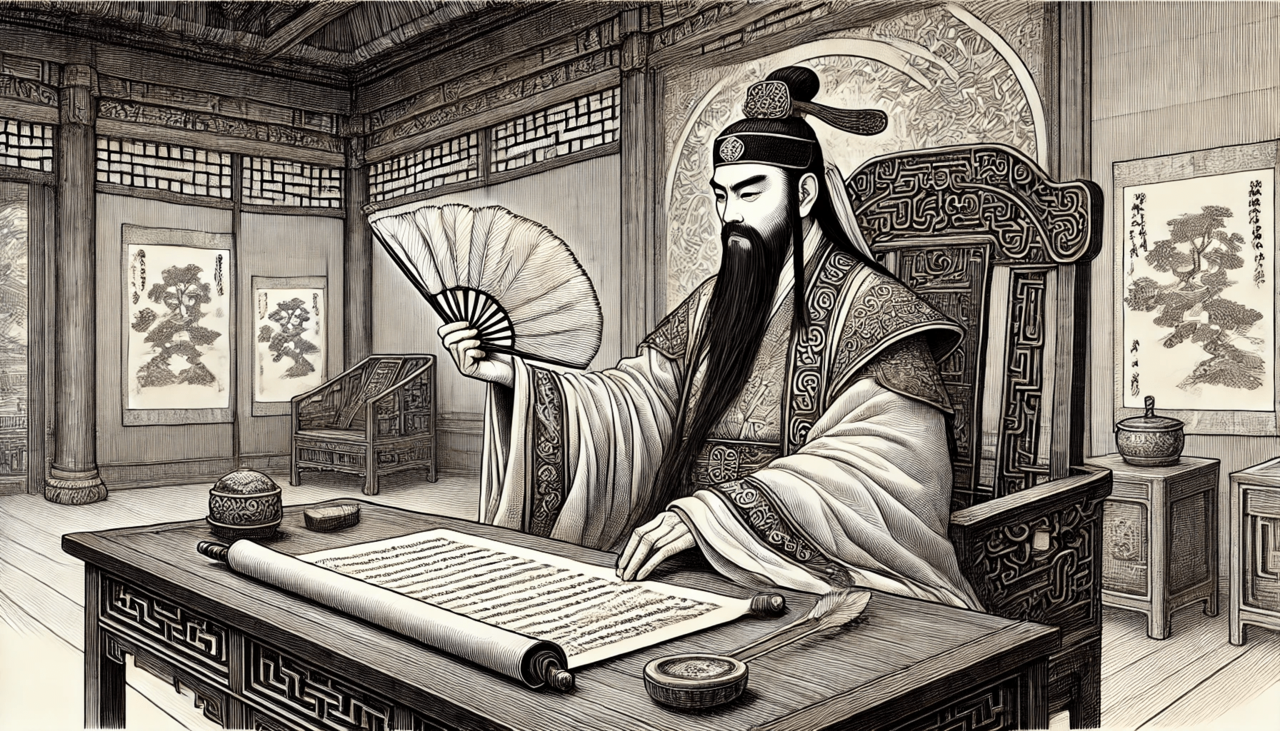早くに母を失った閔損は、義母にいじめられていた。それに気付いた父は別れようとするが…
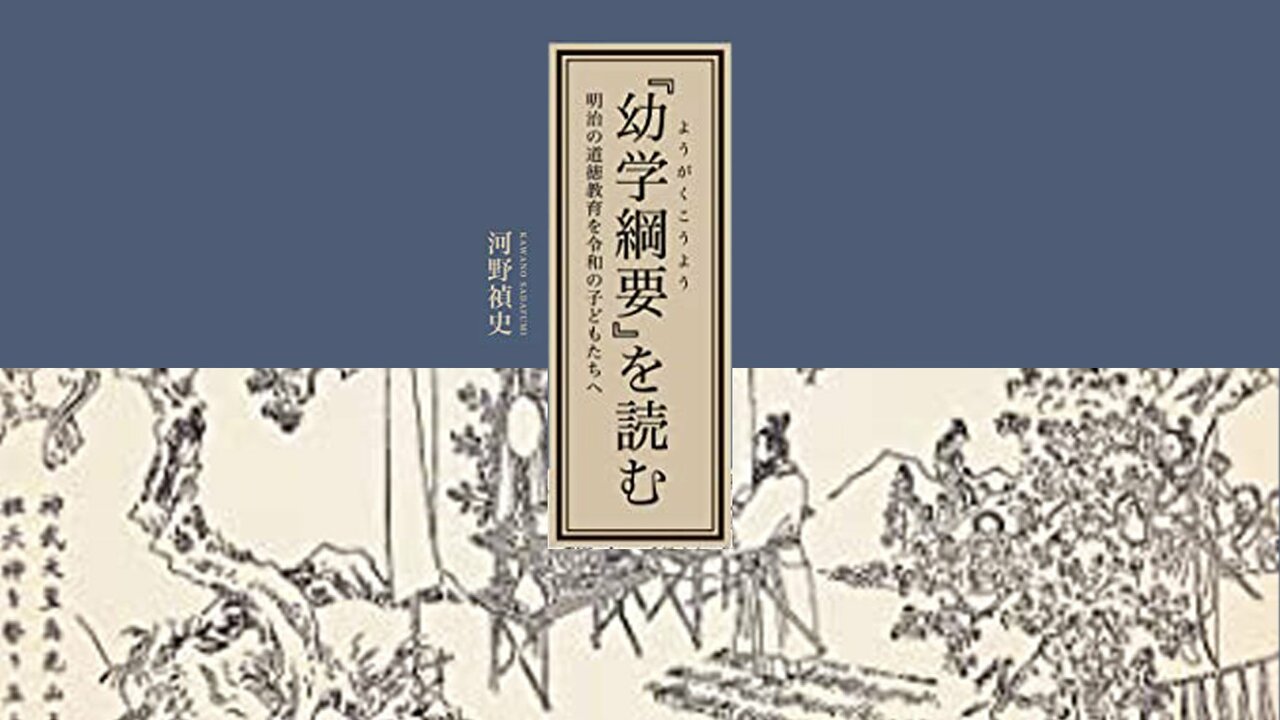
『幼学綱要』を読む
【第9回】
河野 禎史
日本の未来に危機感を抱き、「孝行」「友愛」「信義」など20の徳目から我が国と志那の偉人にまつわる逸話が記された、明治の子どもたちの学びのための書を現代語訳する
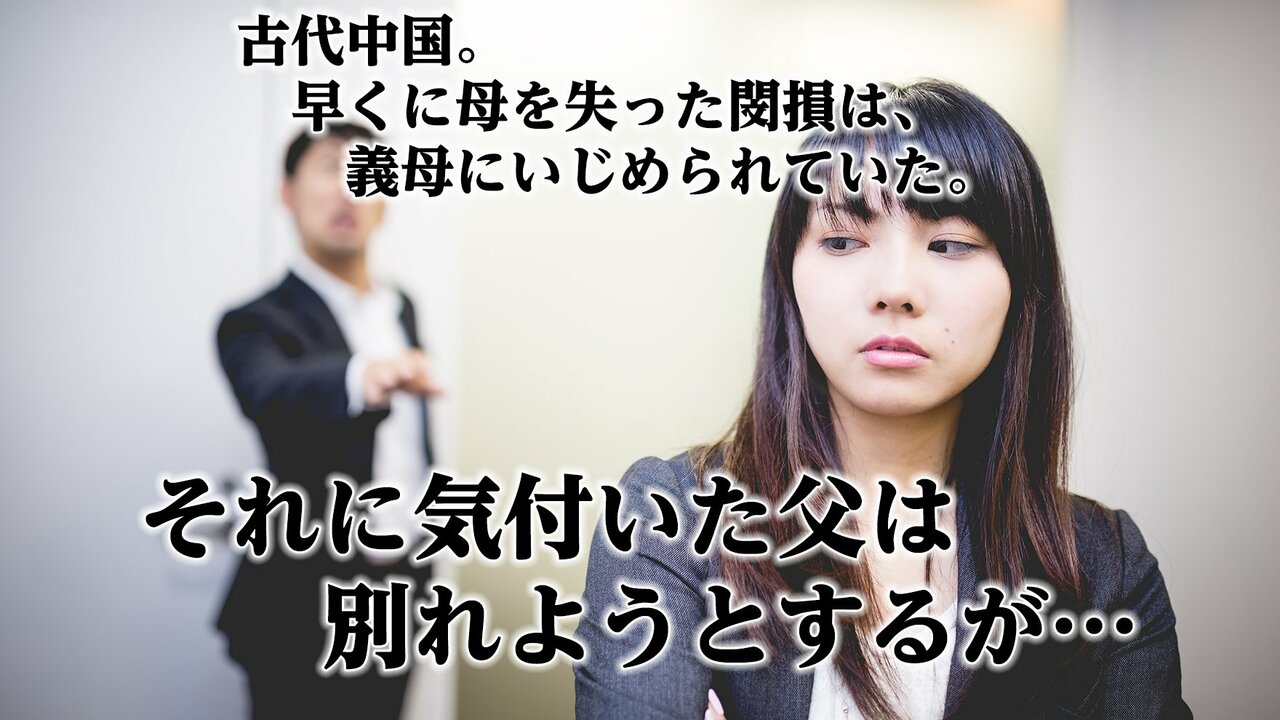
明治 15年(1882 年)、その勅命を受けた元田永孚によって編纂され、宮内省より頒布されたのが『幼学綱要(ようがくこうよう)』です。戦後以降の日本では『幼学綱要』について新たに解説された書籍はほぼ存在しておらず、いまではその存在を知る者も少なくなっています。本書は、そんな日本の未来に危機感を抱いた著者が執筆した『幼學綱要(原文)河野禎史注釈』(2021 年 マーケティング出版)を現代語訳したものです。※本記事は、河野禎史氏の書籍『「幼学綱要」を読む』(幻冬舎ルネッサンス)より、一部抜粋・編集したものです。
【前回の記事を読む】古代中国。再婚した父と義母は弟を愛し、舜を殺そうとしていた。そんな家族に彼がとった行動とは。
第一章
〇支那史
⑩二十四孝、説苑
【10】「閔損」
春秋時代(紀元前数百年前)の頃のお話です。
魯の国の閔損は早くに母を喪ってしまいました。
父は後妻を迎えてから、母は二人の子供を生みました。
その二人の子が着る服は暖かな綿が入っており、損が着る服は、いつも薄手の物です。
父が冬の寒い月の日に、損と馬車で出掛かけました。
損は体が寒えて車を引く綱を落として失くしてしまいました。父は、これを責めますが、損は何も言い訳をしません。
その後、父は、その理由に気付き、妻と別れることを望みました。
その時、損は父に言います。
「母がいれば一人の子が寒いだけです。もし、母が去れば三人の子が寒くなります」
父は、その言葉に心を打たれて別れることを止めました。
また、母も悔い改めてから三人の子に対して等しく接するようになり、ついには慈愛の深い母となりました。