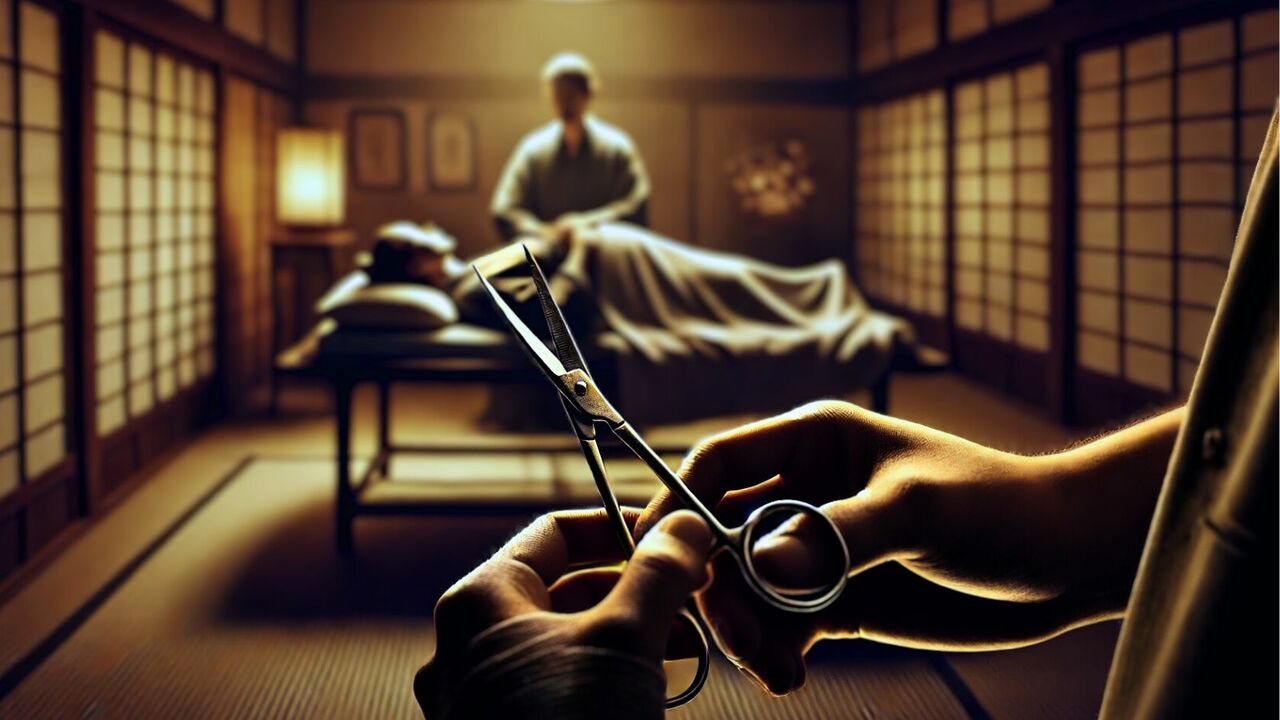第一章
一
万条がそんな感情を抱くようになったのは、それなりの理由があった。
五年前の御一新で、京都が都であることを体現する天皇が、まずいなくなった。皇族や公家もそれに付き従い、ほとんどが東京へと移住してしまった。
それだけではなかった。彼らを支えてきた商人や町人までもが東京へと去り、京都の街は徐々に活気を失って行ったのだ。嘉永三年(一八五〇年)に二十九万人を数えた人口は、明治五年に二十四万人まで減少していた。
御所の周囲に建ち並ぶ公家屋敷は、ほとんどが無人となってしまった。洛中の大名屋敷も同様で、みな売りに出されていた。幕末の動乱のさい、政治の中心となった京都は、どこもかしこも見る影なく寂れていた。
京都はどこに向かって行くのだろう──。
川端通を過ぎ、花見小路を南に見たとき、万条はまた不安がよぎった。その先に祇園があるが、倒幕の志士たちが通い詰めた往時の賑わいはなかった。
とはいえ十八歳の自分には、若さだけは溢れるほどの自信があった。ただその力のやり場が、まだ見つからなかっただけだった。
東大路通を過ぎたあたりで、万条はようやく気持ちが落ち着いてきた。そして三条通を、さらに東へ足を進めた。
歩きながら、急に懐かしい顔が思い出された。
東京に行ってしまった三条実美公は、今頃どうしているのだろう、それに、岩倉具視公は相変わらずなのか、などと頭に浮かんでは消えた。
小さい頃、二人にはよく遊んでもらった。今は、新政府の重鎮として大いに権勢をふるっていると伝え聞いており、そんな彼らに思いを巡らしているときだった。