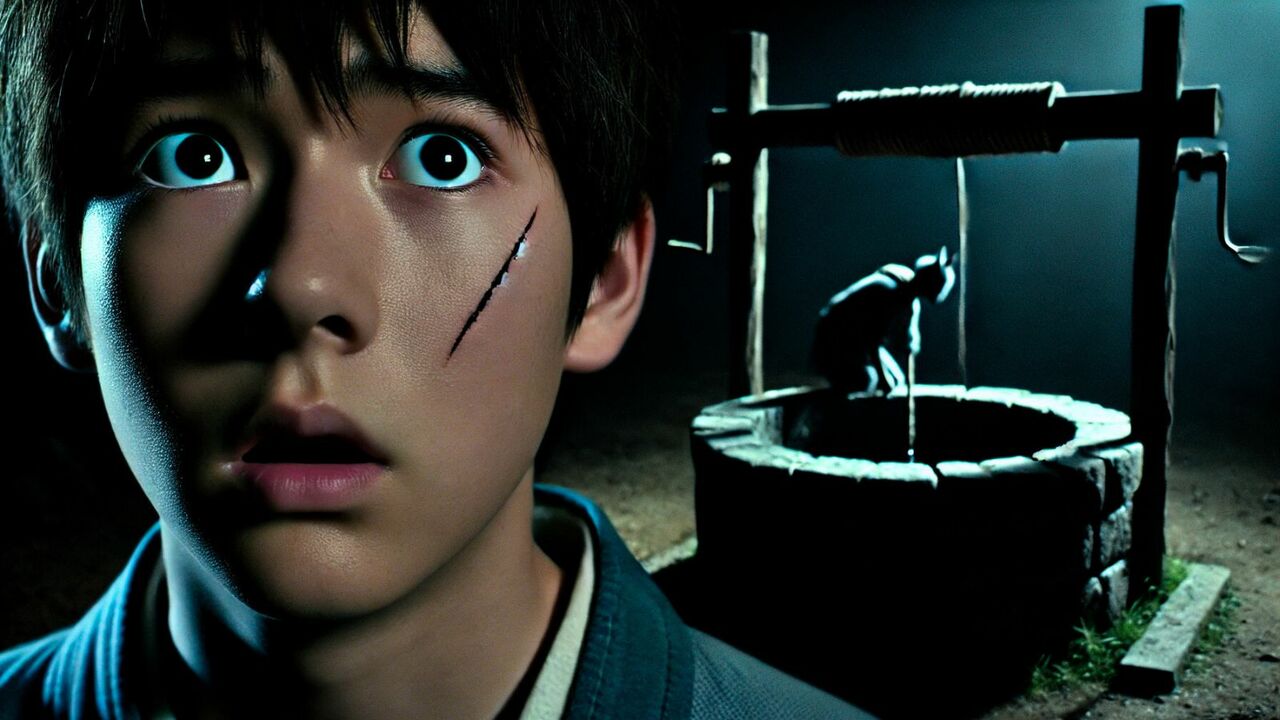ごろごろと雷が鳴り響き、初夏の日中にどこか涼しく感じる湿った風が吹き始めた。空に敷き詰められた雲により、三丈の高さから見下ろす荒川も湖沼群も、本丸居館も薄暗く感じさせる。立ち働く下男下女達も、嵐の予兆にどこか忙しなかった。
源五郎は本丸居館内にある自室に面した中庭に、つき丸を連れ込み放し遊ばせてやっていた。つき丸は腹が満たされたものか元気に中庭を駆けまわり、端から端へ、ぴょんぴょんと飛び跳ねるかのように走っては止まり、走っては止まりを繰り返している。
そんな様子を縁に座り、源五郎は笑顔で見守っていた。そのうち、つき丸は落ちた木の枝を拾って来て、源五郎の前で尻尾を振りながら後ろ足を立たせ、前足は伏せて枝を咥え首を振っている。
「何だ? 俺と勝負しようてか?」
笑いながらその枝を取ろうとすると、つき丸はその枝を咥えたまま引っ張った。
「ぬっ、やるな」
笑顔の源五郎が四つん這いになり、つき丸の力に合わせ拮抗するように引っ張って遊んでやる。つき丸は飽く事なく繰り返し、源五郎はそれに付き合ってやった。
そこにたまたま古河足利幕下の大石石見守が配下の者を連れ通りかかった。石見守は武州葛西城主で、太田資頼の娘が嫁いでおり縁戚にあたる。その正室は現当主資顕にとっては妹に、源五郎には姉にあたるが、長い患いから快方し床払いが出来たと、所用かねがね報告に訪れていた。
資顕に報告後、御対面所から下がる途中、源五郎の姿を見かけたのだ。弟君が御乱心なされた……。
大石石見守は、ぎょっとして足を止め配下の者に、
「何だあれは? あれではまるで、うつけではないか?」
呆れ果てた様子で言ったものだ。
そんな事を言われていると知ってか知らずか、源五郎はお構いなしに「つき丸」に付き合ってやっていた。