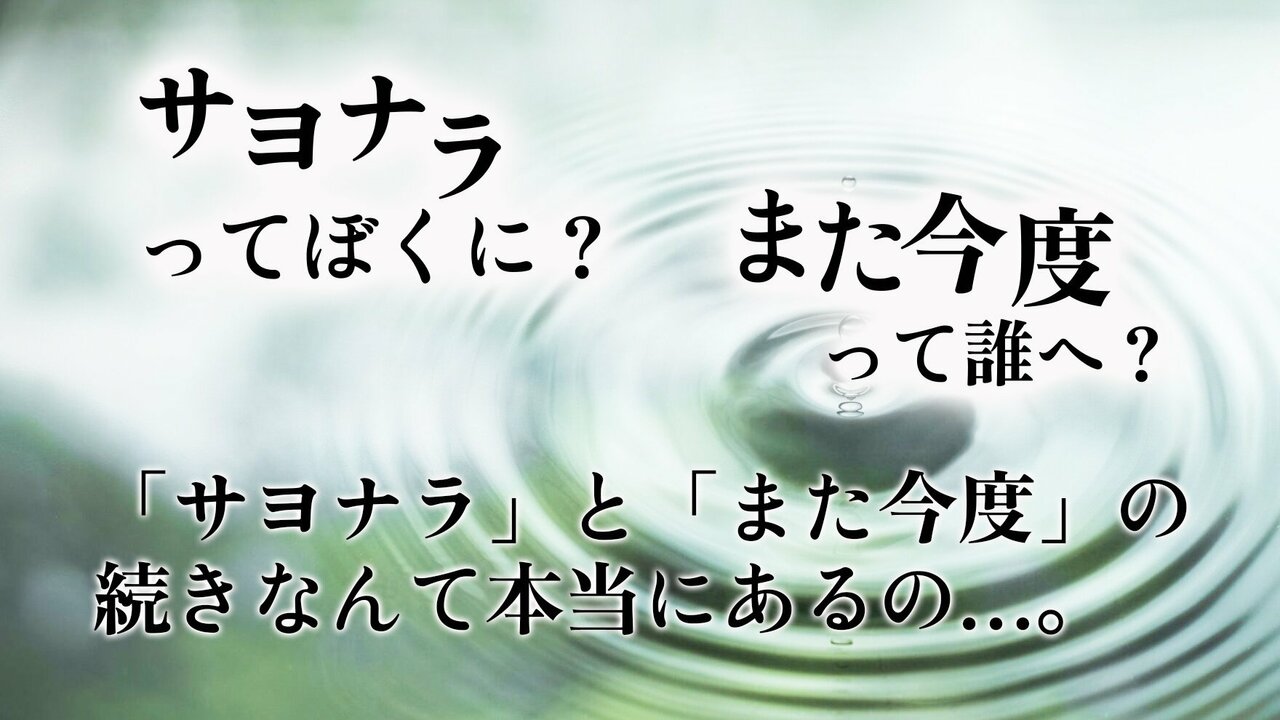ひとしずく
ひとしずくの兄弟たちの内に灯った熱は、少しずつ互いに伝播していきました。そのせいか、みんな少しずつ浮かれ始めていました。彼らは、雪が溶けるにつれて広がってゆく視界の先を眺めては、「楽しみだね」「楽しみだね」と口をそろえて言いました。
これから生まれ出る世界は、諸手を広げて自分たちを待っている。そのことが、嬉しくて嬉しくてたまりません。春を待つ雪たちは、いつでもこうして黄色い声を上げながら、来るべき暖かなときを待ち望んでいるのです。
ひとしずくももちろん、兄弟たちと同じように期待に胸をときめかせていました。けれど同時に、半透明の水の膜を通して見える世界は輪郭がつかめぬほどおぼろげで、灰色や黒の陰影の濃淡に緑が重なり合うようにしか見えなかったので、ひとりどきどきしていました。
兄弟たちの多くは、一滴としての空への旅を少なくとも一度は巡ったと見えてそれらの影が何であるかをよく知っていました。そのためにいずれの兄弟たちも大変余裕があり、この先の世界でこれから起こりうることすべてにみんな胸を昂らせ、陽気に破顏していました。
けれども、まだ何も見聞きしたことがないひとしずくにとっては、まわりの雪がすべてなくなり、視界がすっきりと晴れやかになるまでは、何も見えないのと同義でした。
ひとしずくは、自分ひとりだけが違う世界を見ているようで、とても心細くなりました。兄弟たちの嬉しそうな表情を見れば、こわいことなど何もないのだということはよくわかりました。けれどそうは言っても、からだが重たく感じるようなじっとりとした不安は、簡単に拭えるものではありません。
まわりの兄弟たちは、不透明な視界の先で何か動くものがあるたびに歓声をあげていました。ところがひとしずくは、兄弟たちの歓声が向けられているものが何なのかがわかりません。
さらに、それらの動くものは時折、バサバサッとか、ピウーーといった奇天烈な音を立てるので、そのたびにひとしずくはぎくりとして、まわりの様子をうかがうのでした。
突然、彼らの視界の中に、より一段と濃い灰色の何かがかぶさって、ほとんど何も見えなくなることがありました。それは、何のこともない、梢の先で溶かされた雪の塊がクマザサの葉の上にぼとりと落ちて滑ってきただけのことでした。
兄弟たちは思いがけないとびきり面白い見世物に、声を立てて笑いました。けれどもひとしずくだけは、巨大な翳りが自分たちの世界に突然現れたのだと大変慄き、思わず声を上げてしまったのです。そのとき、兄弟たちがいっせいにひとしずくの方を振り向いたので、ひとしずくはとても恥ずかしくなりました。