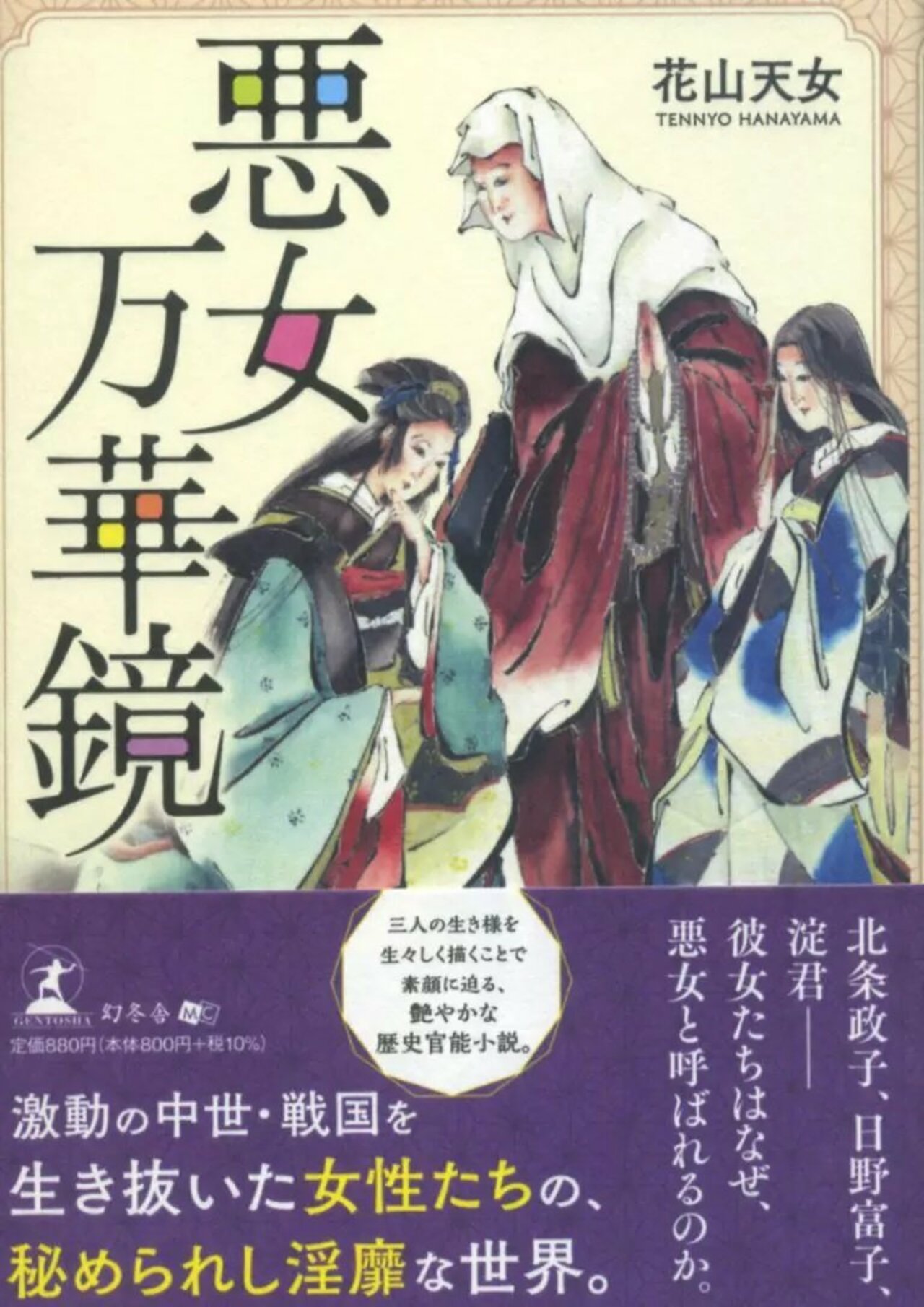第1部 政子狂乱録
二 新鉢を割る
ついでながら、男は淫水を早く漏らさず先に女に気を遣らせるのがよい。男の淫精が漏れそうになったら止めなければならない。それには、男の尻の戸渡(蟻の戸渡ともいわれ、肛門と性器の間の皮膚が鎖状になった部分)を中指で時々押さえてやると淫精の洩れは遅くなる。この秘法は、平安時代初期の貴族・歌人で希代の色豪、在原業平が伝えた大秘密であるので、これを鍛錬して我が物とし女をいつも快楽に耽溺させるのが男の甲斐性と言うものだ。
「あはッ、ふあああぁぁぁぁっ……あなた、何だか政子のあそこが蕩けそう、しっかり私を離さないでくださいな」
男は、ここを先途と最深部の壁まで突き進ませた剛槍を、ゆっくりと引き抜きながら、あらわになった毛と太腿をのぞいてみる。男の剛根の抜き差しで陥没していた二葉の粘膜は、蜜で充満した内壁を道連れにめくれ、なぎ倒された恥毛がキラキラと光を放ちながら猥らがましく逆立っている。
「はあっ、もう死にそう、この身を天国につれていかっしゃれませな! はっ、はっ……」
まるで打ち上げ花火のように、女は白目を剥いて顔をのけ反らせ、下腹部が大きく波打ち、男根を離すまいと必死に腰を持ち上げ、時折ブルブルツと美しい下肢を痙攣させ、幾度となく歓びの絶叫を上げる。
「あーっ・・・・・・・・■※?△☆?」
白い喉首をのけ反らした政子は、最後の一声を放った。
「……今、私は死んで極楽を見たようですわ、お憎らし。貴方のお道具には何か特別のお力でも宿っているのかしら」
愛しい男と、初めてこの世とも思えぬ快楽を交わすことができた新妻は、物憂げな表情で夫の胸に唇を這わせた。
「政子、それは死んだというのではなく、気が逝ったというのですよ。男には陽精、女には陰精というものがあって、戦もそろそろ終わりころになると、この精が出るような、出ないような気分になって、総身の肉体が骨の髄まで痺れてしまうのです。この精が出てしまうことを、気が逝ったというのですよ」
それでも、今初めて男を経験した政子には理解できないらしい。
「男と女が媾合っても、男は一度逝くだけなのです。でも女は何回も逝くことができるから気持ちはよいのですが死んだわけではありません。媾合の歓びは、かたじけなくも男女の道、自然の摂理といえましょう」
政子は何となく理解したようでも、ひと理屈つけ加えるのを忘れなかった。
「貴方、本当にご苦労様でした。お前様のお道具は政子にとって大切な宝物だということがよく解りました。その元気なところを無くさないうちに、又、明日の晩も致しましょう、お願いできますか。これほどよいことを今日限りというのなら、私、あなたの前で死んでしまいますから」
新妻は、さすがに顔を赤らめ、間が悪そうに髪をなでた。
「でも、こんな大切なご一物は私のものだけにして、ほかの所では決して使わないでくださいな」
と、一言付け加えるのを忘れない、新しい夫に一本釘を打った言い方だった。今日の政子は可愛かったけれど、彼女は決して自分の意志を曲げない中々の女性と見える。頼朝のこれまでの近郷の娘などとの経験からしても、未通女というものは、一旦男と情を通じてしまうと、男の身体も心も自分だけのものと勘違いをする。