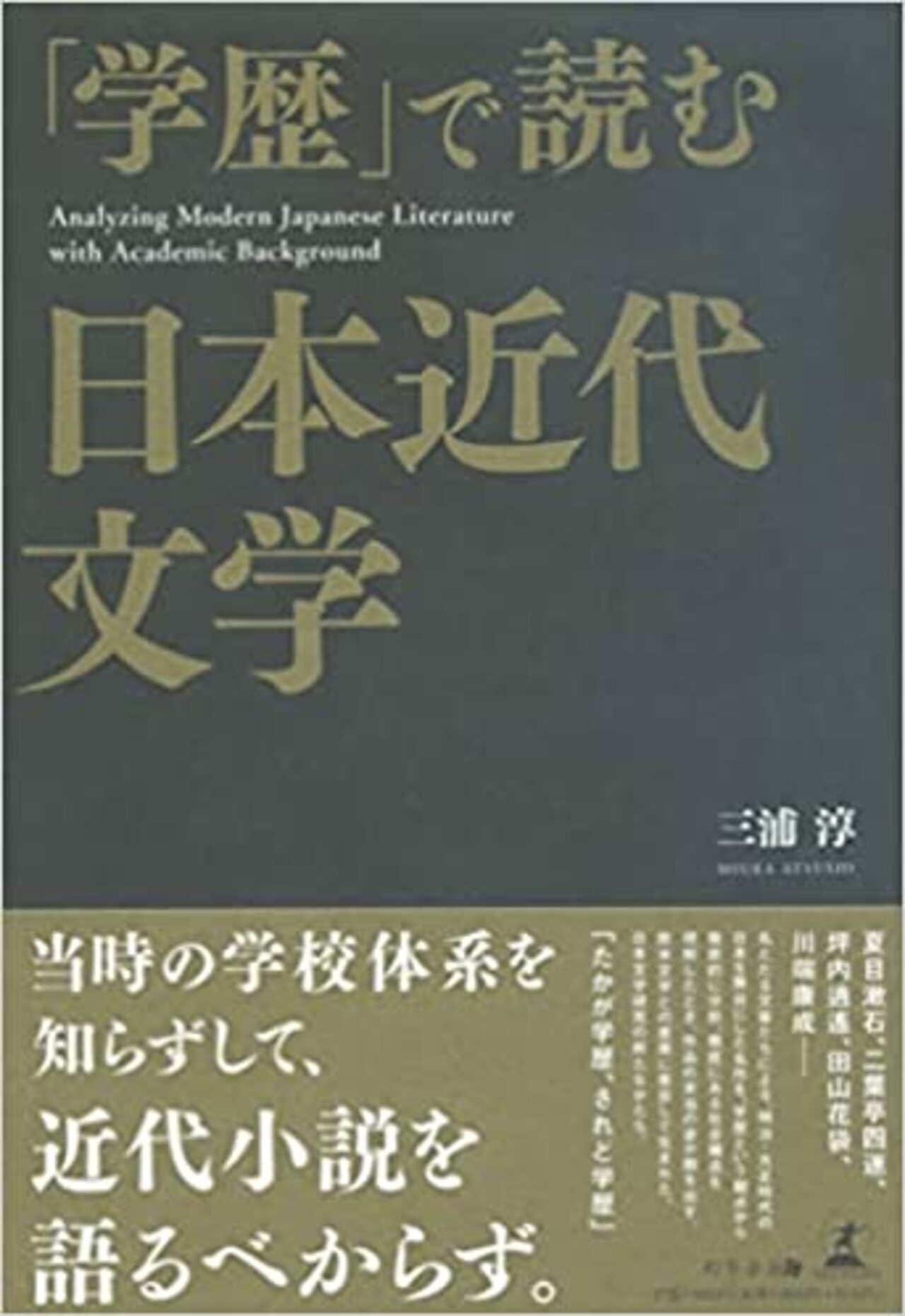「小説の裨益」は、つまり小説は何の役に立つのかということですが、逍遙は以下のように主張しています。一は「人の気格を高尚になす」、二は「人を勧奨懲ちょう誡かいなす」、つまり勧善懲悪ということです。三「正史の補遺となる」は、通常の歴史記述が及ばない人間模様や心理を描くことが小説にはできると言っているのです。四が「文学の師表となる」、つまり文章表現の模範が小説にはある、ということです。最後に、東洋の小説はローマンスにとどまってきたと述べ、改めて西洋の小説を模範とすべきだと訴えています。
以上が「上巻」です。
まとめて見ると、こうした芸術・文学史や小説の変遷の捉え方は、一九世紀を基盤にした、主として英国やフランスの文学を模範とする見方であると言えます。
二〇世紀に入ると、意識の流れに目を向けたり夢や神話に人間の隠された欲望や本質を見ようとするなどの新しい潮流が生まれてくるのですが、一九世紀末に書かれた『小説神髄』にそうした観点を求めるのは無理な話で、逍遙は東京大学で英国人の教師から教わった文学論や小説理論を基盤にして、こうした分類にまとめ上げたのだと考えられます。
こうした文学観に、当時流行していた進化論の影が認められるという指摘もあります。ダーウィンの進化論は単に生物学に影響を与えたにとどまらず、社会の見方にも進化論を適用するという方向性を生みました。
そうしたソーシャル・ダーウィニズムの代表的な論客がハーバード・スペンサーであり、その影響下にあったエドワード・S・モースとアーネスト・フェノロサが明治期に相次いで来日し、できたばかりの東京大学でお雇い外国人として講義を行ったのでした。
キリスト教の支配下にあるヨーロッパではダーウィニズムへの批判も強かったのに対し、キリスト教の天地創造説から自由な日本人にはむしろダーウィニズム、そしてソーシャル・ダーウィニズムが素直に受け入れられたのです。
彼らが東京大学で講義をしていた時期は逍遙が東大に学んでいた時期と重なります。逍遙の『小説神髄』はダーウィニズムに基づく文学進化論であり、それは逍遙がお雇い外国人を通してハーバード・スペンサーを受容したからだと江藤淳は述べています。
(『漱石とその時代 第一部』)
いずれにせよ、一九世紀末に書かれたという時代性を考えれば、逍遙の小説理論(というより主として英国から輸入した理論)は間違ってはいませんし、ノベルとローマンスの区別などは二〇世紀後半になってもそれなりに有効な図式として通っていました。
例えば日本では一九七四年に『シンポジウム英米文学』というシリーズ本の一冊として『ノヴェルとロマンス』が出ており、英米文学者ばかりでなくフランス文学者をもまじえて両者の違いや分類の流動性が検討されています。