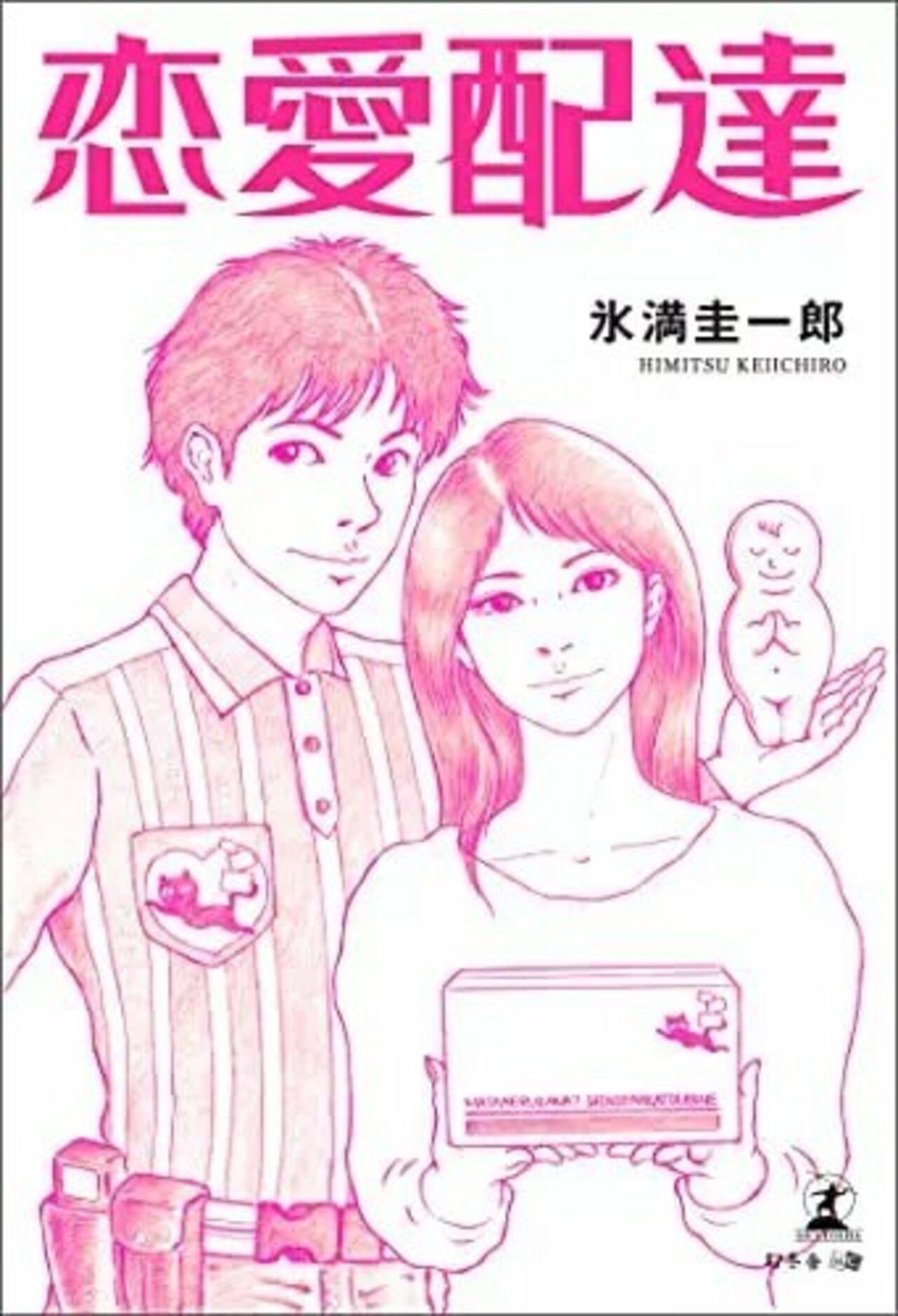【前回の記事を読む】【小説】もう会えないと思っていた最愛の人を花屋で発見するも…
第一 雑歌の章その一
鵲の橋
「今のご気分や調子はどうですか」と聞かれたが、それがお勧めの花とどう関わるのか理解できず、どう答えたらいいのかもわからずに、「……えぇと」と上を向いて考えていると、「難しく考えないでください。現在の体調です」と女性が助けてくれる。
「暗闇に灯りを見つけたようなほっとした気持ちです」と今度は正直に答えるが、緊張に包まれた僕の答えが女性の質問と微妙にずれていることに気づかなかった。
「体調が悪いとかお疲れではないですね」と聞かれ、「はい」と答えて自分のズレに気づく。
「お好きな色はありますか」との言葉に、「それは……」と言って僕は凍り付いてしまった。
高校二年の時に彼女から同じことを聞かれたことを思い出させる……これはデジャブなのか。
どうしてあの時と同じことを懐かしい彼女の声色を使い再び自分に問うのか、それはあまりにも酷じゃないか。でも仕方なく、あの日と同じように答える。
女性がもし自分の探している彼女本人ならその答えを知っているはずなのにと思いながら。
「好きな色も嫌いな色も特にありません」と言って期待して待つ。……女性が、「あの時と同じ答えをするんですね」と言ってくれることを。
「そうですか。花はどちらに飾りますか。玄関ですか、それともご自分のお部屋ですか」
残念ながら自分の儚い期待はいとも簡単に流されて女性は次の質問に移ってしまった。
「自分の部屋に飾ります」と落胆して僕は答えた。
「お部屋に置いて気分が落ち着くのと明るいのではどちらの花がよろしいですか」
「落ち着く花がいいと思います」
「そうですね、わかりました」と言って女性はにっこり微笑むと、「この花はいかがですか」と水色の花に手を伸ばす。自分がそれに頷くのを確認し、「こちらの花も併せてもよろしいですか」と青紫の花にも女性は手を差し伸べている。
「お願いします」と言って僕が周りを見ると店内には色々な種類の花がきちんと並び、ピンク、オレンジ、青、赤、黄、紫、白の豊かな色彩が店をきらびやかに飾っている。
それぞれの花にゆっくりと視線を移してみるとそこに明らかな違和感がある。それは自分が見ているのとは逆の不思議な感覚……間違いなく、たくさんの花からの視線を自分が集めている。
だが、それは決して不快な思いではなく、自分を優しく労わってくれる心地良さを感じる。