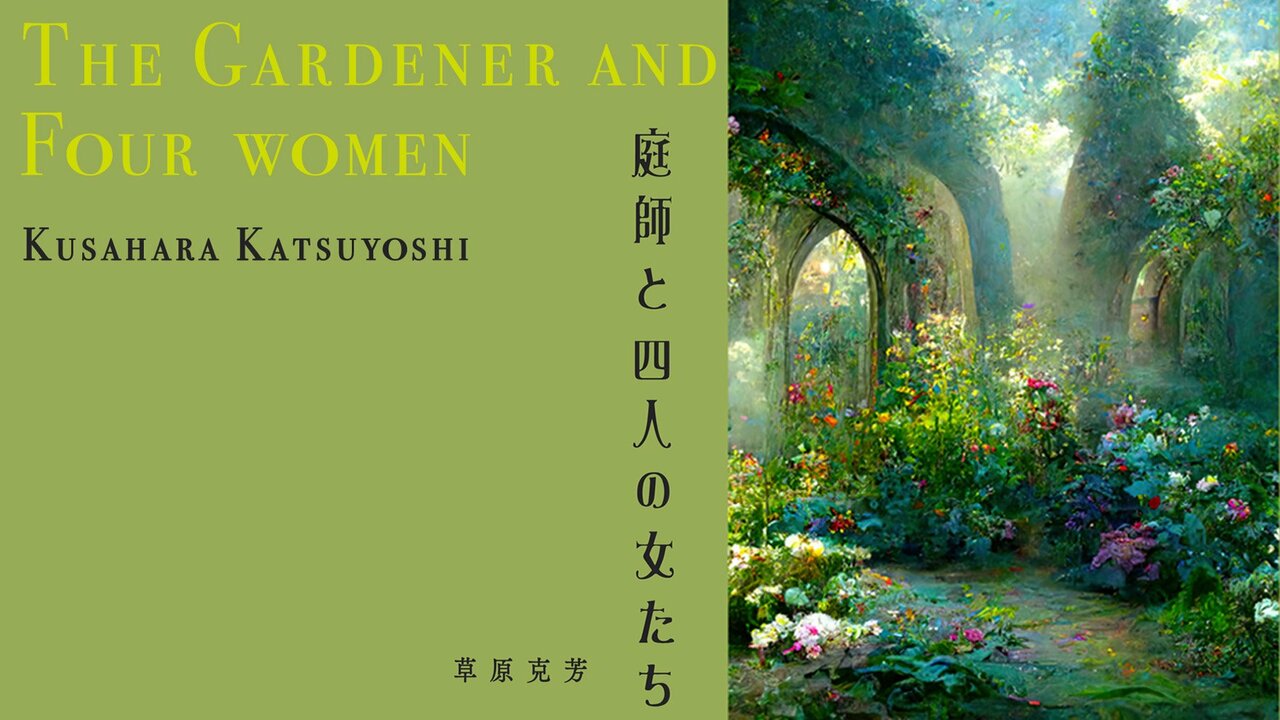庭師と四人の女たち
1
この庭の西側の通路手前には、ハエジゴクや、ウツボカズラやモウセンゴケなど、食虫植物ばかり生えている薄気味の悪い一角があった。ときおりマス江はその片隅にしゃがみ込んで、緑色の口を開けてわが子のように待ち受けている植物たちに、羽虫や蝿などのエサを落とすという、奇妙な趣味があった。
小さな緑の魔物たちは、ほとんど彼女の一部となっており、物言わぬ食虫植物たちに、マス江はまるで、小さな雛に対するような愛情を注いでいた。
睦子もこの小さな日陰の一角だけは、「マス江さんの庭」とか「袋田植物園」とか呼んで、それとなく黙認していた。白亜の列柱下の陽の当たる一角にある店主の小さなハーブ園とは、じつに好対照な風情だった。そちらにはラベンダーやカモミールが植えられていた。
「大盛況だったわ。パンタレイのお客さんもいっぱい来てくれたの。ほら、大学生の五朗ちゃんとか。クルマ出して荷物運んでくれたのよ。アメフト? アメラグ? 何でも、そういうのやってる子よ。あ、そうそう。最近見かけなかった五丁目の二村さんも来たわ。古い額縁を買ってくれたの」
「二村っていうのは、あの、しんねりむっつりした、感じの悪い中年男だろ。ちょっと、ノイローゼみたいな」
「そうそう。二村良夫さんだったか、良政さんだったか」
「どっちでもいいだろ、あんなの」
「ええ、その良夫さんだったか、良政さんは、何でもタウン誌とか、官公庁の広報紙やなんか編集してるみたいよ。この近くのアパートに仕事部屋を借りてるのよ。ああ見えて、昔は大手企業のPR誌とかもやってて、羽振りが良かったらしいの。赤坂だか乃木坂に事務所構えて、たいそう忙しかったらしいわ。
その後、会社閉じて借金も抱えて、しんどくなったとか。この店でも、よくコップの水で精神安定剤飲んでいるわ。ときどき動悸が激しくなるらしいの。あたし、あの人、カルシウムが欠乏してるんじゃないかと思うんだけど。でも、いい人よ。第一印象は、とっても感じ悪いけどね」